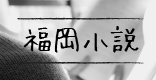第1章:ひかり(小説「悔恨」)
記事内にプロモーションを含む場合があります

『もう終わりかな。』
蒸し暑い7月の、眩しいひかりが差し込む午後だった。
弘一朗は大きなため息と一緒に吐き出すように呟いた。
頭もひどく痛む。
気が付けば、昨夜事務所に入ってから、一度も外出していない。
厳密には、ソファーに腰を降ろしたまま、全く移動していないことにウンザリとしながら最後の一本となった煙草に火をつけた。
(純二に買って来させるか。)気怠く携帯電話に手を掛けたところで止めた。
(後二時間は戻ってこないだろう。)
昨夜は一睡もしていない。このまま少し仮眠を摂るか。
大きく背伸びし、ゆっくりとその重たい腰を上げた。
「起業したからには会社をどんどん大きくしよう。」
「金運が舞い込むようにこの黄色いソファーセットを購入しよう。何しろ安い。」
なんだか恰好悪いなと思ったが、純二に押し切られ購入を決めた黄色いソファーから。
窓から見下ろす景色は自分のそれとは違って見えた。
地元住人憩いの大濠公園では、一心不乱にジョギングするもの、にこやかにベビ-カーを押しながら談笑する若いお母さんたち、まだまだ付き合いはじめか、並んで腰を掛けているベンチからは、恋人同士の距離感とは相反する間が漂っている。
さっきまでの眩しいひかりが、暖かなやさしいひかりに変わった。
会社存続の危機の中、弘一朗は昨夜までとは明らかに異なる雰囲気を発していた。
(純二が戻ってきたとき、居眠りしていたら危機感のない経営者だと思われるか?昨日慌てて事務所に来たから、路上に駐車した車は大丈夫か?普段なら気にも留めないような、
そんなふわふわとした感情が支配していた。)
そう言えば、少し腹も空いてきた。
弘一朗と純二は高校時代からの友人だった。
福岡県北九州市のはずれにある、それはもうため息がでるくらいの、田舎町の高校だった。
福岡県北部では一応の進学校として名高い。また、県下でも指折りの歴史を誇る学び舎のお陰か、年配の方々からは、「とても素晴らしい高校を卒業していますね。」とよく言われたものである。
ただし、現在では国立・有名私立大学進学を目指す特進クラスと、三流大学に滑り込みで入学するのが精一杯の普通クラスに分かれている。
初めてのクラス分けの時、弘一朗と純二は出会った。
俺達は、と言えば、当然後者の方だ。
思えば、二人には共通点が多かった。
中学時代は共にバスケット部で汗を流した。
当時流行りのバンド活動にも夢中になっていた。
お互いに優秀な姉がいたのだが、不思議と二人は、どうせかなわないと拗ねることも、劣等感を抱くこともなかった。
(男の子には自由に、好きなことをやらせよう。)
お互いの両親ともにそのようなおおらかな想いで息子に接していたのだろう。弘一朗と純二はその意を汲んだか、はたまたその思いに付け込んだか、何れにしても、其々に高校生活を謳歌していくことになる。
その時はまだ、気が付かなかった。
二人は、薄氷の類似だということを。
一学年では同じクラス、同じバスケット部ということもあり、よく遊んだ。
高身長で運動神経抜群、中学生時代もそれなりの実績を残した純二と、平均身長で運動音痴というわけでは無かったが、走る・飛ぶといった先天性のそれらはからっきし、しかし、ボールや道具を使うことによって、それらしく見せることが非常に上手な弘一朗。
自ずと部活への取り組み方、ひいては評価も変わっていった。
弘一朗は退部した。
二人は今まで通りとは行かないまでもそれなりの友情関係を続けたが、それも次第に無くなっていった。
卒業式で一言二言話を交わしたのを最後に、それぞれの未来へ進んでいった。
それでも運命の歯車は二人を繋ぐ。
弘一朗は事務所のドアを開けた。
最寄りのコンビニエンスストアに向かう途中、昨夜路上に駐車した車を確認した。
そこは建物の敷地内ではなかったが、駐車禁止の標識もなく、行き止まりであった。大型車でもUターン可能なほどのくぼみがある、弘一朗のいつもの停車スペースだった。
(よかった。大丈夫だった。)
駐車禁止の警告もなかったが、その日は近くのコインパーキングに駐車し直した。
コンビニエンスストアに入ると真っ先にアイスコーヒーをかごに入れた。
お腹は空いていたが、何故か、おにぎりのひとつも手に取ることはなかった。
『マルボーロメンソールライト一つ。』無愛想に伝えると、それに応えたかの様に店員も無表情で会計を済ませた。
事務所に戻りながら、ふとコインパーキングに停めた自家用車に目を遣った。
世間一般には高級国産車といわれる黒塗りのセダンだ。
(随分と汚れている、洗車でも行くか。)
これまでに車は数台乗り換えてきたが、気まぐれで大晦日に洗車したことが数回ある程度で、そんなことを思ったことなど無かった。
だが結局、洗車しようとはしなかった。
事務所に戻り、煙草の封を解いた。そして、思い出の黄色いソファーに深々と腰を沈め、徐に煙草に火を付けた。
大きく一回燻らせてところで、アイスコーヒーを一口含んだ。
喉を通り、食道を下降し、胃に辿り着くのが分かった。
その感覚と同時にあることが頭をよぎった。
(純二が戻ってきたときに思い切り、驚かせてやろう。明日の支払期限に不足している2千万円を集めるため、純二を含めた複数の幹部社員もここ数日不眠不休だ。
幸いここには純二しか来ない。)
≪通常のオフィス近くに、私と純二、あともう一人だけしか存在を知らない隠れ事務所を借りていた。≫
思い入れのある黄色いソファーも廃棄するには勿体ないと、メインオフィスから移動させてきたものだ。
さっきの電話から、あまり期待できない状況は把握出来た。
一度リセットしたい。
事業も、純二との関係性も。
ただ何かキッカケが欲しい。
そうだ自殺したふりをして驚かせてやろう。
(純二のやつ、慌てふためくぞ。きっと。)
翌日に倒産の危機が迫っていることは全く気にならなくなっていた。
昨夜、いやここ数日の不安が嘘のように、純二は驚くかな?ひょっとしてその場に座りこんじゃうかな?などとくだらない思いを巡らせながら、気が付くと笑いが止まらなくなっていた。
少し湿ったワイシャツの首元を緩め、最近では一番のお気に入りとなっているGUCCIの青いドット柄のネクタイを解いて、その時を待った。
黄色いソファーの横にあるドアノブにネクタイをかけ、座った状態で首に巻く。
玄関が開いたと同時にほんの少し力を抜いて首を掲げる。
部屋の内扉が開いたとき、顔面蒼白の純二に
『驚いたか?金策ご苦労様。一度死んだつもりでやり直そう。』笑顔で語りかけよう。
イメージはばっちりだ。
どれくらい時間が経っただろうか?
途中煙草でも燻らせたい気分だったが、その時に戻ってきたらすぐに芝居がばれてしまう。
ドアノブに吊るされたネクタイに首をあずけ、じっとしているのは良い気分のはずはないが、不思議と苦にならない。
≪ガチャツ≫
突然に玄関が開いた。続いてすぐに内扉が開くはずだ。
よし、今だ。ゆっくりと首をかかげ、お尻を少し前にずらした。
「はらちゃん!」純二の叫び声が聞こえたと同時に、目の前を真っ白な眩いひかりが弘一朗を襲った。
原田弘一朗 32才 起業から6年が過ぎた7月。
夕焼け前の妖艶なひかりに部屋全体が包まれた蒸し暑い日の出来事である。
1章:ひかり
2章:友情
3章:変化
4章:親子の関係
5章:勝負
6章:破滅
7章:悟の狙い
8章:父の想い
9章:純二の視点
10章:回想
最終章:闇の真実
投稿者のプロフィール
最新の投稿
-

-
2024.11.14.
レジャー・観光 【2024年】福岡での七五三のお祝い いつする?親の服装は?着物レンタルは?神社でのお参りや写真撮影のマナー -

-
2024.11.11.
レジャー・観光 紅葉八幡宮「ライトアップ&もみじ祭」2024年の紅葉の見どころと開催情報 -
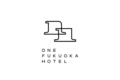
-
2024.11.06.
ホテル・宿泊 2025年4月24日開業「ONE FUKUOKA HOTEL」天神の新ランドマーク!アクセス・客室・施設情報まとめ -

-
2024.10.30.
レジャー・観光 ベイサイドプレイス博多イルミネーション2024-2025 今年も11月1日から開催!港と光の共演