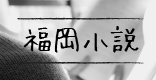第八話 深夜の多忙(小説:モテすぎた男)
記事内にプロモーションを含む場合があります

その後は特に騒動もなく其々にクラブ「アマルフィ」を後にした。
特別に何も無いことが当たり前なのだが、今回のセミナーはトラブルが多すぎる。
「アマルフィ」を出た後、参加者たちがどのように別れて、はたまた連れだって飲み直しに行くのか、多少気にはなったが、これ以上のトラブルはウンザリだ。
田村は真っ直ぐに帰路に就いた。
宿泊予定のビジネスホテルに帰って早々に眠りに就きたい田村であったが、この夜、彼の部屋には何人もの来客があった。
「ふぅっ。長い一日だったなぁ。」
ホテルの部屋に入った田村は一瞬の静寂の中、長い一日の疲れを受付横の自動販売機で購入した缶ビールと共に流し込んだ。
シャワーでも浴びようと重たい腰を上げた時であっただろうか。
「コンコン」と扉をノックする音が聞こえてきた。
気だるい体を引きずるように扉のぞき穴に目を向けた。
おそらくは三上か、佐藤であろうと覗いたその先には、意外な人物が立っていた。
近藤将彦である。
「浜夕」で感情に任せて退席した彼は、その夜田村の部屋を訪れた。
「さあどうぞ中へお入り下さい。」
そう言って部屋の中へ近藤を招き入れた田村だったが、それは彼にとっても好都合であった。
藤原明日香の言う様にセミナーの主催者としてあのまま放置しておくことは出来なかった。
しかしながらこの面倒臭いタイプの男にどうアプローチを取るべきか悩む手間が省けた訳だ。
「近藤さん、災難でしたね。あなたが悪いと言う訳では無い。ただこのセミナーは講師の女性を口説く為の場ではありませんから。明日からもう一度セミナーにご参加頂くと言うのは難しいかもしれませんが、今回のセミナー代金はすべてお返し致しますし、彼女の方もこのまま何も無いようでしたら特段問題にもしないようです。」
近藤を窓際の小さな応接セットの椅子に案内しながら取りつく島のないよう雄弁に語ったつもりの田村だったが、思惑とは違う、げんなりとする面倒な返しが襲ってきた。
「違うんだな。お金が返してほしい訳では無い。ましてや無意味なセミナーに参加させてくれとお願いに来ている訳でもない。」
「では一体どういった用向きで御出でになったのでしょう?」
「私は藤原明日香さんと一緒になるべき人間です。それをあなたの無意味なセミナーが邪魔をしている。私はこのセミナーで初めて彼女に会ったのではない。その以前から私たちはお互いがお互いを引き付け合うようにして結びついている・・・。」
「邪魔をしているつもりはありませんが、一体何を仰りたいのか、さっぱりわかりませんが?」
「彼女をこの仕事から解放してほしい。今すぐに。」
「近藤さん、それはあなたの決めることでは無い。それどころかあまりに行きすぎた干渉だ。」
田村は少しばかり語気を強めて言ったが、この手の面倒な人間にそのようなテクニックは通用しないことは分かっている。
ここまで話して、時間を空けず藤原明日香にこのことを告げるか?または彼女には意中の相手がいることを近藤に伝えるか迷った。
が、後者を選択することで谷川旬と云う次の被害者が出るだけだということはすぐに想像できた。
ならば藤原明日香に伝えるか?不思議と彼女に迷惑であるとか、怯えるのではないかなどと云う想いに駆られることは無かった。
藤原明日香ならすべてを上手く鎮めてくれるのではないか?そんな考えに落ち着いていた。
「今から、彼女に連絡を取ってみます。彼女が何と言うかわかりませんが、もし可能であるなら私の部屋で話をされて見ては如何ですか?」
「なるほど。いい案ですね。」
近藤の回答を待たずして田村は藤原明日香の携帯電話を鳴らした。
電話口の彼女は直ぐにこの部屋へと来ると言う。
そのことを近藤に告げ、重たい沈黙の中、彼女の到着を待った。
10分もしない内に彼女は遣ってきた。
そこからは一瞬の嵐が通り過ぎるか如くだった。
部屋に入るや否や彼女は近藤の左頬を思いきり引っ叩いた。
そしてあまりのことに面を喰らっている近藤目掛けて一気に捲くし立てたのだ。
「城南区役所市民課で窓口業務をされている一人っ子の近藤さん。お父さんは大濠学園の校長先生、お母さんは義父から相続した立派なお宅で茶道の先生をしておられる絵に描いたような素敵な家庭で、何不自由なく親の言う通りの人生を歩んできた近藤将彦さん。
一人暮らしの女性の部屋に忍び込んだ間抜けな姿が監視カメラに記録されている近藤。
あんたの馬鹿げた思い込みでその幸せな家庭を壊すつもり?」
「・・・・・・・なんのことだか、あの、、藤原さん、、僕は、、」
明らかに挙動不審になり、その場から逃げたい衝動が抑えきれなくなったのであろう。
近藤は椅子をひっくり返すほど勢いよく立ち上がり、入口に体を向けて歩きだそうとした。
「待ちなさい。そんな逃げるように帰ることは無いわ。人生で会話を交わす人数なんて人口で考えたら僅かなものよ。あなたとは何かしらの縁があったのよ。それに、犯罪行為を働いたとは云え、姑息な行いは見られなかった。あなたと私は友達よ。
今はまだ単なる友達だけど、貴方次第で何か変わるかも知れない。私が欲しければ、抱きたいのであれば、そうなる可能性もゼロでは無いわ。
私の為になる事をしなさい。私たちは友達なの。わかった?」
「はい。わかりました。」
戸惑いながらも瞬時に、そして従順に、そう答えるのが精一杯の近藤に尚も藤原明日香は、
「わかったのならもう帰ったら。あと私の連絡先教えておくわ。貴方のも教えて。」
「それと、これだけは言っておくわ。私の人生は谷川旬のものだから。彼になにかあった時には許さないわよ。」
顔面蒼白の近藤は生気のない眼で軽く頷くと、そのまま部屋を後にした。
続けざまに藤原明日香も軽い会釈の後、田村の前を通り過ぎようとしていたその時に、
「藤原さん。・・・・・・・・・・・・・・・。」
「悪かったね。」
そう言うのが精一杯であった。
二人が部屋を後にした静寂に包まれた部屋で一人、もう温くなった缶ビール片手に椅子に掛けるでもなくぼんやりと外のネオンに目を向けていた。
藤原明日香、想像を超えていた。
どこか神秘的で落ち着き払っていながら、時折見せる屈託のない笑顔。
しかしその裏には言いようのない影がチラつく。
本人から聞いた子供の時の出来事が彼女をそうさせたのか?
谷川旬に対する異常なまでの想いは本物なのか?そうだとすればそれはどのようにして育まれてきたものなのか?
近藤と相対した時の言動、情報収集能力その全てが謎に包まれている。
彼女が近藤を嵌めたのか?
今後彼女は近藤を利用するのだろうか?
いや、近藤だけでは無い。彼女に係わるすべての男達をその影に引きずり込んで行く気であろうか?
だとすれば当の自分も何らかの歯車に組み込まれてしまうのであろうか?
佐藤吉備の言う通り、彼の会社会長の愛人と云う話、強ち間違いではなかろう。
いろいろな思いが頭の中を駆け巡った後、ひとつの結論を出した。
佐藤にいち早く此処までの詳細を話し、この件から身を引くということを。
それから20分後には田村は小さな応接セットで佐藤吉備と向き合っていた。
「そうですか。一筋縄では行かないですね。」
これまでの経緯を聞いた佐藤は小さく言った。
「佐藤さん、悪いことは言わない。手を引いた方がいい。
私も少なからず人生経験を積んで来たつもりですが、あのような女性に会ったことがない。いや、別に彼女が詐欺を働くであるとか、魔性の女であるとかそんな事が言いたい訳では無いですよ。」
「わかります。彼女からはそのような邪心は感じない。
ただ、その話を聞いて尚、いやより一層彼女に惹かれてしまう。」
「佐藤さんのお気持ちは分らないでもない。御社の会長の愛人であるリスクであるとか、彼女の得体の知れない素性であるとかそのようなことは逆にその想いを増幅させることだってあるでしょう。
でも、一点。彼女が谷川さんに心底惚れていると言う事実は超えられない大きな障壁です。」
「確かにそれは問題ですね。ただ、私自身の考えがまだ固まっていない。」
「と、言いますと?」
田村の問いに佐藤は苦い笑みを浮かべて答えた。
「彼女と本気で交際して、ゆくゆくは結婚というゴールを意識するのか、それとも単なる火遊びと言うか、素敵な女性に振り回されてみたいと願っているのか、、、、あと一つ、尊敬して已まない会長の愛人という立場が私を駆り立てているのか・・・・。」
「何れにせよ佐藤さん、・・・私の手に負える相手では無い。申し訳ないが」
最後まで言わせることなく佐藤が返した。
「大丈夫です。言いにくい事や、個人の情報までお話頂きましてありがとうございます。
お互い今回伝えた個人に関する情報は聞かなかったことにしましょう。ただ、今後も何か相談したい事柄に当たりましたら、連絡取らせて頂いても構いませんか?」
「そうですね。個人情報の部分は聞かなかったことにする方が賢明ですね。連絡頂くのは構いませんが、あまりお役には立てないと思いますが・・・・。」
「ありがとうございます。それでは私は田村さんの教えを忠実に実行して、次なる恋のお相手を探すとしますか。」
そう言って佐藤は部屋を後にした。
一時は金儲けの種になるかとも思われた案件だったが、きっぱりと断って正解だと思うと同時に、これで藤原明日香を裏切らなくて済むのだと言う不思議な安堵感に包まれていた。
一方、田村の部屋を出た佐藤はすぐさま携帯を取り出した。
「佐藤です。ええ、そうです。間違いありません。それともう一つ朗報があります。それは月曜日にお話しします。はい、大丈夫です。そのまま進めて問題ないと思います。
そこの部分はご安心ください。録音データを改ざんします。何かあれば、田村氏が吹聴したということに。はい、わかりました。」
不敵な笑みを浮かべ自身の部屋へと戻って行った。
同じ頃、クラブ「アマルフィ」を出た後、真っすぐホテルに戻った和田健は真っ暗い部屋の中で、やけに目に刺さるテレビの明りにうんざりとして、電源をOFFにした。
「アマルフィ」を出て直ぐ、「次、どこかで一杯やりませんか?」と言う三上の誘いは断った。
暫くするとその静寂に耐え切れなくなり、またテレビの電源を入れた。
幾度かそれを繰り返した後、近藤は部屋を出てある場所へ向かった。
“コン、コン、”部屋の扉をノックしたが応答は無かった。
三上の部屋だ。
この時、三上と出会えていれば、いや、この後田村の部屋に行きさえしなければ、彼は苛苛しい頻雑に巻き込まれることもなかっただろう。
“コン、コン、”のぞき穴から見えたのは近藤であった。
その時田村は、毛利に電話をしていた。
二度、三度と鳴らしては見たものの、応答は無く、結局その日折り返しの連絡が掛かって来ることも無かった。
「やぁ、いらっしゃい。」
そう言うと、近藤を部屋へと招き入れた。
「すいません。突然。大丈夫でしたか?」
「ええ、構いません。丁度電話も終わったところでしたから・・・。」
「それなら良かったです。いや、佐藤さんがいらっしゃって居たのではないかなぁと思ったものですから。」
「えっ、どうしてまた?」
「たまたま佐藤さんの後姿と電話口の話声が聞こえたものですから・・・。」
「そういうことですか。ええ、先程少しお見えになっていましたよ。」
少しばかりドキッとしたが、なにも悪いことをしていたわけでは無い。
隠す必要はあるまいと事実を告げた。
「で、どうされました?先程の件ですか?」
「それもありますが、何となく田村さんとお話ししたいと思いまして。」
「それは光栄です。何れにしても先ずは三上さんの件からお話しして、お互いすっきりしましょうか?」
田村の投げ掛けに和田も応じた。
「すいません。僕が変なこと言ったばかりに余計な気を揉ませてしまって。」
「とんでもない。お話し出来る所は全て正直にお伝えしましょう。
先ず、私と三上さんは以前からの知り合いです。私のセミナー事業を応援して下さっています。後、これも正直にお話ししておきましょう。
私と毛利さんも知り合いです。知り合いと言うべきか、幼馴染です。」
「毛利さんと?」
「ええ、毛利の奴、奥さんに愛想尽かされたようでしてね。私も独り身ですからよく彼のところで食事をするのですが、その時彼が参加したいと言って来ました。
ただ、恐らく一人で参加するのが嫌だったのでしょう。知り合いに声を掛けて一緒に参加したようです。私としてはどなたと何方がお知り合いであるとか云うことに興味は無い。
ですから、毛利の知り合いが誰なのかまでは把握していません。
が、おおよそ想像は付きます。瀬尾さんでしょうね。」
これには和田も同調した。
「多分そうでしょうね。でも前回も瀬尾さんはいらっしゃいませんでしたか?」
「そうです。そうです。単なる偶然でしょうね。」
「そうなると、明石さんもお知り合いではないでしょうか?」
「どうでしょうか?そこまでは分かりません。毛利とは年齢的にもそれ以外においても接点は少なそうですが、もしかすると瀬尾さんのお知り合いかも知れませんね。」
「確かに。そう考えると自由時間でのあの雰囲気は説明が付きます。」
「ああ、和田さんの仰っていた異様な雰囲気とはそのことだったんですか?」
田村の問いに和田は少し考え、間を空けて答えた。
「それが全てでは無いのですが、少しだけパズルが埋まった気がします。」
「なんだか探偵みたいですね和田さん。」
「いやぁ、毎日暇を持て余しておりまして、人間観察は私の趣味みたいなものです。
でも、そうなると、クラブ「アマルフィ」での毛利さんの瀬尾さんに対する態度は理解出来ても、それ以前の会場での立ち振る舞いは違和感がありますね。」
初めこそ、どうでもいい和田の推理に付き合う気も無かった田村であったが、次第と本気で聞くようになって行った。
「と言いますと?」
「だって、お一人で参加することに躊躇いがあって瀬尾さんに声を掛けた訳でしょう?
その割にはお二人が会場でお話しする所を一度も見ていないですよ。」
「確かにそうですね。」
「そんな瀬尾さんは個人相談の時間を調整してまで谷川さんと話し込んでいた。しかももう一人のお知り合いである可能性の高い明石さんまで巻き込んで。」
「そう言われると確かにそうですね。」
「僕の感じた違和感はそこです。近藤さんの異常な行動でもなければ、藤原さんの谷川さんへのアプローチでもない。ましてや、三上さんの僕に対するそれでもない。
上手くは言えませんが、毛利さんを含めたあの四人の何かにです。
勿論、クラブ「アマルフィ」でのあれが無ければ、毛利さんを含めることは無かったわけですが。」
「すごい洞察力ですね。要するに、毛利を含めた三人が何らかの意図を以て谷川さんに接近していると云うことですね?」
「そこまでは分かりません。ただ本来の趣旨とは違う何かしらの思惑がありそうかと・・・・」
「いやぁ、確かに。ちょっと調べてみる価値はありそうだな。」
田村は心底感心した。
そして、別に内緒にする気もなかったが、三上が毛利を食い物にしようとしていることは話さなかった。
幼馴染と教えた手前、食い物にされようとしている友人を見過ごす酷い奴だと思われたくなかったのかも知れない。
「本当につまらない推理に付き合わせてしまって申し訳ありませんでした。」
「とんでもない。非常に興味深い話でした。」
「なんだか、田村さんと話していると楽しくてつい色々と余計な事まで話してしまいます。」
お世辞とも本音とも取れる和田の言葉に田村は
「そう言って頂けてありがたいですよ。和田さんのわだかまりが解けたかどうかはわかりませんが、こうして色々なお話が出来て良かったです。
明日のセミナー終了までには私の恋愛テクニックの全てをマスターしてくださいね。」
そう言って話を終わらせた。
「そうですね。ありがとうございます。それじゃ部屋に戻ります。」
そうして入口扉のドアノブに手を掛けたところで、
「ああ、それから田村さん。先ほど佐藤さんが廊下で『なにかあったら、田村氏が吹聴したことにします。と、言っていましたよ。私にはわかりませんが、一応お伝えしておきます。 それでは、おやすみなさい。」
そう言って田村の発言を待たずして扉を閉めた。
残された田村はと云えば、佐藤のそれが、どういう意図で発せられた言葉かはわからなかった。
が、しかしそれが藤原明日香に係わる事だと言うことはわかった。
そして、田村は落ち着いていた。
翌々考えれば不思議なことでは無い。
何か言い知れぬ魂胆があるに違いなかった。
“佐藤はあれほどの大企業で執行役員にまで上り詰めた男なのだ。”
“なにかあるならば俺は、藤原明日香を守ってやらなければ。”
何故だか田村は、そんな思いを抱いた。
そして同時に和田健、彼のことも守ってやらなければいけない。
そう考える内に自然と落ち着く快さに、酒で酔ったか、そんな自分に酔い痴れたか、どちらにしても心はとても穏やかであった。
その頃毛利は、博多では老舗として有名な明太子の販売店が入居するビルの二階にあるBARの個室で、明石と共に瀬尾の到着を待っていた。
このBARは葉巻の種類が豊富なことで知られており、1杯、2杯飲んで帰るだけでも10,000円以上はする。
このような店に普段来る事もない明石は、毛利に勧められるままに1本3,000円はする高級葉巻を燻らせていた。
初めて体験した苦にがしいその味わいは二人の沈黙そのものであり、真っすぐに昇り、その後は薄く消え細る煙は、この先の人生を表しているかのようであった。
つい先週、毛利のイタリアンレストランで顔合わせした際には、感じようもなかったその憂慮たる思いは明石の中で増長する一方だ。
そんな二人の重苦しい空気も限界に達する間際になって、瀬尾が合流した。
「おう、瀬尾ちゃん。こっち座りなよ。」
毛利は努めて明るく瀬尾を招き入れた。
そんな毛利を気遣うように瀬尾もまた明るく振舞った。
「さっきはすいません。飲みすぎてしまいました。でももぅ大丈夫。迎酒で絶好調ですよ。」
三人寄ればなんとかではないが再び前向きな意識を持ち直すことが出来そうな感覚に包まれた明石が、その場を更に勢いづけた。
「さあ、仕切り直しですよ。今から始まるアドベンチャーに乾杯―。」
「乾杯」
「乾杯」
その夜三人は、谷川旬の会社に対する思案を打ち合わせするでも無く、急場で出来上がった土台を補強するかのように、お互いの信頼を強めるごとく朝方まで飲み明かした。
同じくその夜、谷川旬と藤原明日香はひとつになった。
深い眠りに落ちるその前に藤原明日香に言われた言葉が、谷川旬の頭を何度も廻った。
「しゅんちゃん、私は何があってもあなたを裏切らない。だから信じて。
どんな時も私を信じて。何があっても私を信じて。
どんなに泣いても、たとえ涙を失くしたとしても、私はあなたを裏切らないから。」
投稿者のプロフィール
最新の投稿
-

-
2022.05.11.
福岡小説 どこまでも惹き込まれるその青色 -

-
2017.03.07.
福岡小説 第十話 あなたの為なら(小説:モテすぎた男) -

-
2017.02.21.
福岡小説 第九話 迷い(小説:モテすぎた男) -

-
2017.02.07.
福岡小説 第八話 深夜の多忙(小説:モテすぎた男)