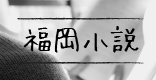どこまでも惹き込まれるその青色
記事内にプロモーションを含む場合があります
年上の“その綺麗な人”は年下の僕をどう見ているのだろう?
子供では無いが大人では無い、そんな蒼い季節が二人を惹かせ合う。
今までの自分では届かないと知った二人は・・・・・。
甘酸っぱい恋より大人で、将来を誓えるには幼すぎる。
いつまでもこの恋愛に揺られていたい。
1
「辻山さん今日から復帰らしいよ。」
「へーそうなんだ。久しぶりだよね?二か月ぶり?ん、三か月くらいなる?」
「誰?辻山さんって?」
「お前、辻山さん知らないの?もぐりだねー。」
「もぐりと云えば、彼女スキューバダイビングする為だけに海外行っていたんでしょう?」
「そうなの?語学留学だと勝手に思い込んでいたよ。」
「いや、だから辻山さんって誰?」
「違うだろう?あの方はバレエを極めにヨーロッパに行ったんだよ。」
「あの方って・・・・。だから辻山さんって・・・・・。」
「ハイハイ。おしまい。そろそろ忙しくなるし、あいつも来る時間だよ。」
この店一番の古株“ふなっちゃん”の号令にて二階厨房で盛り上がっていたアルバイトの
面々はそれぞれの作業に取り掛かる。
はずもなく、“辻山さん”談義を継続した。
「彼女パーフェクトだよな。」
「パーフェクトって完璧って意味だよね?」
「ただ少しだけ、肌色黒くない?」
「ねぇ、完璧ってこと?」
「確かに黒い。だけどそこがそそるんだよなぁ。それにしたって海焼けだろ?」
「海焼けって言葉ある?仮にあってもそれって漁師か何かじゃないの?」
「そお?無かったか?どっちでもいいよ。あの誰に対しても分け隔てない優しい笑顔。彼女
最高だよ。」
「そろそろ僕の質問に答えてもらってもいいかなぁ?」
「なんだよ、さっきからうるさいなぁ。」
「いや、だからその辻山さんっていう人は一体全体どこの誰・・」
せっかく質問に答えて貰えるかも知れない時になって、彼はストンと床に尻もちをついた。
遅れることコンマ何秒かしてガタンッ、ゴゴッとさっきまで彼が腰掛けていた細足のチェ
アーが床に転がった。
「お前らー。口ばかり動かしてないでさっさと体動かせー。シバくぞ。」
更に次の瞬間、ニューヨークヤンキースのお洒落なキャップが宙を舞う。
「痛いっ」
“ふなっちゃん”は大袈裟に座りこんだ。(キャップは彼女愛用の制服のようなものだ。)
自分の忠告を聞かずにあいつの制裁を受けた後輩同僚をニヤケ面してみていた“ふなっち
ゃん”は、あいつの次の標的となった。
「お前が居ながらどういうことやー。ブスは人の倍、いや、三倍働かんかい。」
お気に入りのキャップを叩かれ、酷い暴言を受けた我々の先輩、“ふなっちゃん”は大粒の
涙を溢しながらもサッと切り替え黙々と働きだした。
“ひどい。酷過ぎる。”さすがは、デビル種田店長だ。
彼はシバくぞっと言う前には大抵シバキ終わっている。
そんなことはどうでもいい。
デビル種田店長にシバかれることも時給に含まれている仕事の一部だ。
面接時にその説明が足りなかっただけのことだ。
そんなことよりもなによりも“ふなっちゃん”にブスだなんて・・・。
彼女は本当にブスだった。
ブスなんて言葉は本当はブスでは無い人にしか使ってはいけない言葉だと云うことを知ら
ない大人に、僕は初めて出会った。
アルバイト全員は彼にこの上ない恐怖心を抱いていた。
口は悪いし、直ぐに手をあげる。おそらくは生まれも育ちも悪い。噂ではつい数年前まで
バリバリの暴走族として慣らしていたそうだ。
なによりいけないのはそのお顔。
とにかく恐ろしい顔面をしていた。
ちなみに、隠す必要もなければ、この先その話をすることもないので先にお知らせしてお
くことにする。
この店一番の古株“ふなっちゃん”はデビル種田店長のことが好きだ。
それ以上でも以下でもないのだが、先程の彼女を見たであろう。健気でならない。
せめてその事実だけはみなに知って置いて欲しかった。
しかもデビル(ここからは面倒なのでデビルに割愛)に仕事を教えたのはその“ふなっち
ゃん”である。
数年前まで暴走族であったデビルは僅か二年前にこの店のアルバイト募集に訪れ、奇跡的
に採用され、その奇跡は彼の軌跡へと変わった。
持前の面の厚さを社長に買われたらしく、アルバイト時代を含め僅か半年で店長まで上り
詰めたらしい。
そして、アルバイト初日から右も左もわからないデビルを指導したのが“ふなっちゃん”
なのだ。
健気な彼女の恋がどうなっていくのか。
どうにもならない。
彼女はただの“ふなっちゃん”であり、主役では無いのだから。
福岡市城南区にあるカラオケビル「ニューヨーク80‘S」。
1Fは駐車場で僕らの待機場所の厨房は2F、受付フロントは3Fにあった。
3F~8Fまではすべてカラオケ部屋となっていて外観はまるで普通のマンションだ。
場所柄アルバイトは福岡大学の学生や、近隣大学生、中には九州随一の頭脳を誇る九
州大学の学生さんも居た。
大学生ばかりではお店のシフトは組めない。
午前11:00のオープンから翌朝6:00までの営業時間だ。
中には、つい先日まで“おこちゃま”であったようなフリーターや、テキ屋でずっと働い
ていましたというような柄の悪い人から、美術大学でヌードデッサンのモデルをしていま
すといった変わり種も居た。
長い営業時間だ。
昼の部門と、夜の部門に分かれていて、昼の部には主婦も多く働いていた。
なかには僕を誘惑してくるようなチャレンジャーなご婦人もいた。
数々のアルバイトに落選した僕は三か月ほど前からここで働いている。
薄暗いカラオケルームでデビルの面接を受けた僕はこちらから辞退させて頂こうと思っていたのだが、意外にも気に入られた。
「今日から働いて行け。」
デビルの命令で僕のアルバイト生活が始まった。
採用された僕は昼の部に入れられた。
その時の僕はと云うと、卒業まで残り数か月と言う所で専門学校を辞めたばかりだった。
人員が不足している11:00~19:00までが僕の勤務時間だった。
必然的に共に働くスタッフの大半が主婦。すれ違いで、僕のようなフリーターが穴を埋めると云う感じだった。
主婦のみなさんは20才~45才位まで幅広かった。
こんな人達と上手くやって行けるものかと心配したのだが、それも取越し苦労に終わった。
20才手前の僕は主婦の皆さんのかわいいマスコットになった。
そうこうしていると夜の部のスタッフが足りないということで、時間に余裕のある僕が夜の部に回されることになった。
そんなに親しいアルバイトも殆ど居ない夜の部での初出勤の日、厨房で「辻山さん」談義を耳にしたんだ。
このお店は、お客様が3Fフロントに来店されると、専用マイクで2F厨房にアナウンスが入るシステムだった。
「3Fフロント、一人お願いします。」
それは、お客様が来店されたことを伝えると同時に、2F厨房から3Fフロントへ接客用のスタッフを呼び出し、更にはフロントからお客様を各お部屋までご案内するという一連の流れになっていた。
この日のフロントは“ふなっちゃん”だ。
「3Fフロント、一人お願いします。」
声だけ聞く分にはとても“ふなっちゃん”のお顔を想像できない、、、、、素敵な声だ。
夜出勤初日と云う事で他のスタッフに馴染めていなかった僕は、直ぐに「行きます。」と、元気に3Fフロントに駆け上がる。
フロントからお客様を5F 503号室に御案内して、再度フロントに戻ったその時、フロント奥にある店長室のデビルから呼ばれた。
恐る恐る店長室へ足を踏み入れるとそこには、普段では決して見せることのない笑顔のデビルが椅子に腰かけていた。
そしてその横には、栗色の艶やかな髪の毛の女性が立っていた。
「ちょっと来い。明日から一緒に働いてもらう辻山だ。といってもお前よりも全然先輩だ。きちんと挨拶しておけ。」
「あっ、どうも。よろしくお願いします。」
「こんばんわ。辻山です。お名前は?」
「あっ、僕は・・」
「べら。お前はべらじゃ。」
唐突にデビルが横槍を入れてきた。
当時お店には制服らしい制服は無く、アルバイト全員が上半身だけストライプのヤンキースのユニホームを着用していた。(“ふなっちゃん”の帽子は彼女だけのオリジナルだった。)
パンツは其々が其々に自由なスタイルであった。
普段はジーンズを着用している僕はこの日、洗濯が乾き切らず、とても派手な、ジャージのような、スエットのような、とにかくあり得ない柄のパンツを穿いていた。
「お前、なに魚のべらのような派手なズボン穿いとるんじゃ。シバくぞ。」
そう言われた時にはもう、デビルの前蹴りを腹に受け、「うっっ」と情けない声を出して蹲っていた。
「あはははっ」と豪快に笑いながら「辻山さん」が「大丈夫?」としゃがんだその時、彼女から海のような香りがした。
思わず「はっ」としたが、恥ずかしいのと、その香りで気が動転したのとで、「大丈夫だよ。」
と彼女を突き返してしまったその時、
“スパンッ”
小気味良い音と共に、二度目の恥ずかしさが遣って来た。
「先輩だって言ってんだろうが。敬わんかい。」本日二度目、デビルの愛の鞭だった。
「辻山さん」は「あははははははは」っと先程よりも余計に笑っていた。
それが彼女との初めての出会いだ。
その後、「辻山さん」は厨房に降りて来てみんなに挨拶をした。
「おひさしぶりです。明日からまた宜しくお願いします。」
「辻山さん、久し振り。」
「元気だった?」
厨房は一気に色めき立った。
そんなアルバイト達を尻目に「辻山さん」は軽く会釈をしただけだった。
そして、
「じゃあね。べー。」
そう言って彼女は、僕にだけさよならをして帰って行った。
その時、厨房にいた何人かに
「今、お前にだけにじゃあねって言ったよね?」
「ベー。とかなんとか言ってなかった?」
などと詰め寄られたが、実際僕自身も僕にだけ言ったものか確証が無かったし、「ベー。」と言う単語に心当たりも無かった。
だがアルバイトの皆は、僕への関心もそれっきりで、久しぶりの「辻山さん」で持ち切りとなった。
「見たか?やっぱり綺麗だよな。」
「久し振りだったせいか、随分大人に見えたよ。彼女いくつだっけ?」
「そうだな。綺麗だった。たしか23才じゃないかなぁ。」
「そんなになるか?だって大学生だろ?違ったかなぁ・・・」
「福大だろ?女学院だったかな?いずれにしてもミスなんとかだったのは間違いないよ。」
「いや、23才で間違いないよ。ちょくちょく休学とかしていたからじゃないか?」
「そんなことよりも彼女地元のテレビ局でアナウンサーに内定しているんだろう?」
「えーっ。そうなの?知らない。知らなかった。」
「何でそんなこと知ってるの?お前」
「そもそも地元って何処なの?」
「ん、どこかな?埼玉、いや名古屋かな?」
「辻山さん」談義はいつまでも続いた。
僕はその時、そうなんだぁ。彼女アナウンサーになるのか・・・・。
綺麗な髪だった・・・・。
そして、海のようなそれでいて甘い・・・そんな不思議な香りだったなぁ。
そんな事を思っていた。
「3Fフロント一人お願いします。」
“ふなっちゃん”の声にみながブーイングを出していたその時、僕はまだ、彼女の海の香りのような何かを思い描いていた。
結局、何も思い浮かばない中、少しだけ明日が楽しみだった。
次の日は直ぐに来た。
15分前出勤がルールのお店のいつもの厨房で、まだスタッフも少ない18:40分、彼女と二人きりになった。
「よー“ベー”。おっはよー。」
「おはようございます。」
「くらっ。何か暗いよ。大丈夫“べー”?」
「いや、あのさぁ、“べー”ってなに?」
「あっ、先輩ですけど。」
「“べー”ってなんですか?」
「やだなぁ、そんなに畏まらないでよ。」
「はぁ?だったらもう一度聞くけど“べー”ってなんだよ?」
「いやいや先輩ですけど、デビルに言いつけますけど・・?」
「・・・・・・もういい。あんたと話しているとイライラする。」
僕は彼女と距離を取ろうとした。
「ねー。私、“あんた”って名前じゃないよ。」
「知ってるよ。そんなこと」
「じゃ、ちゃんと名前で呼んでよ。“べー”。」
「俺の名前も“べー”じゃ無いよ。」
といったところで今更ながら気が付いた。
“べら”ですね。はいはいデビルが命名した“べら”。僕はそう、昨日から“べら”になったのです。
「知ってるよ。原田君でしょ。でも私は“べー”って気に入っているんだ。」
「そうなの。それじゃご自由に。」
「本当?じゃあ“べー”にする。宜しくね、“べー”。」
「よろしくお願いします。」
「ちょっと、」
「まだ何かあるんでしょうか?」
半ば呆れ半分に振り向いた僕に“辻山さん”は言ったんだ。
「名前呼んでよ。ちゃんと」
「わかったよ“ぷり”。」
「えっ、何?」
「いや、だから”ぷり“」
僕は恥ずかしくなって小声でもう一度言った。
「“プリ”?私の事?“プリ”?」
「そう“ぷり”」
「えっ、えっ、私がプリティーだから?ねぇ、ねぇ、」
“辻山さん”は、それはもうニコニコして聞いてきた。
「いや、違うよ。自分でそんなこと言って恥ずかしくないの?」
「違うの?恥ずかしくもなんとも無い。だって私、かわいいもん。」
「本気で言ってる?」
「うん。誰からも言われるよ?可愛いって。ほぼ毎月告白されてる。」
彼女は至って真顔だった。
「・・・・・・・そうなんだ。なんて言えば正解?すごいねーって?」
「なんにも言って欲しくない。事実を言ってるだけだから。“べー”も素敵だよ。
言われたこと無い?」
「なに突然?無いよ。素敵だなんて。」
「無いの?そうなんだぁ、じゃぁ“べー”はモテないんだね。」
「あのさあ、悪いけどあんたよりもモテるかもよ俺。ただし、あんたみたいに自慢はしないけどね。」
「なんだ、やっぱりモテるんじゃん。でも、素敵って言われたことは無いの?」
「無いよ。素敵だなんて。」
「そっかそっか。“べー”はやっぱり、まだまだ子供だね。」
そう言って「辻山さん」はニコニコしていた。
「あんたに言われたくないよ。」
「あんたって言わないでくれる?それなら“プリ”でいいから」
彼女は真顔で言った。怒っているようでもあった。
「情緒大丈夫?」
「いいから、あんたはやめて。」
「わかったよ、“ぷり”」
そう言った瞬間、“ぷり”は僕に飛びついてきた。
そうして自らの腕を僕の首に回して締め付けてきたのだ。
そう、俗に言う“ヘッドロック”だ。
本当に突然の出来事だった。
「かわいいのぉ。かわいいのぉ。“べー”」
「意味がわからん。どけよ。」
そう言って彼女を突き放すことで精一杯だった。
そんな事をしていると、すぐ横には19:00出勤の他のアルバイトが立ち竦んで僕らの様子に唖然としていた。
“ぷり”は真っ赤になって何事もなかったように僕から距離を取った。
僕は、切り替えが下手なこと右に出る者なしの人間だ。
非常に恥ずかしかった。
ただそれだけだった、かと云えば本当は違った。
“ぷり”の柔らかな胸の感触と、あの海の香りのような、甘い匂いのようなそんな事が頭から離れなかった。
突然の“ぷり”の襲撃に驚いた僕であったが、他のアルバイト君達はもっと驚いたに違いない。
三日と経たず、すべてのアルバイトに情報が行き渡った。
“原田と「辻山さん」は怪しい”。
みんなに知れ渡るまでの三日間僕は意図的に彼女を避けた。
恐らく彼女もそんな感じだった。
では周りのみんなはどうであったかと言えば・・・・。
「辻山さん」に問い質すことは勿論出来ず、みなが僕に聞いてきた。
“二人は付き合っているのかと”
僕はハッキリと否定した。
実際に付き合うどころかまだ数回しか会ったことも無いのだから。
いちいち詮索されることは面倒ではあったが、それがきっかけとなって、夜のアルバイトのみなと打ち解けることが出来た。
しかも、みんなは「辻山さん」のことは見ているだけで良いらしかった。
それほどまでに高根の花だと決めつけている様子で、僕のことをライバル視するような人は現れなかった。
ただ一人を除いては・・・・。
そう、デビルだ。
何日目かの深夜、店長室のデビルに呼び出された。
「お前、「辻山」と付き合ってるのか?」
「いえ。」
「本当のことを言えよ。」
「本当に何もありません。」
「だったらなんで店中そんな話になってるんだ?」
「ただ仲良く話していた所を見られてしまって・・・。それ以外に理由は分かりません。」
デビルは足の先から頭のてっぺんまで刺すような視線を僕に向けた。
「・・・・お前、その気あるのか?」
「いえ、ありません。」
「本当だろうな?」
「はい。今のところは・・・。店長は「辻山さん」のこと好きなんですか?」
デビルの重圧に耐えきれなくなった僕は、何故かそんな恐ろしいことを聞いてしまった。
瞬時に何発か覚悟したのだが、デビルからはパンチどころか意外な言葉が返ってきた。
「どうだろうな・・・。一人の男としては、あんないい女を放って置く理由は無い。但しこの店の責任者として従業員に振られる訳にはいかない・・・。」
なんだかびっくりした。
デビルと普通に女性の話をしていることに。
そして、デビルが従業員の目を気にしていることに。
いや、社会人としての規律を重んじていると言うべきか。
そしてこうも思った。
のんびりしていたらデビルに彼女を取られるかも知れないと。
今となってと云うか、あの時より幾ばくか経過すれば分かる事だが、あの時は分らなかった。
小さな世界で、店長は絶対的だった。
何人ものアルバイトと付き合っては別れるというのを繰り返しているという噂を聞いていた。
あのデビルとの夜から数ヶ月後には、そんな小さな世界で彼女は生きていないということを知る事になる。
そしてそれは、自分が恐れる対象はこんな小さな世界の覇者では無いと云う現実に20才そこそこの僕は打ちのめされる。
デビルはこの夜僕に言った。
「勝負だな。お前に負ける気もしなければ、あいつを譲る気も無い。」
デビルは情熱的な男だ。
感性だけで生きているのかも知れない。
そんな僕の不安は一瞬のうちに消し去られことになる。
その日より5日後、お昼のアルバイトとして入って来た25歳の綺麗な元ヤンと、デビルは付き合った。
そしてその直後から同棲を始めたと云う話を僕が聞くのは、それから10日程経った日のことだ。
あの夜の出来事をデビル目線で思い起こすと死ぬほど恥ずかしい。
僕ならまともに目も合わせられない。
なのにデビルと来たら、何事もなかったかのように「原田、同棲はいいぞ。」と言ってきた。
僕は誰と何の勝負をしようとしていたのだろう?
こうして僕は大人になって行くのだろうと思った。
過去の発言や恥ずかしい経験は一晩寝たら脱ぎ捨てなくては、大人には成れないのだと。
全くの余談だが、この二年後の解けるように熱い夏の日、大人に近づいた僕はデビルに電話をする。そして、
「あんたへの信頼は無くなった。こちらも納まりが付かない、今から○○まで出て来い。」
と呼び出すこととなる。
デビルは来なかった。
たくさんの事を教えてくれたデビルと決裂した夏の日だった。
“ふなっちゃん”同様にデビルが主役では無いので、この話もここで終わりにしよう。
さて、気まずい数日間が過ぎて、アルバイトの興味は僕達から消えかけていた。
その頃になると、“ぷり”とは人目を気にすること無く話をするようになっていた。
「ねー。なんで“プリ”なの?やっぱりプリティーの“プリ”でしょう?」
「いや、本当にたいしたことじゃあ無い。お前、ぷりぷりしているから。」
「ぷりぷりって?」
「体つきだよ。二の腕、けつ、全体的に。」
「はぁ?ガキが偉そうに言うなよ。見た事も無いくせに。」
「見せれるものなら見せてみろ。ちなみに俺はこんな感じだから。」
そう云って僕はTシャツを捲ってお腹をさらけ出した。
貧乏生活の賜物か、僕の腹筋はなんとなくだが、綺麗に割れていた。
それを見て彼女は言った。
「・・・・・そのうち見せてやる・・・。」
この頃にはもう“ぷり”に恋をしていた。
今になって想えば、蒼い恋だ。
お互いのことはほとんど話していなかった。
彼女が地元テレビ局に就職が決まっていることすら、彼女の口から聞いていなかったのだから。
少し前に皆が噂していた通り、彼女の日々は忙しかった。
幼少の頃より続けていたバレエも、一週間と間を空けず教室に通っていた。
まあ、週に一度程度のレッスンだったことから、彼女がそれを本業として選択していないことはおこちゃまの僕にもわかっていた。
また、もはや趣味の域を超えていたスキューバダイビングも変わらず愛していた。
そうそう南の海に行ける筈も無かったが、毎週のように馴染みのスキューバダイビング教室を常時行っているマリンスポーツのお店に顔を出していた。
他には英会話教室。
よくもまあ、お金があるものだと不思議に感じたものだが、その疑問は直ぐに解決した。
彼女は西中洲にあるBARでも週に2回ほどアルバイトしていた。
そんな忙しい彼女を一番追い詰めていたもの、それは卒業と云う大イベントだった。
厳密には卒業できるか出来ないか、極めてぎりぎりのラインにいたようだったが、就職も決まっていたことから、何かしらの膨大な提出物との交換条件が課せられていたように記憶している。
彼女のカラオケ屋でのアルバイトは、決まって19:00~翌2:00までのシフトだった。
僕はと云うと、19:00~翌6:00まで。要するにラストまで勤務して居た。
そんな時彼女は、2:00から6:00までの間、待合室でその膨大な提出物と格闘していた。
そして僕が6:00に仕事を終えるとそのまま近くの「黒田屋」に二人で通った。
早めの朝食と云うべきか遅めの夜食と云うべきか、遅めの夜食と云ったほうが正解だろう。
なぜなら彼女は決まって生ビールを注文していたから。
そんな僕らはまだ“恋人”には成っていなかった。
「“ぷり”きつくない?良いんだよ、態々待ってくれなくても。」
「別にあなたを待っているわけじゃぁ無いよ。」
「そんなんだ。だったら家で遣った方が集中できるでしょう?」
「色々とね。大人の事情もあるのよ。」
「ふーん。そんなもんか。」
「そう。そんなもんよ。“べー”あなたどんなファッションが好きなの?」
「ファッション?自分の?相手の?」
「両方。」
「ファッション・・・・よく分らん。」
「なんでよ、私はね、今着ているような裾の広くなったパンツが好きなの。脚が綺麗に見えるでしょう?あとボロボロに色落ちしたジーンズも好き。あんまりスカートは穿かないけどあなたが好きって言うなら穿いて挙げてもいいよ。短いセクスィ-なやつ。」
「・・・・なにがセクスィ-だよ。年を考えろよ。俺はどんな服装でも構わないよ。」
「なんだか面白くない。折角あなたが着てほしい服を着てあげようと言っているのに。この私が。」
「ばばあ・・・・・。いい加減にしろよ。今はきちんと課題をこなして無事に卒業することだけを考えな。」
「つまらんおとこだな、あなたは・・・・。」
「いちいち自分や相手の服装を気にするような男が立派と言うなら、俺はつまらんおとこでいいよ。」
「屁理屈に聞こえないことも無いけど、そんなあなたは嫌いじゃないな・・・。」
そう言って彼女は二杯目の生ビールを飲み干してその日はお開きとなった。
その日“ぷり”とお別れをした後、途端に彼女の言う“大人の事情”が気になった。
気にしても仕方のないことだと切り替えられたのは、彼女の発する“あなた”という言葉を頭の中で反復していたからだろうと思う。
“ぷり”が僕に対してよく使う“あなた”という響きが堪らなく心地良かった。
初めこそムズ痒くなる感覚を覚えたが、彼女からすればそれは自然な言葉であった。
そんな事を思いながら眠りにつく。
真冬の朝とは云え、いい加減外も明るくなっていた。
今日目を覚ませばまた彼女に会える。
それだけで幸せだったんだ。
「おい、起きなくていいのか?遅刻するぞ。」
同居人である“大水”の声に飛び起きた。
「やばい。助かった。サンキューな。」
なんとか遅刻すること無くギリギリのところで間に合った。
そうだ、ここできちんと訂正しておこう。
同居人と云うのは間違いで、正確には福岡大学の学生である“大水”が契約している部屋に行き場を無くした僕が荷物も無しに転がり込んだだけだ。
時刻は18:42分。
早々に着替えてタイムカードを押さなければ今日も僕はデビルの餌食となってしまう。
男女特別に仕切りのない倉庫兼更衣室に駆け込んだちょうどその時、彼女は長い髪を一つに結うところだった。
薄暗い、湿った倉庫に、ふわぁっと甘いそしてやわらかな海の香りがしたんだ。
「おはよう“べー”」
「おはよう“ぷり”」
「そんなに見惚れないで。お姉さん照れちゃう。うふっ」
「見惚れてねえよ、出勤早々馬鹿言ってんなよ。」
彼女は意地悪な視線を僕に向けていた。
「本当は見惚れてたでしょう?」
「・・・・・・・・うん。見惚れてた。」
「えっ、本当に?やけに素直だね?」
「そんな日もあるよ。“ぷり”お前のことが好きだよ。抱きしめてもいい?」
「えっ、えっ、どうした?えっ、ありがとう。・・・・・えっ本当に?えっどうしましょう?」
彼女は動揺していた。
なんだかとても可愛らしかったんだ。
今日は僕の勝ちだと思った。
「どうもしなくていいよ。冗談だから。」
「あっそういうことですか?なるほどねー。こりゃぁ、お姉さん一本取られたわ。それはそうとあなた今朝と全く一緒の服装だけど・・・・・・ちゃんと家に帰った?」
「ああ、寝坊しちゃって。そのまま飛び起きてきたよ。」
「いや、そのまま飛び起きてくるのはいいのだけどね・・・・・ということはそのままの服で寝ていたと云う事になるのかしら?僕ちゃんは?」
「いやまぁ、普通にそうだけど・・・・なんで?」
「パジャマ着ないの?パジャマじゃないまでもジャージとか・・・・・・。そのこと自体が異常だと云う事に気が付けないあなたはある意味すごいわ・・・・。」
「へん?お前なんか疑ってない?俺別に女の家なんかに泊まってないよ。」
「あっ、ごめん。全く気にしてないから。勘違いしないでね。」
なんだか急に恥ずかしくなった。
「そっか。そうだよね。」
そう言ってストライプのシャツに両方の腕を通し終えたそのとき、彼女はやさしく僕を後ろから抱きしめたんだ。
そしてなんとも悲しげにこう言ったんだ。
「嘘。不安になった。なんだか寂しくなったよ“べー”。」
「えっ、なんだよ、何も無いよ。真っすぐ家に帰ったよ。」
動揺を隠しきれないまま、馬鹿正直に答えた僕を尻目に彼女は、・・・・ケラケラと笑いながら厨房の方に向かっていた。
そして去り際にこうも言っていたんだ。
「冗談よ。年上をからかうからこういう事になるのよ。でも“べー”あなた無臭ね。お風呂も入ってないだろうに。」
「・・・・・・・・・。」
そっかぁ、僕は無臭なんだぁと人生で初めて知った瞬間だった。
僕らのアルバイト先はそれなりに忙しいお店だった。
ひと月の売り上げは平均して2,000万円ほどもあった。
従事するアルバイトは総勢で25名ほども居た。
僕らはデビルの強烈なリーダーシップのもと、ひとつに纏まっていた。
たくさんの売上が上がると云う事は、たくさんのお客様が来る訳で、たくさんのお客様が来ると云う事は、たくさんのトラブルも起きるという事になる。
このお店はとにかくガラの悪いお客様のトラブルが絶えなかった。
時にはあのデビルでさえ、尻込みするような強烈なお客様のからのクレームや、お客様同士の喧嘩など、ありとあらゆる事件には事欠かない場所であった。
「3Fフロント一人お願いします。」はお客様が一組来店。
「3Fフロント二人お願いします。」はお客様が二組以上来店。
そして「3Fフロント三番お願いします。」はトラブル発生。
とくにフロント周りで揉め事が起きているときを指しており、至急フロントまで複数の男性アルバイトは上がってきなさいと云うメッセージだった。
ある時僕は1F駐車場でお客様の車の誘導をしていた。
一息ついてビル上部を望める開けたスペースに出た時に“ガシャーン”とけたたましい音と共に大きめの砂利が飛んで来るような感覚を覚えた。
何が起きたか分からず、茫然と辺りを見渡して理解した。
砂利のようなその物質はビールジョッキの見るも無残な姿だった。
慌てて上を見上げると、そこには常軌を逸したお客様がニタニタと笑っていた。
その細かな表情までは読み取れなかったが、全身から放つ異様な雰囲気は常人のそれとは違っていた。
ここで問題なのは、僕を驚かせようとしただけなのか、それとも狙いをつけたものの外してしまったのか・・・・。
どちらにしても普通ではない。
また別の日にはある新人アルバイト君にこう言われた。
「あのー、原田さん・・・・背中に足跡付いてますけど・・・・・。」
僕はストライプの制服を脱いで背中を確認した。
「あーこれね。さっき705号室のお客様からとび蹴りされたんだよ。」
「えっ、飛び蹴り?えっ、大丈夫なんですか?」
「平気、平気。たまにある事だから。」
その新人君は感情を無くした顔で何度かゆっくりと頷いていた。
まぁ、あまり興味は無いかも知れないが、事の経緯を軽く解説しておこう。
お客様からのご注文の品を、僕たちアルバイトはマンションで言うところの非常階段を使って持って行く。(エレベーターは使用禁止だ。しかも厨房は2Fにしか無い。)
ご存知のように厨房は2Fにある為、7F、8Fとなるとひと苦労だった。
しかも、それが頻繁に続くと流石に足にきてしまう。
その時僕は何度目かの7Fのオーダーを連続した後、7Fと6F間の踊り場付近で階段に腰掛け、休憩をしていた。
そこに完全に飛んでしまっているお客様が、文字通り僕の背中目掛けていきなりの飛び蹴りを見舞ってきた。
「なにさぼっとんじゃー。ビールまだかー。はよ持って来んかー。」
とまぁ、こんな具合である。
余談になるがその後、そのまま踊り場から地上に落とされそうになった。
たまたま現れたそのお客様の連れの方が止めてくれたのだ。
“ありがとうございます。お連れ様。お客様は神様です・・・・・・・・・・・。”
なんとも不思議だが当時はそんなことくらい当たり前で、この店で働くようになってからというもの、多少のトラブルには全く動じなくなっていた。
今なら即警察の出動となるだろうに・・・・・・。
ただあの日はそんな事件などかわいいと思えるようなトラブルが起きた一日だった。
「3F フロントキャーッ、ちょっとなんなんですか?ガーッ、ゴン、やめてく・・。」
2F厨房にいた僕らにも緊張が走った。
と云うのは大袈裟で、1フロア違えばその緊張感は天と地の差がある。
しかも2F厨房にアルバイトは10人近くが待機しており、“赤信号みんなで渡れば怖くない”という空気が漂っていた。
色々なタイプのアルバイトが居るもので、揉め事など一切御免だという九大生から、非常に好戦的なレスリング部の副主将や、武勇伝には事欠かないテキ屋あがりのお兄さんまで様々だった。
10人の中でも好戦的な3人が自発的に、3Fフロントへ向かった。
5分経ち、10分経ち、15分経過しても誰一人2F厨房へ戻ってくる者は居なかった。
厨房でのんびり無駄話をしていた僕らは少し不安になって来た。
いや、厳密にはかなりマズイ状況に違いないことはわかっていた。
それと云うのも、3Fフロントからは凄まじい怒鳴り声と、備品が破壊されていく音が聞こえていた。
途中、厨房から見えるエレベーターは三階に停まって、直ぐに一階に降りていた。
どう云うことかと云えば、お客様が来店され、3Fフロントに向かう、そして不可抗力なのか、自らの意思なのかは分かりかねるが、たった今乗って来たエレベーターに乗って帰っていると云う事を僕らに伝えていた。
そんな時、ヤキモキしていた僕らの所に最新の情報が届いた。
そしてそれは、何も知らずにフロントに向い、とんでもない災難に巻き込まれて顔面蒼白になった、今日は休みの筈の「辻山さん」から齎された。
「“べー”大変なことになってるよ・・・・・。」
「知ってる・・・・。」
「知ってたの?まぁ、知ってるかぁ、あの騒ぎじゃぁねぇ・・・・・・・。てか、だったらこんな所でなにしてんの?」
「いや、何が起きてるの?」
「はい?知ってるんじゃないの?」
「何かトラブルがあったことだけは把握してる。」
「いやいや、そんなレベルじゃないよ。だってデビル正座してるよ・・・・・・。あと、誰だっけ?あの柔道部かレスリング部かの大きな子。」
「山根君?」
「ああ、そうそう彼なんて・・・・・・・・顔面血の海だよ・・・・・。」
「えっ・・・・・。そんなに酷いの・・・・。」
「いや、酷いなんてもんじゃないよ。」
「相手は何人いるの?」
「4人。」
「で“ぷり”はどうしてそんなに詳しいの?」
「あっ、これ。」
彼女はそう云って「てつおじさんのチーズケーキ」と書かれた紙袋を悠然と掲げた。
「・・・・・それがなんだよ・・・・。」
「“ふなっちゃん”に差し入れしようかと思ってフロントに行ったのね。そうしたらバッタリ遭遇・・・・。で、「姉ちゃんは何者かね?従業員ならそこに立っとき、唯の客ならさっさと帰らんかー。」って思いっきり怒鳴られた・・・・・。」
「・・・・・・・災難だったなぁ。」
「あっ、それとボスみたいな奴にお尻鷲掴みにされたんだよ。」
「・・・・・・・・・それはまぁ、良いとして・・・。」
「いや“べー”良くないんですけど、私お尻掴まれたんですけど・・・・。」
「うん。まぁ、それは良いとして。どうしたものか・・・。」
「いや、全然よくないんだけど。“触られた”じゃなくて掴まれたんだけど・・・」
「“ぷり”しつこい。今そんな悠長な事言っている場合じゃないから。」
ここで彼女は持ち前の意地悪さを発揮させた。
「“べー”あなたそう云えば、空手の有段者だよね・・・・・・。行ってきなよ。」
彼女は本気とも取れる眼差しを僕に向けた。
「まぁ、全員締め上げてもいいけどな。・・・・けど俺の拳は凶器と一緒だからなぁ、警察に逮捕されたしまう恐れがあるなぁ。」
「・・・・・・・・・・ほう、ほう、それで・・・。」
「本気じゃないよね・・・・。俺まで血の海にされちゃうよ。そうだこんな時は坂田部長に連絡だよ。」
「やるだけ無駄だよ。」
僕の案は厨房にいる他のみんなもわかっていたようだった。
坂田部長は来ないと云う事を。
それでも打てる手はそれしか無い。
厨房の壁に備え付けの電話から、坂田部長宛てに電話をしてみた。
030-○○○○-○○○ 今より一ケタ少ない当時発売されたばかりのセルラーフォンだ。
「はい、もしもし。」
坂田部長は直ぐに電話に出てくれた。
「お疲れ様です。城南店アルバイトの原田です。」
「おー原田君、どうしたの?」
「急にすいません部長。今ですねお客様のクレームで大変なことになっていまして。」
「種田君は?休みなの?」
「いやそれがですね、正座させられているようでして。アルバイトの数名も暴行を受けているようです。」
「あらら。なんね。ヤー公か?」
「分かりませんが、恐らくはそうだと思います。」
「わかった。あいつら調子に乗せたらダメよ。つけ上がるだけだから。」
「そうですね。ありがとうございます。直ぐ着て頂けますか?」
「・・・・いや今は動けない。こちらから警察手配するから。」
「・・・・・・・・・・あっ、そうですか・・・お願いします。」
「任せときなさい。原田君、あいつら調子に乗せたらダメよ。」
「・・・・・。」ガシャン。
僕は無言で受話器を置いた。
坂田部長は今日も来ない。
そしてみんなはそんなこと百も承知であった。
少しすれば警察が来る。
そんな安堵感は一瞬にして消えた・・・・。
「おい、酒出せ。んー、なんね、やっぱりお姉ちゃんは従業員か?」
「・・・・・・・。」
どうやら見つかってしまったようだ。
「こんなカラオケ屋で働くのは勿体ないばい。ねーちゃんうちの店で働かんね?稼げるよ。」
四人組?の内の二人が2F厨房まで足を踏み入れてきた。
厨房は混乱に混乱を来した。
数名のアルバイトは裏の倉庫兼更衣室に避難した。
二人組の男達は、厨房に置いてあるジャックダニエルや生ビールを我物顔で飲み始めた。
「ねーちゃん、こっち来てお酌でもせんね。」
僕の大切な“ぷり”は完全に標的にされた。
“ぷり”が無言で僕に助けを求めているのがひしひしと伝わって来た。
でも、怖くて動くことが出来なかった。
その時だった。
以前感情を無くした顔で頷いていた新人君が男二人に近づいた。
「あのー、そろそろ帰られた方が良いんじゃないでしょうか?」
その新人君はニコニコしながら男二人に言い放った。
当然彼らも黙っては居ない。
「なんじゃークソガキ。ぶっ殺すぞー。おーっ。」
それはもうすごい剣幕だった。
「僕なんて殺しても何の得にもなりませんよ。警察もそろそろ来ると思いますし、さぁ。」
二人の男達は厨房の椅子を蹴りあげ、テーブルに置いていたお皿と云うお皿を床にブチ撒け、「なめとんのかオノレはー。××××××」もう後半は何を言っているのかさえ解らないほど興奮していた。
そんな彼等とは対照的に落ち着き払った新人君は少し間をおいて口を開いた。
「んー。赤城です。博多区の赤城の息子です。上に居られるお連れ様はどちら様ですか?」
二人の男達は瞬時に引き攣った表情になったのは僕にも分った。
「なんね、赤城さんのご子息ねぇ。早く言って貰わんとそう云う事は。」
隣からもう一人の男も口を開いた。
「俺らもう帰りますけん。赤城さんには今日のこと言わんで下さい。」
「そうですか。だったらさっさとお帰り下さい。」
そのまま3Fフロントに上がった男達は直ぐに残りの二人と一緒になって厨房に戻ってきた。
そして、その中で一番年長そうな人が新人君の前に来て頭を下げた。
「なにも知らんやったもんで。すんませんでした。」
こうして嵐のような時間は通り過ぎたのだった。
残されたのは散らかった厨房と、血の気が完全に引いてしまったアルバイト達と、顔面血の海の山根君。
そして大好きな“ぷり”の信頼を大きく損ねたであろう僕。
“ぷり”はそんな僕を軽蔑しただろうか・・・・・・。
そんな感傷に浸る暇もなく、デビルが厨房に降りてきた。
そして、生ビールを“グイっ”と一気に飲み干した。
「最高に面倒な奴らだった。山根大丈夫か?他の奴らもよくがんばったなぁ。」
そう云ってスタッフ達に労いの言葉を掛けた。そしてこう続けた。
「で、なんであいつら急に帰って行ったの?その後厨房にも来なかったか?」
僕と「辻山さん」それと先程の状況を知るアルバイトとで、デビルに説明をした。
すると、“スパーン”と心地よい音が鳴り、先程の新人君が頭を押さえた。
「こら、そんなとっておきがあるなら直ぐに出さんかい。このどアホ。」
そう云ってもう一撃、新人君に喰らわせた。
新人君は「そうですよねぇ」と言いながらニコニコしていた。
ヤクザも頭を下げて引き下がった新人君を“どアホ”呼ばわりで二発喰らわせたデビル。
先程まで正座させられていたデビル。
彼の切り替えの早さが欲しい・・・。
その日僕はデビルと他のスタッフに無理を言って早上がりをさせてもらった。
理由は唯ひとつ。
“ぷり”のご機嫌取りに他ならない。
その日は午後23:00には着替えを済ませ、不信感でいっぱいの“ぷり”と一緒にいつもの
「黒田屋」に向かった。
お店から「黒田屋」までは歩いて10分程度の道のりであったが、その間彼女はずっと僕に文句を言い続けた。
「きっとあなたはこの先も私のことを守ってはくれないのよね。」
「あーあ、なんだか悲しいやら情けないやら、あーあ、どうしてくれるの“べー”」
「いや、本当にごめんなさい。」
「別に謝る必要なんてないよ。ただあなたより4つも年上のおばさんが、乱暴な男達にお尻を掴まれ、怒鳴られ、挙句お酌させられそうになり、終いにはさらわれそうになっただけだから・・・気にしないで。」
「・・・・・さらわれそうになんてなってないだろ?」
「いいの、いいの、気にしないで。自分の身はなんとか自分で守ったから。」
「いや、だから謝ってるだろう、ごめんてば。しかも自分で守った訳ではないでしょう?・・。新人君が助けてくれたんじゃなかった?“ぷり”も顔面蒼白だったような・・・・。」
「なんだか全く反省の色が感じられないわね。怖かったの?僕ちゃん?」
「・・・・・・怖かったよ。マジで。・・・・・・」
「確かに・・・・怖かった。・・・・・許してあげるよ。でも~マジで怖かったね~。」
そう云って彼女はニコニコした笑顔を見せてくれた。
これまた余談だが、「黒田屋」に入ると、先程の四人組が居た。
そして“ぷり”は、「ねーちゃん悪かったなぁ。けど仕事変える気になったらいつでも連絡してくれや。」と無理やり鞄に名刺をねじ込まれていた。
ちなみに僕も「お前の彼女か?羨ましいのぉお前×××××××。ぎゃっはははははは。」
とても、とても卑猥な言葉を頂戴した。
本当に僕は引きが強い。
そのまま店を後にする訳にはいかず、僕等は静かに食事をして帰ることにした。
その日の「黒田屋」は全く楽しくなかった。
新年を迎えようとしていたそんな頃、僕たちは未だ恋人同士では無かった。
そして、恋人同士でもない二人には破局と同じく、隙間風が吹いていた。
理由はいくつもあった。
この時、僕らのカラオケ屋に新しいアルバイトが遣って来た。
名前を“えっちゃん”と言った。
年齢18才と偽った17歳の女の子であった。
福岡市南区のヤンキー学校を中退したばかりの彼女はどこから見ても20才以上に見えた。
みんなの憧れの“辻山さん”とは違う、手の届くかもしれない美少女だった。
“えっちゃん”はその気さくさもあってか男性スタッフ達の人気者となった。
そしてすぐに彼女を巡っての幾つかの恋愛バトルが巻き起こった。
先陣を切って見事に玉砕したのは例の新人君であった。
その後も、何人かの挑戦者が現れたのだが、全員KOと云う結果に終わった。
その中には未来を有望視された九州大学院生も含まれて居た。
ヤンキー学校中退の“えっちゃん”に振られた将来有望視クンはそのままお店を辞めてしまった。
そんな“えっちゃん”は「辻山さん」をお姉ちゃん、お姉ちゃんと慕っていた。
以前は僕と“ぷり”の「黒田屋」は今では、「辻山さん」と“えっちゃん”の「黒田屋」と変貌していた。
そんな折、待合室で格闘中の“ぷり”から不意に言われた。
「ねぇ、“べー”、“えっちゃん”あなたのことが好きだわ。」
僕はうすうす気が付いていた。
「そうなんだ。」
「あら、あら、あら、随分余裕だねぇ~。うれしいでしょう?」
「どうかなぁ。別に、あんまりなんとも思わない。」
「意外だわ、あなた“えっちゃん”みたいなキツメの顔した女の子好きじゃない。」
「まあねぇ。綺麗な顔してるよね。」
「うん。あの子良い子よ~。ほんとかわいい。しかもしっかりしてる。
あの若さにして既に人生反省してる。大検取るなり、編入するなりして大学を目指すって言ってた。しかもそのための費用は全額自分で用意するんだって。私より全然大人だよ。」
「うん。立派だね。でも、言うのは簡単だけどそれを実行できるかどうかだよ。」
「そうね。なんかさぁ、昔の“よくないお友達”から離れるのが凄く大変って言ってた。」
「まぁ、そうだろうね。環境が変われば人も変わるよね。彼氏だったりさぁ。」
「あら、あら、わかったようなこと言うわね。おこちゃまのくせに。」
「俺こないだ20才になったよ。」
「知ってる。おめでとう。“べー”。」
「俺のことおこちゃまなんて言うのはお前だけだよ。頼り甲斐あるとか、落ち着いているとか、よく言われるもん俺。」
「ぷっっはははっ、それ面白いギャグだね。」
“ぷり”は豪快に笑い飛ばしたんだ。
「はぁ、もういいよ。そうやっていつまでも子供扱いしてろよ。」
僕は正直に言うとこの頃本当にウンザリしていた。
デビルほど変わり身は早くないが、“えっちゃん”はじめ、他にもそれなりに可愛いと思われる女の子から度々恋の告白を頂戴していた。
でも、どうしても「辻山さん」と比べてしまっていたんだ。
彼女と出会わなければ、彼女が4才も年上でなければ、彼女が何処にでもいる普通の女性ならば、僕は今のように苦しんでなど居ない筈だ。
その時、「辻山さん」は僕の方をキョトンとした無表情で眺めながら手招きをしていた。
「なに?」
「・・・・・・・。」彼女は手招きを続けている。
「なんだよ。偉そうに・・・。」僕は嫌々足を進めた。
そして、待合室のソファーに腰掛ける彼女の正面に立った。
すると彼女は僕の左手を取って自らに引き寄せたんだ。
そうして両方の手を僕の首に回して言ったんだ。
「おめでとう。“べー”20才は特別だよ。素敵だよ“べー”は。」
僕の中の時間は静止していた。
その間ずっと、ずっと彼女の甘い海のような香りが僕を包み込んでいたんだ。
薄暗い待合室はUFOキャッチャーなどのゲーム機の照明だけでその視界を保っていた。
普段は無機質に光るゲーム機達の明りは、未熟な二人を照らしていた。
すっと、ずっとこうして居たかったんだ。
あと一時間、朝まで、この先の人生ずっと・・・・・。
「なんだよ急に。放せよ。」
「照れるなよ。」
「照れてないよ。」
「いや、いや、照れてるでしょう?」
「“ぷり”俺マジで照れてないから。もう戻るわ。」
そう云って僕は早足に待合室を後にした。
この時僕は、まさにどうしようもない想いに苛々していたんだ。
僕は彼女が好きだ。自問するまでも無い。
彼女も僕が好きだ。とまでは言い切る自信が無かった。
彼女はみんなに優しかった。
彼女はみんなに変わらぬ笑顔を振りまいた。
さすがにハグをされたと云う他の誰かの話を聞いたことは無い。
だが、それは彼女と他のスタッフとの微妙な距離感と云うか、空気感と云うべきか、僕だけが異常なまでに彼女との距離が近いだけなのかも知れない。
4歳年下という事実が僕を追い詰める。
彼女は僕をかわいい弟のように見て居るだけではないだろうか?
そうだとすれば僕はなんて間抜けな自称“モテ男”だろう。
僕は疲れていたんだ。
そんなある日、いくつかあるうちの中でも大きめの亀裂となる事件が起きた。
「辻山さん」と「原田」は仲が良いだけで付き合うことは無い。
そう判断したアルバイトのみんなは“えっちゃん”の切ない想いを実らせようと実にくだらない作戦を実行した。
営業終了後、車三台ほどに相乗りして、現在でいう糸島の二見ケ浦に行くことになった。
僕はずっとイライラしていたんだ。
なんとなくそういうことが起きるのではないのかと云う気配を感じていた。
案の定だった。
極寒の浜辺でBBQを楽しんだ後、一人、また一人と僕を取り囲みだした。
あっという間に僕はみんなの円の中心にポツンと佇み、ほろ酔いのアルバイト達は“えっちゃん”コールを始めた。
渋る様子を見せながらも、それでも僕の前に立った“えっちゃん”は実に堂々とはっきりと言った。
「私、原田さんが大好きです。付き合って下さい。」
僕はイライラしていた。
とてもとても苛ついていたんだ。
そう、その輪の中に「辻山さん」も居たから。
おこちゃまの僕は、大勢のアルバイト君達にその感情をぶつけることは出来ずに、一人の女の子を傷つけたんだ。
「俺その気ないわ。お前みたいなクソガキなんてありえない。あと俺、地元に彼女いるから。」
波の音だけが聞こえた。
総勢10人以上はいる浜辺で・・・・。
“えっちゃん”は大人だった。立派だった。
「まじですか?・・・・。また来月告白します。今日は惨敗―。」
そう大声で叫んでくれた。
まわりのアルバイト君達も無理やり笑顔を作ってくれた。
僕は、僕は誰の顔も見ることは出来なかった。
そう、僕はおこちゃまだった。
明くる日、倉庫兼更衣室で“ぷり”と二人きりになった。
なにも話はしなかった。
歪んだ空気さえも僕を遠ざけているかのような、そんな凍えた空間で、彼女の甘い海のような香りは感じなかった。
そんな日が幾日も続いたある日、「辻山さん」は高級外車に送られてカラオケ屋に遣って来た。
2F厨房脇の非常階段から、ぼんやりと煙草を吸っていた時、それを見た。
なにかが、僕の中のなにかが“ガタッガタ”と音を立てて崩れた。
僕は、直ぐに3Fフロント前に設置された公衆電話に向かってダイヤルを押した。
その日は金曜日だった。
深夜に差し掛った頃、2F厨房脇の非常階段で煙草を吸っていたアルバイト君達がざわついていた。
「ダークブラックのGTSだ。女だよ運転手。」
当時は大人気で、若い男性諸君憧れの日産スカイラインGTSに乗る女性。
そう、僕の高校時代の彼女だ。
正確には福岡に進学してからも付き合い、別れるを幾度となく、繰り返していた。
彼女は地元で就職していた。
僕は福岡で遊んでばかりだった。
適当だった。
浮気をして彼女を裏切り、また彼女を頼った。
彼女は何度も何度も、僕を受け入れてくれた。
今、僕の中では昔の人だ。
しかし、そんな彼女はどう想っていたかと云えば、わからない。
いや、想像したくないと云うのが本当の気持ちだった。
彼女は電話すれば、直ぐに100キロ近い距離を諸戸もせずに駆けつけてくれた。
どんなときも。
ほんとうにどんな時でも駆け付けてくれたんだ。
僕はそんな彼女を利用したんだ。
僕はおこちゃまではない。
僕は救いようのないクズだった。
2F非常階段がアルバイト達の休憩場となっていることを知っていて、そこから見える位置に車を停めさせた。
僕の思惑通り、アルバイト達は直ぐに気付いた。
先ずは車に注目する、その後車外に出た彼女は、必ず誰かアルバイトの目に留まる。
彼女は何時間もそこで待機している。
彼女はそんな子だった。
その日早上がりをお願いした僕は、2F非常階段から複数のアルバイトが見守る中、彼女の車の運転席に乗り込み、お店を後にした。
「GTSの女は原田の彼女らしいよ。」
「俺見たよ。彼女。暗くてよく見えなかったけど。」
「格好いいよな。」
「格好いい。高くて買えないよ。学生の俺はシビックがいいとこだよ。」
「シビック持ってるだけいいじゃん。」
「けど、いいよな原田さん、GTSに乗ったあんな綺麗な人が彼女で。」
「見えなかったんだろう?彼女。」
「なんとなく雰囲気でわかるでしょう?いい女か“ふなっちゃん”か。」
「そこで“ふなっちゃん”出す?流石に可哀そうだろ。」
「それはそうとして、スタイル抜群で髪の毛が長くて、大人って感じの人だったよ。」
「あいつ、モテるよな。」
「うん。モテるな。奴は・・・。でも原田どうしてんだろうな?」
「なにが?」
「いや、あいつ部屋無しだろう?」
「あ~そう云われればそうだよな。地元の連れのところに居候してるんだったよな確か?」
「それがどうした?」
「いや、あいつ、何処でやってんだろう?」
「そんなのどこでもいいだろう。車の中でもいいしさ、ホテル行ってるんじゃないの?」
「そんな金ないでしょう?」
「GTSの彼女だよ?それくらい彼女さんが持ってるでしょう。」
“ぷり”も“えっちゃん”もいる厨房で、僕がいない時にはそんな話になっていたようだ。
「原田さん、あの人、前に言っていた地元の彼女なんですか?」
ある時、「来月も告白します」と言ってくれた“えっちゃん”が不意に聞いてきた。
「あ~、どうだろうな。よくわかんない。」
真っすぐな“えっちゃん”にまたしても適当な言葉を投げ付けてしまった。
でも、この日の“えっちゃん”は本気だった。
「原田さん、あの人何度も来てますよね。私一度駐車場でお話ししました。」
「・・・・・マジで?・・・いつ?」
「先週です。」
「そ~なんだ。」
「凄く綺麗な人ですね。」
「化粧だろう。高校生の時は酷いものだったよ?」
「その人にしても、「辻山先輩」にしても・・・・・あの、今からもう一度告白します。」
「はぁ、もういいから。」
「いや、します。それで終わりにします。」
「だったら尚更しなくていいよ。」
「いえ、私ヤンキーなんで、その辺はきちっとしたいんで。」
「・・・・・・・・。」
「私と付き合ってくれませんか?」
「ごめんなさい。」
僕は即答した。
その方がいいと思ったんだ。
後腐れなく仲間として働き易いと思った。
けど、それで終わりでは無かった。
「はやっ、」彼女は笑っていた。
そしてこう続けた。
「あー。終わり。もう私は大丈夫です。」
「・・・・・・で?」
「で、あの人彼女さんなんですか?」
「なんでお前にそんなこと言わなきゃいけないんだよ。」
「あのね~原田さん。私本気で好きだったんですよ。それを今スパッと諦めたんですよ。なんでか分かります?」
「えっ、良いの?言っても・・・」
「なんですか?」
「えっ、いや俺がお前に全く興味ないからでしょう?」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・言いすぎでしょう、それ。」
「いや、お前が言えっていうから・・・・・。」
「それはそうなんでしょうけど、それは原田さんの気持ちであって私には全く関係ありませんから、」
「いや、なんか言ってることおかしくない?」
「いいんですよ。まだ私話してる途中ですから。GTSの人にも、「辻山先輩」にしても私敵わないなって思ったんですよ。だから諦めたんですよ。」
「“ぷり”がなんで出てくるの?」
「はぁ~面倒臭い。中学生か?「辻山先輩」は原田さんのこと好きですよ。」
突然の“えっちゃん”の密告に僕は心が躍った。
「そんな気はしていたけどね~。」茶化すことでギリギリだった。
「いや、私真面目に言ってるんですけど。私がそんなこと言ってたなんて“辻山先輩”には言わないでくださいね。なんかイライラするんですよね。多分私が空気読めずに原田さんの事好きだって相談したから、“お姉ちゃん”辛かったと思うんですよね。なんとかしてあげなきゃって。それで何か気まずい感じになっている二人を見てたら責任感じるんですよね。」
「なんか、お前決めつけ激しいな?」
「もう~。はぁ、事実でしょう?」
「・・・・・・・・・・・。」
「それでですね、GTSの人、あの人とお付き合いしてるんだったら私は“お姉ちゃん”渡しませんよ。それだけです。」
「そうですか・・・・。」
「もういいです。私はしっかり伝えましたから。GTSの人が彼女さんであれ、そうで無くても私は知りません。ちゃんとして下さい。」
「おい、・・・・・・・お前格好良いこと言ってるけど・・・・鼻毛出てるぞ・・・。」
「・・・・・・・・そう云うところ・・・直したらもっとモテますよ。・・・・あと、・・・・・・・・二人に振られたら私が付き合ってあげますから。」
“えっちゃん”はそう言って笑顔を見せたが、少し悲しそうにも見えた。
こうして僕と“えっちゃん”の恋物語は終わった。
ここで、主役では無いが活躍してくれた“えっちゃん”のその後をお知らせしよう。
少しだけ今までの脇役より長くなるがお付き合いください。
鼻毛が出ていた日から10日経った頃、福岡市城南区「ニューヨーク80‘S」2F厨房にて、午後19:30頃。
「やっと、見つけた。あんたちょっと顔貸しなよ。」
そう言って金髪にスエット姿の少女2人と、金髪か茶髪かよく分らない髪色をした少年3人が厨房入口から顔を覗かせた。
その内の少女が“えっちゃん”に表に出て来いと言っているようだった。
その時、厨房には僕と“えっちゃん”新人君と、山根君の後輩がいた。
僕らはポカーンとしていたが、“えっちゃん”は嫌そうな顔をしていた。
恐怖であるとか、受けて立つであるとか、そのような、相対するどちらの感情も“えっちゃん”からは感じ取れなかった。
「お店に迷惑が掛かるから・・・帰りなよ。」
彼女は淡々とした口調で返したのだが、彼女達はそれが気に食わなかったようだ。
「いいからさっさと出て来いよ、お前。」
一人、また一人と、そんな感じで大声を上げ始めた。
数々のトラブルを経験した僕はこの日、全く恐怖心は無かった。
恐らくは僕は一番年上だった。
不思議なもので、これ位の年齢の時は、1歳でも年長で有れば、なんとなく心にゆとりが出るものだ。
「おい、どうするのが正解?」僕は“えっちゃん”に尋ねてみた。
彼女は本当に申し訳なさそうに「仕事中に申し訳ないんですが、少し下に行ってもいいですか?」と僕に聞いてきた。
「うん。一緒に行ってやるよ。」
僕がそう言っている頃、「じゃ、駐車場に行きましょうか?」と新人君が彼らを誘導しようとしていた。
「なんだお前、関係無い奴は引っこんでろ。」そのような罵声を浴びせられた新人君は「関係無いこと無いですから、さっ、行きましょう。」そう言って非常階段を降りて行った。
当事者である“えっちゃん”さえも、置いてきぼりを食らった様子だ。
新人君と“えっちゃん”を含めた彼等は駐車場の隅で話を始めた。
僕と山根君の後輩は、厨房裏のベランダからその様子を伺っていた。
ベランダと言っても2Fの為、その距離は僅かで、彼等の会話の内容までなんとなく聞き取れていた。
“ああでもない、こうでもない”と双方の興奮が高まり、収集が付かない状態になって居たその時、少し後ろで見ていた新人君が動いた。
「よし、わかった。」
「俺を好きにしろ。それで勘弁してくれ。」
「????」
僕も、山根君の後輩も、彼等も、そして“えっちゃん”までもが「??」だった。
しかし、新人君の心に灯った火は消えそうも無かった。
「いいから、ほら、ほら、殴れ、殴れよ、早くしろよ、人目に付くし、店長も来るから。」
そう言って彼等の前を行ったり来たり・・・・。
その内自身の根性を試されているかとでも思ったか、少女の一人が新人君の顔面目掛けてパンチをお見舞いした。
そこからは雪崩のように多勢によるパンチ、キックの雨嵐。
新人君は一切手出しせず、亀のように地面に這いつくばった。
僕は直ぐに彼等の元に駆け寄り、割って入った。
「もう、いい加減しろよ。」
良いところだけを持って行った僕は、殴られずに済んだ。
その時、目尻から鮮血、口の中は血だらけの新人君が、立ち上がり言い放った。
「もう、いいだろう。“えっちゃん”のこと勘弁してくれよ。」
彼等は帰って行った。
新人君は身を呈して“えっちゃん”を面倒から救い出したのだ。
新人君は“赤城”を名乗らなかった。立派だった。
そして“えっちゃん”は僕にだけ礼を言った。
新人君は「・・・・・・」何度か無表情で頷いていた。
僕は思った。
やっぱり、人を好きだと云う感情がすべてだと。
好かれていなければ、どんなに努力をしても、どんなに食い下がっても報われないのだと・・・・思っていた。
“えっちゃん”にご挨拶に来た彼等は福岡市の早良区辺りでは有名な○○という暴走族の連中だったらしいのだが、“えっちゃん”は無事に仲間から離れることが出来たようだった。
話は横道に逸れるが、これより半年ほど前、僕の同居人“大水”は○○という暴走族にセブンイレブン裏の空き地で暴行を受け、最後に“ホームランバーバニラ味”をたっぷり顔面に塗りつけられたらしい・・・。
「俺、もうすぐ20才よ。・・・・。」彼は悲しそうに呟いていた。
そんな“えっちゃん”はその後、急速に拡大を見せる“ニューヨークグループ”の中核メンバーとして活躍して行くことになる。
次々と出来る新店舗のアドバイザースタッフとして沢山のアルバイト達を指導して行った。
僕という呪縛から解放された“えっちゃん”はその後、複数のアルバイト達を相手に浮名を流すこととなる。
僕の元には、その頃には既にカラオケ屋のアルバイトを辞めていた新人君から悲しみの報告が齎されていた。
そんな“えっちゃん”はお金を貯めて、大検をクリアして、見事大学生になった。・・・・・・・・・りはしなかった。
「ニューヨークグループ」を離れた彼女は中洲で更なるキャリアを磨き、雑餉隈という南の歓楽街で2店舗のクラブを経営する敏腕ママとなった。
当初こそ「飲みに来んですかー。原田さん。」と云う“えっちゃん”の誘いに乗ってみようかとも思っていたが、パワーアップした彼女を想像して身震いした僕は、その後彼女に会う事は無かった。
“えっちゃん”に関して最後は良い話で締め括ろう。
二年もの間“えっちゃん”を愛し続けた新人君はその後、見事恋人同士になりましたとさ。
“想いは叶う”新人君から教えられた気がした。
随分と逸れてしまったが、僕と“ぷり”の話に戻るとしよう。
その話を聞いてからも、僕と「辻山さん」に流れる隙間風は収まる事は無かった。
二見ケ浦での余りに幼稚な僕の発言、地元の彼女に関する噂や、憶測も在ってか、彼女から僕に近付いて来ることは無くなった。
自称“モテ男”の僕は心を閉ざした相手と接する術を持ち合わせてはいなかった。
しかも、GTSの彼女に関するアルバイト達の話は、そのほとんどにおいて事実と相違無かった。
そして、意図的に僕を遠ざけていた「辻山さん」は、いつかの高級外車から降りてくることは、もはや珍しい事では無くなっていた。
僕が最も気になっていた高級外車に関する情報はやはり、アルバイトの噂話から齎された。
「昨日も「辻山さん」送って貰っていたね。」
「あ~見た。あのピカピカの車でしょう?」
「俺も先週見たよ。あれポルシェのなんとかって云うやつだよね?確か。」
「911?」
「違う、それじゃないよ。出たばっかりの新型なんだよ、なんだったかなぁ。」
「ボクスタ―。」
きっと正解は出ないであろうと思い、事前に調べ上げていた僕が答えた。
「ポルシェ・ボクスターだよ。」もう一度駄目押しだ。
「そうそう、それだよ、それ。」
歯医者の親を持つ、実家がお金持ちかどうかまではわからないアルバイト君が確証を与えてくれた。
「高いだろう?500万円位するの?」
「馬鹿言ってんなよ。500万で買えるかよ。1500万いや2500万位はするよ。」
実際には700万~800万円位だったと認識していたが、敢えて僕は訂正しなかった。
20歳そこそこの僕にとっては500万だろうが2500万円だろうが一緒だった。
見た事も無ければ、稼いだことも無い。
今だけではなく、将来に渡っても自分がそんな車に乗る姿なんて想像も出来なかった。
そしてこの頃にはもう、「辻山さん」と僕は唯の友達だとする結論が、アルバイト達の共通認識だった。
更に同時期、「辻山さん」の出勤日数は日に日に少なくなっていた。
膨大な量の提出物と格闘していると思いたい所ではあったが、アルバイト達の話はそうではないようだった。
そしてそこで僕の知らなかった、僕が一番恐れていた、唯一の情報が齎された。
「ポルシェの人。「辻山さんの彼氏らしいよ。」
「まぁ、そう考えるのが妥当だよね。」
「しかも、特別大きな衝撃も無いよね。だって「辻山さん」だったらそんな彼氏が居たってなんの不思議もないもん。」
「確かに、むしろこんな所でアルバイトしていることの方が違和感の塊だよ。」
「納得・・・。」
「納得だね。」
アルバイト達が結論に達した頃、僕もまた、
“納得”した。
他人の口から聞くことで余計に現実な思いに引き戻される。
彼女は僕と同じ空間に居ながら、見ている、感じている世界はどれ程の開きがあるのだろうか。
僕じゃなければ、もっと大人だったら、いや、ポルシェの人だったら、彼女のあの海の香りのような甘い匂いが何であるのかを知っている気がしたんだ。
僕が住んでる小さな世界・・。
デビルなんかが恐れる恋敵などでは無かった。
でも、この時でさえ僕は気付いていなかったんだ。
そう、そして「辻山さん」ですらそれが見えずにいたんだ。
2
“ポルシェの男。それは、彼女が働くBARのオーナーだった。”
得体の知れぬ相手と戦うよりかは、わかっていた方が幾分かは良い。
もっとも僕はと云うと、完全に戦意喪失状態であったのだが・・・・。
しかもその頃の僕は、大きな変化の中にいた。
デビル同様にアルバイト入店から半年も経たず主任となった僕は、数ヶ月後にはこの城南店の店長となる事が決まっていた。
成長著しい会社にとって、フリーターの僕は貴重な人材だったようだ。
覚えなければならない仕事はとにかく膨大だった。
店長になる事が決まってからの僕は、昼も夜も無くお店に居ることが日常となった。
新店舗の店長に決まっていたデビルはそちらの開店準備が忙しいらしく、城南店に顔を出す日は極端に減っていた。
僕はその代役として城南店の采配を揮うことが増えて行った。
しかし、現実は厳しく僕に圧し掛かった。
結論から言えば、20才になったばかりの僕に、昼の部、夜の部を合わせた合計27名のスタッフを束ねることは無理だった。
“えっちゃん”や新人君、山根君の後輩など、僕より年齢が下で、僕よりも入店が浅い人間にしか、指示を出すことが出来なかったのだ。
いちアルバイトとして働いていた時には、マスコットのように可愛がってくれた昼の部の主婦達からも、その統率力の未熟さゆえ陰口を言われる対象となっていた。
陰口などは良い方で、夜の部のスタッフからは、直接その能力を疑問視する声が、僕の目の前で聞こえてきた。
そんな時、僕に出来る事は無視を決め込むこと、それだけだった。
今ではもう「辻山さん」の居なくなった待合室で一人、暗がりの中、重圧と戦う振りを、更には苦悩する青年の姿を、如何に効率よくアルバイトに見付けてもらい同情を引けるか、そんなことしか僕には出来なかった。
身内からの非難はまだ良い方で、頻発するトラブル対応でお客様の前に立ったときなど、「お前みたいなガキが責任者か?」と何度言われたことか、数えきれないほどだった。
様々なトラブルで経験を重ねたつもりになっていたものの、自分が責任者として対峙する問題はどんなに小さなものであっても、僕の膝を震えさせた。
トラブルひとつ解決できない僕は、更にスタッフの信頼を無くすという負の連鎖の中、少しずつ、でも確実に心を壊していくことになる。
僕は、以前起こした対人事故の瞬間を思い出していた。
“やばい”と追い込まれると同時に“夢であってくれ”と願う、その現実逃避は今では、毎日のことだ。
群れからはぐれた小魚は気が付いた。
先頭を逞しく泳ぐリーダーがいて、周りを取り巻く楽しい仲間達に紛れて泳ぐ大海原は、どこまでも澄み切った青で、海上の雷雨、更には高波などの障害を感じることは微塵もない。
もっとも、そう思っていた大海原も、今となっては内海の汀線辺りに過ぎないことも熟知している。
ただ、如何に落第人間の僕でもわかっていたことがあった。
“僕は、仲間達に紛れて泳ぐわけにはいかない。”
“僕は、先頭を泳がなければならない。そうでなければ、はじかれ、迷い、泳ぎ着かれたその先に待つのは暗く深い、何処までも暗いその先に沈んでいくだけだ”
そう思っていた。
「辻山さん」と出会った時の、あの惹き込まれるような、青い海のような甘い香りは今、僕には届かない。
一人悶々と悩む仕草を続けたところで、状況が好転することは無かった。
アルバイトの大学生達は、試験期間が迫ると、お店の営業お構いなしにまとまった休みを一斉に取った。
そしてそれが終わると、過剰人員関係ないとばかりに、希望通りのシフトを入れた。
勿論、そんな彼等を束ねることが出来ない僕にすべての責任があることは明白だった。
銀行から転職して来ていた坂田部長からは「原田君、数字読めるか?前年同月対比って分かるか?あいつらを調子に乗せたらいかんよ。」とご指導を賜る日々だった。
ヤクザよろしくアルバイト達をあいつら呼ばわりした坂田部長は、その後も頻発するトラブル処理の為に、城南店に来る事は無かった。
目覚めて迎える楽しみでしかなかった僕の居場所は、自身の城となった今では、その居場所を無くそうとしていた。
そんな僕の心の拠り所は、恋人になれるかも知れなかった「辻山さん」などでは無く、どんな時でも文句の一つも言わず、駆け付け、寄り添い、励ましてくれるGTSの彼女だったことは言うまでも無く、もう僕にダイヤルを押すことへの躊躇いなどなかった。
破壊された青年の心は更なる破滅を手繰り寄せる。
俺が必要としているのだから傍に居ればいい。
静かに、俺の愚痴に頷いていればいい。
爛爛と、俺の自慢話に目を輝かせていればいい。
俺が欲した時にうっとりと見詰め返せばいい。
そして感じて、荒々しく、身をくねらせてさえいればいいんだ。
そんな、お前が必要なんだ。
ありがとう、今までずっと。
ありがとう、これからも。
馬鹿な男の歪んだ愛情も、その想いを伝えて、貫き通すことが出来るならば女性も幸せかも知れない。
そんな簡単なことすら僕は出来なかったんだ。
“ねぇ、あなたの愛した人はこんな人ですか?”
“ねぇ、あなたの隣にいる人はどうしようもないクズですか?”
“ねぇ、自分で決めた事だからって諦めていませんか?”
“ねぇ、あなたは幸せですか?”
“僕はあなたを苦しめていませんか?”
“僕は、僕は、僕には、他に好きな人がいます。”
献身的な彼女の胸の中で、激しく交差する善意と悪意。
いや、何が善で、何が悪かもわからなくなっていた。
ただ、すべての感情は掴めないその先の、またその向こうにあるなにかにつき動かされるようであった。
そして、それから何度目かの彼女のテールランプを見送ったその夜、僕は彼女に電話をした。
ボタンを押す指が震える。
頭の中で整理した筈の繰り返された綺麗事は、僕の中の創られた世界だけのもので、真っすぐな彼女を前にしてはその影すら浮かぶ事は無い。
「話があるんだ。」
「うん。」
彼女の「うん。」はすべてを理解した「うん。」だった。
僕には分かった。
何故なら彼女はずっと、僕の為に自分の感情を押し殺してきたから。
そんな彼女の「うん。」は今までに無い、不安と悲しみを抑えきれない、そんな「うん。」だったんだ。
時間が止まる。
静止した時間の中で、彼女の優しさだけが蘇る。
その優しさに映し出される鏡には、どこまでも利己保身な醜い自分が浮かんだ。
これまでとは違う、本当の終りを迎えようとしている今、覚悟が無いのもまた、僕の方だったのかも知れない。
「・・・あのな、俺・・・・・・・、」
「ねぇ、・・・・・・私が傍に居て幸せだったでしょう?」
「えっ、・・・・。」
「私、めちゃくちゃ幸せだったよ。」
「・・・・・・・・・・・ぐっ、くぅぅぅ、ぐっっ」
僕はもう、溢れる涙が止まらなかった。
ずっとずっと。
今までの彼女への数々の愚行が脳裏を駆け巡っていた。
「どうしたの?泣くなんて柄でもない。私、泣かないよ。今日まで何十回も泣いてきたもん。」
彼女は泣きながらそう言ったんだ。
「私、いつでも幸せになれるんだよ。でも、最高の幸せはもう君に貰っちゃたから、後はね、程ほどに幸せになるよ。」
泣き続けるだけの僕に彼女は言葉を重ねた。
そんな彼女のやさしい嘘は深い霧から僕を解放してくれた。
「好きだったんだ。本当に。あとどれくらい時間が流れれば、どれほど大切なものを失ってしまったのか気付くことが出来るかも知れない。そんなことの繰り返しだった。俺、幸せだったよ。本当にお前が居てくれて幸せだった。」
尚も泣き続ける僕が彼女に言った最後の言葉だと記憶している。
“ごめんなさい”と言うのはあまりにも失礼で、“ありがとう”と言えば彼女は二度と戻って来ない気がしていた。
彼女ももう、号泣していた。
「ねぇ、憶えてる?高校三年生の夏、私に声をかけてくれた時のこと。まさか君から話しかけられるなんて思っても見なかったよ。舞い上がったよ。
そして、その後・・・・・彼女にしてくれた。
それだけで私はうれしかったよ。なのに、福岡に行った君はその後も連絡をくれた。
高校を卒業する時が最後だって思っていたから。
ひょっとしたら、このままずっと一緒に居られるんじゃないかと夢見ちゃいました。
高校を卒業して、就職して・・・めちゃくちゃしんどいことも多かったけど、君が連絡くれたから、傍に居させてくれたから・・・・たくさん思い出くれたから・・・・。
そして今、まさか君が私の為に泣くなんて・・・・。
それだけじゃない。
“幸せだった”なんて言葉聴けるなんて思ってもみなかった。
まさか、私に酷いことしたなんて思ってない?
私は幸せだった。
君から連絡が来ない時でさえも、もしかしたら連絡が来るかも知らないと思えるだけで毎日が生甲斐だった。
こんなに人を大切に思えることを教えてくれた君は、すごく特別な存在なんだよ。
きっと他人は言うだろうね?
若い二人の一時の感情だって・・・。
でも、私にはわかるの。
ちがうな、わたしにはわかっていたの。
君との日々は私が年を取って尚、色褪せない最高の日々に成ることを。
これからの人生で沢山の出会いや恋愛を重ねて行くかも知れない、次に出会う人と結婚して子供を産むかも知れない。
でも、それは結果であって私の我儘じゃないの。
言っていること難しいかな?
いつか君にもわかって貰えたらその時は本当に幸せだよ。
私のこの想いが本物かどうかは私がこの世から居なくなる時しか確認しようが無いけれど多分間違いないかな。
私は君よりかは幾分か大人だからね。
ありがとうね。
私は自信を持って前に進んで行ける。
きっと君もそうだよ。
今まで本当に、本当に、幸せだった。
ありがとう。」
そう言って彼女は電話を切った。
僕のことを唯一“こうちゃん”と呼べなかった彼女とはその後、二度と会う事は無かった。
無くした気になってみても、無くして分かることってやっぱり、無くさないとわからなかった。
過去の発言や、過ちは一晩経てば忘れてしまえばいい。
そうして僕は大人になるのだから。
はやく大人になりたいと云う人がいた。
先のことが知りたいと思った。
大人になど、なりたくないと云う人がいた。
先のことなど考えたくないと思った。
時間は止まらないのだから。
その後も直面する毎日は、益々僕を追い詰めていく。
でも、彼女との別れはほんの少しだけ、僕に勇気をくれたようだ。
僕は、お店の都合通りのシフトに入れない、入るつもりのないアルバイト達に辞めてもらった。
僕を店長として認めるつもりのない者にも、辞めてもらった。
そして、ちょうどこの頃、大学4年生のアルバイト達が一斉に辞めた。
大量の新規アルバイトを採用したことで、お店の雰囲気は一変した。
“ふなっちゃん”は別格だとして、“えっちゃん”も新人君も今では立派に先輩面だ。
テキ屋あがりの彼や、生活の懸かった主婦、フリーター諸君は新たに船出しようとする新生城南号に乗り込んで来てくれた。
自信は人を変えていく。
「お前みたいなガキが責任者か?」と言われる事もほとんど無くなっていた。
そして、デビル同様に未熟な僕を“店長”と呼び、育ててくれていた“ふなっちゃん”から言われた。
「私、原田くんの為にお店辞めるね。私、本当にこの店が大好きだった。だけど新しく生まれ変わった今、私が居たらダメな気がする。ねぇ、立派な店長になってよ。」
こうして、僕は新たな仲間のリーダーとなって大海原の先頭を泳ぐこととなる。
僕の背中を押してくれた“ふなっちゃん”最後の夜、沢山の元アルバイト達が彼女を労いに遣って来た。
僕の知らない顔も随分といた。
元アルバイト達は城南店でも一番大きな部屋を5時間以上貸切って、飲めや歌えやの大騒ぎで、彼女を送り出した。
そこには久し振りの「辻山さん」も駆けつけていた。
僕は、なんとか話すきっかけが欲しかった。
それでも、見ず知らずの人達が多い中、部屋に分け入り「辻山さん」を連れ出す程の勇気は持てなかった。
いや、それだけではない、本当は彼女に拒まれることを何より恐れていた。
今日は”ふなっちゃん“の晴れ舞台だ。
そんな大切な日に雰囲気を壊すような真似は控えようとする、何か別の理由を見付けて、大切なことを先送りにしようとする悪い癖だ。
僕はまだまだ弱い人間だった。
大きな窓ガラスに投影された薄ら眩い電飾看板の明りと、ゲーム機から出る直接的な光の相まった待合室の中でも、一番薄暗い場所を見つけて僕は腰を下ろした。
季節は春の訪れを感じるにはまだ早く、暖房を切った待合室は底冷えのする寒さだった。
今までどれだけの人が腰を下ろしたであろう。
そのソファーは布張りで、ペルシャ絨毯のような特徴的なデザインの施された高級感漂うものだった。
気を抜けばどこまでも沈んで行きそうな、そんな時化の中に居た。
平日の深夜。
さすがの繁盛店もこの時間帯に待合室は稼働していない。
一人で考え事をしたり、黙々と作業するには丁度いい。
人は何故に暗い部屋を好んで悩み事をするのだろう。
太陽が燦々と降り注ぐ中においては、悩みごとなど出来ないか。
それどころか、悩みごとそのものが吹き飛んでしまう。などという言葉を聞いたことがあるだろう。
僕はそうは思わない。
本当に辛い悩みや、抱えきれない問題は太陽の日差しの下でもなくなることは無い。
ただ気持ちを切り替え、その悩みや問題と向き合う勇気を与えてくれるだけだ。
よってその悩みや問題と向き合うことからは逃げられない。
そして、悩み事と向き合うにはやはり、薄暗い静かな場所が最適だ。
ゲーム機の明りさえ目障りで、僕は電源コードを引き抜いた。
先程まで座っていたソファーは大きく窪み、同じ場所に僕を誘う。
一時間程経過した頃、待合室のドアが開いた。
悩んでいる青年の姿を誰かに見付けてほしい訳では無い今の僕には、迷惑な侵入者だ。
僕の大事な時間を邪魔しに来たその侵入者は、入口傍のソファーに傾れ込むように座った。
外からの明りのみに頼る待合室にあって、その侵入者がどこの誰なのかは全く分からなかった。
そしておそらく、先客がいることを知らないであろうその侵入者と僕の二人は、暫くの間、奇妙な時間を共有した。
たとえ物音一つしない暗い空間であっても、誰かが居るのと、一人で居るのとでは天と地ほどの差があるものだ。
その奇妙さに耐えられなくなった僕は、こちらの存在に気付いていないであろう侵入者に配慮して大きな咳払いを一つしてからソファーを立ち上がった。
驚かせてしまっては申し訳ないという僕の配慮などお構いなしに、その侵入者は無反応を決め込んでいた。
流石に限界を迎えた僕は、待合室から出ることを決め、入口へ向かって歩き出す。
この待合室は普段から施錠などしていなかった。
その為、酔いの周ったお客様が勝手に入って寝込んでしまうケースや、極稀ではあったが外を歩行中のお客様でもない方が忍び込み、朝まで熟睡なんてこともあった。
何フロアか上には「辻山さん」が居ると云うのに、酔っぱらいの世話などしたくもない、と無視を決め込もうかとも思ったのだが、今や僕はこの店の責任者だ。
そういう訳にも行かず、その迷惑な侵入者に目を向けて、・・・・・その人だとわかった。
正確にはその侵入者に近づくたびに大好きなあの香りに心躍っていた。
「なにしてるんだ、お前。こんなところで。大丈夫か?」
僕は久しぶりのその人にぶっきらぼうに問い掛けた。
「うん。平気だよ。ちょっと呑み過ぎただけだから。」
「そうか。ゆっくり休んでから部屋に戻りなよ。暖房入れとくから・・・。」
そう言って僕は入口ドアに手を掛けた。
待っていた。
時間にして1秒、2秒、あるかどうかだろうが、僕は待っていた。
彼女からの返答を。
このまま彼女からの返答がなければ、もう彼女と話す機会は来ないかも知れない。
「あなたこそ何してたの?電気も点けず、ずっと?」
ホッとした。
まだ彼女と話すことが出来る。うれしかった。
「考え事してたよ。」
「そっか。そう言えばあなた、店長になるんだよね。」
「そうだね。」
「おえでとう。」
「うん。」
単語だけのそっけない会話になる事は予想出来た。
ただ、ここまで言葉が出てこないとは思っていなかった。
なにか話さないと、そう焦れば焦るほど余計に言葉は出てこない。
そんな僕に彼女は、またも助け船をくれた。
「座れば?」
「・・・・。」僕は無言で彼女の横に腰を下ろした。
「なんだか雰囲気ちがうね。」
「そうかな。スーツ着てるからじゃない?」
「ホントね。スーツ着てる。ふふっ、あなたがスーツ着るなんてね。」
「なに、おかしい?」
「おかしいよ。そりゃぁ・・・」
「なんで?似合ってるって言われるよ?」
「あなたはいつもそればっかりね。~言われるよってそればっかり。」
「ん?なにが?」
「他の人がなんて言おうが、どう思おうが私には関係ないの?わかる?わからないかなぁ?」
「いや、わかるけど・・・。」
「他の人は似合ってるって言ったんでしょう?でも私は似合って無いと思う。」
「そっか。似合ってないのか。」
「うん。似合ってない。・・・・・他の人なんてどうでもいいでしょう。」
「・・・・・・・・・・そっか。」
「あなたが他の人からどう思われているとかどうでも良くて、そんなことより、あなたは自分の意思が無くて、他の人の意見をさも正しいことのように・・・・ムカつくよ、わたしは。」
彼女は怒っていたと思う。
彼女はいつも周りに笑顔を振りまく。
でも僕にだけは、その笑顔の何倍も怒りをぶつけてくる。
「あのさぁ、俺、どうしようもないくらい好きな人いるんだけど、どうしたらいいと思う?」
「何?突然に。知らないよ。そんなこと。」
「他の人じゃなくて、“ぷり”の意見が聞きたいんだよ。」
「久しぶりだね。その呼び方。」
「うん。どう思う?」
「だから知らない。面倒臭い。好きにしたらって感じだね、私からしたら。」
「そっか。」
「そうだよ。みんな喜ぶんじゃないの?あなたから告白されたら。だってあなたはモテ男なんでしょう?」
「お前はいつも厭味ばかりだな。久しぶりに話すって言うのに。」
「いや、厭味とかじゃなくて、興味が無いだけ。なんだかあほらしくなってくるわ。」
「興味持ったら?自分のことなんだからさぁ。」
「またそれ?いらないから本当に。」
「・・・・・・・・・・・・。」
「全然成長しないよね、あなたは。」
「成長してるよ。お前の云う他人の評価じゃない。自分自身でそう感じてるんだ。
みんなそれぞれあるだろうけど、俺にも有ったんだよ、色々と。」
「だから?」
「・・・・・・。」
僕は彼女の心の中がわからなくなった。
もし僕の独りよがりだったら?
彼女には素敵な大人の恋人がいて、その人と同棲していたら?
将来を約束している二人だったら?
“僕はとんだお笑い者だ”
彼女に返す言葉は見つからず、僕は、ゆっくりと煙草を燻らせた。
「1本貰える?」
彼女はそう言うと僕の答えを待たずして、久し振りとなる煙草に火をつけた。
彼女は煙草を辞めていた。
“これからは喉を大切にしないと”そう言っていた。
おそらくは、今後の仕事を考えてのことであったことは間違いないであろうが、敢えて彼女は僕に理由を説明することは無かった。
「煙草・・・・また始めたのか?」
「今だけよ。お前のせいだ。お前があんまりイライラさせるから・・・。」
「“ぷり”・・・・・・冗談でも何でもない。お前のことが好きなんだ。」
「・・・・・・・・・。そう。」
「そうって・・・・。」
「知ってる。知ってたよ。」
「ダメかなぁ、俺じゃぁ。」
「ダメとかそんなことでは無い。ただ怖いよ、私は・・・。ただただ怖い。」
「・・・怖い?わかるよ。」
「分かるの?あなたに?」
「多分。」
「なにが?なにをわかるの?」
「年齢だと思う・・・・。俺も初めてだけど・・・お前の方が俺よりもっと怖いと思う。」
「・・・・・・・“べー”にしてはすごいね。ほぼ正解だよ。」
「そりゃぁ、そうだよ。俺もずっと悩んでいたから。でもさぁ、もう深く考えずにさぁ、勇気出してみない?お互いに。」
「私いやだよ・・。お互いが十年後ならいいよ。そうしたら4才の歳の差なんてなんてこと無いことくらいわかるよ。でも、この間まで高校生だった四つも年下の男の子に片思いしたり、裏切られたり、そんな経験今まで一度もないから・・・・・。」
「俺も悩んだよ。年上の女の人に弟としてしか見られて無いんじゃないかと悩んだ。勘違いして告白して、その人のこと傷つけるんじゃないかと考えたよ。そして、自分が、俺自身が傷つくことが怖かったよ・・・。」
「・・・・・・・・・ねぇ、あなた本気?わたし本気にするよ?いいの?」
余りにも蒼い二人だった。
今の年齢となった僕がその場に居たなら、あまりの蒼さに苦笑していたに違いない。
いや、今の歳に成っても癒えぬその傷を想えば、儚いその蒼に嫉妬するのかも知れない。
「俺はずっと本気だよ。お前にヘッドロックされたあの時からずっと好きだった。」
「・・・・・・・変なところで好きになったのね“べー”は・・・とても複雑だわ・・。」
「・・・・・そういうのは今いいんだよ。・・・・告白中だろ・・・。」
「そうね。凄くうれしいよ。でもね、私、今お酒入っているし、あなたには確認しておきたいこともある。」
「うん。わかってる。」
「だから明日、きちんと話しない?」
「うん。わかった。でも、明日になって今の話は全く無かったことになるのは嫌だ。」
「それは無いわ。私の気持ちも固まってる。でも中途半端は許せないから。ねっ?いいでしょう?明日。」
「うん。」
「じゃぁ、明日私の家に来て。いつものところで待ち合わせしよ?いつも送ってくれていたあそこに15:00。」
「わかった。」
顔が、体中が、熱く火照るのを感じていた。
先程入れた暖房の所為だろうか?
あの、底冷えするほどの寒さの方が丁度良かったのかも知れないと、僕は思った。
その後顔を出した厨房には“えっちゃん”が居て、僕を見るなりOKサインを指で作り、答えを促すように顔を小刻みに揺らした。
僕は、ゆっくりと頷いた。
“えっちゃん”は、それはもうニコニコとして、はにかむ僕と一緒に喜んでくれた。
後日談だが、僕が待合室にいることを“ぷり”に伝え、延々と渋る彼女をそこまで連れて来てくれたのは“えっちゃん”だったそうだ。
翌日、“ぷり”との約束の時間となった。
初めてとなる彼女の部屋を想像しながら歩いた。
彼女の家は「ニューヨーク80‘S」から歩いて15分程の所だと聞かされていた。
「黒田屋」とは逆方向で、以前から“危ないから送って行く”と、家の近所までは行ったことがあった。
しかし毎回、“この辺りだから、ありがとうね”と、言う彼女の言葉に、家までは行ったことは無かった。
そのことも僕に、余計なことを考えさせる要因のひとつであった。
“きっと真新しいお洒落な家に違いない”であるとか、“彼氏を匂わすなにかがあるかも知れない”だとか、期待と不安が交互に押し寄せていた。
いつもはお別れする場所で、“ぷり”は待っていた。
「よー。“べー”」
「お~“ぷり”」
一言会話を交わしただけでもう、僕らは大丈夫だと思った。
お互いを“べー”、“ぷり”と自然と呼び合える僕らに何ら問題などないのだ。
そしてこの日は彼女を知れる日であり、僕の抱えていた不安を消し去る日となるだろう。
約束の場所で待っていた彼女は、いつもと違って見えた。
栗色の綺麗なストレートの髪で、頭の上に“だんご”を作っていた。
その砕けた髪型には不釣り合いなほど丁寧に化粧をしていた彼女の、唯でさえ妖艶な表情は、今日は特に際立っていた。
今更ながら、“綺麗だ”と息を呑む程だったあの想いは、この時から今まで忘れる事は無い。
あまりの綺麗さに、彼女が初めて“ミニスカート”を穿いていたことに気が付かなかった程だ。
当然、数時間後にはこれでもかと言うくらい文句を言われた訳だが・・・・。
待ち合わせの場所から彼女の家までは僅か20秒程で、それは想像していたような綺麗で新しいマンションなどでは無かった。
古ぼけたハイツの1階部分の部屋のそのまた一部屋が彼女の家だった。
「ただいま~」
彼女はそう言って部屋へ這いって行った。
「さぁ、上がって。」
そう言いながら、玄関の靴を整理した。
「お邪魔します。」
蚊の泣くような声で挨拶をしながら僕は彼女の後ろへと続く。
「こっち。こっちが私の部屋だから。」
「あっ、うん。失礼します。」
誰かに聞こえる筈も無いような小声で呟きながら、初めてとなる彼女の部屋へと足を踏み入れた。
「びっくりした~?」
「ん、いやべつにそんな事無いよ。」
「“べー”あなた嘘が下手ね、動揺が隠せてないわよ。」
「うん。びっくりした!びっくりしてる・・・・・。」
僕は表情を崩した。
「こんなオンボロに住んでいるイメージ無いよ。“ぷり”は。」
「はっきり言い過ぎよ、あなた。まぁでもそう思うよなぁ普通。」
「いや、部屋がボロいって言っている訳じゃぁないよ。なんだか“ぷり”のイメージに合わないってだけの話さ。」
「どうだかね・・・。ここに住んで一年足らずってとこかしら?男の人を入れたのはあなたが初めてだよ。」
「それは光栄です。」
「さて、じゃぁ、何から話しようか?」
「どれからでもいいよ。」
「あなたも質問あるだろうけど、先ずは私から聞こうかな?」
「うん。」
「彼女とはどうなってるの?」
“ぷり”は一切の妥協無い、真っすぐな目を僕に向けていた。
「もう二度と会う事は無いよ。」
「それはどういう意味?きちんと説明して。」
僕は高校の時からつい先日の別れまで、嘘偽りなく彼女に話した。
彼女もまた、途中で口を挟むこと無く最後まで僕の話を聞いてくれた。
そして、色々と言いたい事もあったのかも知れなかった彼女は、一言だけ僕に向けた。
「素敵な人だったのね。あなたのこと信じていいのね?」
僕は彼女の眼を真っすぐと見て、大きく頷いた。
彼女は笑顔を見せた。
そして「次は“べー”の質問に答えるよ。」とニコニコしていた。
「じゃぁ、聞くね。」
「ドキドキ、あ~きんちょ~。あっ、エッチなやつはまだ駄目だからね?」
「聞くかよ、そんな事。・・・・後の楽しみだろそんなものは。」
「あっ、やっぱり聞くんだ。・・・・何か照れくさいね。」
「いや、そんな恋愛モードに入るのは俺の質問に答えてからにしてくれよ。」
「あっ、いやでもそんな急にスイッチ入るタイプじゃないからさぁわたしは。覚えといてね~“ぼくちゃん”」
「・・・・いや、どうでもいいんだけどね・・・なんでまた急に“ぼくちゃん”?」
「え~だって、“べー”と“ぷり”じゃぁ、なんかムードでないじゃない?だからなんかこう~ねぇ、なんか、ほらそういう雰囲気の時はさぁ、なんか別の呼び方でもいいんじゃないかなぁ~ってさぁ。」
彼女はかわいく笑っていた。
とても恥ずかしそうにしていた。
「・・・・・なに?やりたいのかお前・・・・・今?・・・もう?」
「・・・・・・・・・・・・・そんなわけないだろ、バカたれ。」
「だよな?びっくりさせんなよ“ぷり”」
「・・・・・・・・・・お前には一生させてあげるつもりはないからな。」
「・・・・・・・・・・そろそろ質問したいんだけど?」
僕は彼女が働くBARのオーナーである人の話を聞いた。
彼氏ではないのかと。
彼女は大笑いをして「そんなことあるわけない。」と言った。
そして彼との関係を全て話してくれた。
BARのオーナーとは仕事以外一切の関係は無いらしかった。
そして、もう直ぐ現われるであろう、この家の主こそがその人の彼女であること。
さらにはこの部屋はそのオーナーが借りていること。
その彼女とは大学入学以来の親友で、彼女の紹介により、BARで働きだしたこと。
それから、海外へ留学するときに自らの家を解約して、ここに居候になっていること。
最後に聞いたのは、彼女の親友である自分に言い寄ってきたBARのオーナーに腹が立ち、そのバイトを数日前に辞めたこと。
それから彼女の前の彼氏と云うのは、そのBARのオーナーの知り合いの、別のBARのオーナーであったこと。
更には、その前の彼氏は大学の同級生で、彼女より二年早く卒業して外資系金融機関に就職している180センチ以上はあるイケテル人だったこと、さらにその前の彼氏は・・・・・このあたりで僕は聞くのを辞めた。
今日の話も一日寝て忘れてしまおう。
そうして僕は大人になるのだから・・・・。
「今日はいつもと雰囲気がちがうなぁ。」
「そうかしら?いつもと同じでかわいい“ぷりちゃんよ”」
「・・・・・・・いや、いつも綺麗だけど今日は特別だよ。」
「“べー”どうしたの?自棄に素直だね?なんか怖いよ。」
「今までずっと茶化して意地張ってきただろう?いい加減素直になろうと思ってさぁ。」
「ありがとう“べー”わたしもあなたが大好きだよ。愛おしいよ。」
「・・・・・・・・・。でもほんとに今日は綺麗だよ。」
「どうした、どうした?いつもと一緒だよ。ただここだけちょっと違うかなぁ。」
そう言って彼女は大きな瞳を閉じて瞼を指差した。
「青・・・・・色?」
「そう、今日はブルーのアイシャドウで攻めてみました。色っぽいでしょう?」
「うん。」
僕はそう頷いてからずっとその惹き込まれるような青色に釘付になった。
その後しばらくは彼女が何を話していたのかも思い出せない。
とにかくあの艶っぽい青色に心奪われていた。
その時より、今でも「好きな色は何色?」との問いに必ず僕は“青色”と答えるようになった。
そんな僕の浮かれた気持ちを引き裂くように“ぷり”の部屋の扉が開いた。
「いらっしゃ~い。あら、ほんとにかわいい子ね。こんにちは“ぼくちゃん”・・。」
「こんにちは。お邪魔してます。」
「ゆっくりして行ってね。あっ裕子、冷蔵庫においしいメロンがあるよ。」
「サンキュー。遠慮なく頂くね。」
そして、奥の部屋から大きな声が聞こえてきた。
「OK。あっあと、ルール守ってよ~。壁薄いんだから。」
「ルールってなに?」僕は彼女に尋ねた。
「いいの。あなたは気にしなくて・・・・。」
「なんでだよ。」
「はぁ、しつこいよ。“べー”」
「ていうか、あの人まで“ぼくちゃん”って・・・。」
「仕方ないよ。気にするな。」
「いや、気にするだろ。それこそお店に来られて“ぼくちゃん”なんて呼ばれた日にはアルバイト達に合わせる顔が無いよ。」
「へー。“べー”もそんなこと気にするようになったか~。」
「当たり前だろ。自分たちの店長が“ぼくちゃん”なんて言われていたら、嫌だろみんな。」
「どうかな?人はみんな初対面のイメージは崩れないものよ?例えばあなたが10年後、いや10年じゃぁ無理ね、20年後でもいいわ。立派な社会人でも、社長さんでもいいわね。そうなった姿を見ても彼女は多分あなたのことを“ぼくちゃん”って呼ぶと思うよ。」
「そんなもんかなぁ・・・。まあ、その時お前達はくそババアだけどな。はっはははは。」
「おもしろい冗談言うわねぇ。もう帰る?」
「いえ、もう少し居させて下さい・・・。」
「分かればいいのよ。」
それからどれくらい話をしただろう。
そろそろお店に行かなくてはいけない時間が迫っていた。
「そろそろ行くよ。」
「もうそんな時間?なんだか寂しいね。」
彼女がそう言った時、この世界で二人きりになったような不思議な感覚に包まれた。
彼女が目を閉じ、僕の目の前には綺麗な、どこまでも惹き込まれるような青色が広がっていた。
僕らはキスをした。
途中、僕の手は彼女の洋服の中へ伸びたが、“ぷり”はそれをブロックした。
「ダメ。」
「ごめん。付き合った早々・・・。」
「そうじゃないけど・・・・。ルール違反になっちゃう。」
なるほどそういうことか。
それからはもう、毎日が楽しかった。
よく世界の色が変わって見える。などの表現を耳にすることがあるが、正にそれだった。
相変わらず僕は毎日忙しかったが、彼女はすべてのバイトや習い事を辞め、僕との時間を優先してくれた。
僕は居候の為、逢うのはもっぱら彼女の部屋だった。
もっとも彼女も、居候の身で在った訳だが・・・。
朝6:00に仕事が終わるとそのまま彼女の部屋へ向かう日々が続いた。
流石に毎日だと主の彼女にバツが悪いと云う事で、僕は四角い小さな窓から忍び込むように彼女の部屋へ入る事が当たり前となっていた。
一度だけ、巡回中のお巡りさんの目に留まり、就寝中の“ぷり”に事情説明してもらう事態となった。
そんな時、彼女が呟くように言った。
「今のままじゃぁ、駄目ね。あなたとの時間を大切にしたい。もうそんなに時間がないもの。」
僕にもわかってはいたが、考えないようにしていた。
それでも、彼女の口から聞こえてきた現実に僕は動揺していた。
後一か月もすれば3月17日が来る。
そう、彼女の卒業式であると同時に、彼女が故郷の長崎に帰る日だった。
嘘か本当か、彼女は「あなたとこうなる事がわかっていたらあと一年卒業を遅らせた。」と言ってくれた。
その頃には彼女の口から地元NGCにアナウンサーとして就職が決まっていることも聞いていた。
もし仮に彼女が卒業を延ばすと言い出したとしても、僕はそれを受け入れては居なかっただろう。
世間知らずの僕でも、テレビ局への就職がどれ程狭き門なのかと云う事は理解出来た。
彼女もよく冗談として言っていた。
「あなたにもサインを書いて挙げておこうかしら?ごめんなさいねぇ、あなたが第一号では無いけれど、貴重なサインになるかもよ?」
「お前のサイン貰ってどうすんの?煙草のひとつも買えないよ。」
「あなたのそういうところが大好きよ“べー”」
そう言って抱きついてくる彼女が堪らなく愛おしかった。
そんな彼女との関係は、彼女のある決断から一気にその密度を増して行く。
突然彼女は、大宰府にある綺麗なマンションの鍵を僕に差し出した。
「今日から卒業の日まで自由に使える。少し遠くなるけど私はそこに引っ越すわ。私一人だから安心して、“べー”毎日来て。来れるでしょう?これ合鍵渡しておくから。」
突然のこと過ぎて理解に苦しんだが、僕は何も質問しなかった。
只々僕は、4才年上のお姉さんの行動力とその実行力に驚嘆するばかりだった。
今の僕ならばなんの問題も無く用意できるだろうし、その知恵もある。
ただ当時の僕には一月だけ急に部屋を準備するなど、到底考え付かないことだった。
僅かな時間しか残されていないと知りながらも、彼女と二人きり誰の目も気にせず過ごせると云うことが夢のような思いだった。
それからは、彼女に言われるまでもなく、毎日、大宰府のマンションに帰った。
城南店から大宰府のマンションまでは車で30分以上の道のりだったが、その道中も楽しいものだった。
“もう少しすれば、彼女の寝顔が見れる。”
“少し眠りに就こう、隣には彼女がいる。”
“目が覚めたらお昼を食べよう。”
“天気が良ければ、大宰府天満宮に行って梅ケ枝餅を一緒に食べよう。”
毎日が特別な日だった。
テレビとテーブル、そして一組の布団しか無い殺風景なその部屋で、僕は残された時間を彼女と過すんだ。
僕が仕事に出た後、彼女はどのようにして過ごしているのだろう?
福岡を離れるまでに残された短い時間を、僕だけが独占していいものか?
いろんな思いは止めどなく押し寄せてくる、だけど僕はそれを胸に留めることにした。
彼女もきっと、言い表せない不安と闘っているはずだから。
何故なら彼女は度々“後悔してない?私、あなたを信じていいのよね?”と問い掛けてきた。
その目は綺麗で、真っすぐで、とても力強かった。
僕のどこに彼女を不安にさせる行動や仕草があるのか?
自称“モテ男”には分からなかった。
僕の週に一度の休みには必ず二人で外食に行った。
行くのは決まって焼鳥屋だった。
天神や、博多駅、時には福岡大学周辺など、去りゆく福岡の記憶を辿るように、二人で出掛けた。
彼女はお酒が大好きだった。
大好きなだけで強い訳ではなかった。
丁度いい頃合いと云う事を知らず、一度お酒を呑み始めると決まって深酔いした。
この頃、一度だけ言い争いをしたことがあった。
それは、博多駅前にある、市内に10店舗程を数える焼鳥屋でのことだった。
僕はカウンター席が苦手で、店奥にあるテーブル席に腰を下ろした。
「いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。」
「ドンドンドンドン、オーダー頂きましたー。」
太鼓の音が響き渡る元気なお店だった。
「いらっしゃいませー。お飲物どう致しましょう?あっ、どうしたん?」
「おー、なに?ここでバイトなんや?」
福岡大学に通う、僕の地元の同級生に偶然出会った。
其々に生ビールとコーラを、その後、いくつかの串をオーダーした。
彼女は「お友達?」と軽く聞いてきただけだった。
太鼓の鳴り響く騒がしいお店で、僕達は食事を楽しんでいた。
ある程度時間が経った頃、その同級生がテーブルに遣って来た。
「俺そろそろ上がりなんだ。」
「そうなんだ。一緒に食べる?」
「迷惑じゃない?」
「そんなこと無いよ。いいよね?」
僕は彼女に聞いた。
彼女は「もちろん。こんばんわ。」と挨拶をした。
「じゃ、着替えてくるよ。」同級生はそう云って一旦席を外した。
「ごめんね。急に、嫌じゃない?」
そう聞いた僕に彼女は言った。
「嫌じゃないよ。大丈夫。でも初めてで緊張するからあなたうまくフォローしてね。」
「うん。大丈夫だよ。」
そんな話をしているうちに同級生はテーブルに座った。
その時彼女はもう、随分と酔いが回っているようだった。
彼女のパターンは大体決まっていて、急に陽気になったかと思うと、その後は目が据わり、きつそうに項垂れてくる。
そしてそこを越えると、とても甘えてくる。
同級生が来た頃は丁度、目が据わり始めていた頃だった。
彼女は僕達の会話に着いてくる訳でもなく、なんとか相槌を打つ位だった。
あまり彼女を置いてきぼりにする訳にも行かず、なんとなく彼女に話題を振ってみた。
「俺の彼女、めちゃくちゃ綺麗だろ?」
「そうだな。」
同級生の反応は薄い。
元もと落ち着きのある奴で大袈裟な事は言わないタイプだったが、あまりの反応の薄さに僕は食い下がった。
「それだけ?良く見てよ。こんな綺麗な人、俺らの地元で見たことないだろう?」
「うん。・・・・そうだね。」
同級生は困った顔をしていた。
そして彼女はといえば、ほとんど無反応で、真っ赤にむくんだ顔で、目だけは恐ろしく据わっていた。
僕から見ても、まったく可愛くなかった・・・・。
あまりの彼女のグロッキー振りに同級生も気を使ったようで、その後直にお開きとなった。
おそらくはもう記憶も薄ら薄らであろう彼女を車の助手席に乗せる。
「大丈夫?お水買ってこようか?」
「・・・・・・・・。」
「しっかりしろよ。もう車出すよ?」
「・・・・うん。“べー”ごめんね~。折角お友達と一緒に飲んでいたのに・・・。」
「いいよ。呑み過ぎだよ。お前。」
「ごめんね~。大好きだよ~。ねぇ~キスしようよ。ねぇ~”ベー“」
「いい加減にしろよ。こんな誰に見られるかもわからないところでする訳ないだろう。」
「・・・・ごめんね。怒ったの~?」
「怒ってないよ。大体さぁ、お前ちょっと酒飲んだくらいでそんなに甘えて、自分見失って、・・・大丈夫なの?他の男にもそんなことしているんじゃないのか?」
「あのねぇ~・・・・・・そんな分けないじゃない。あなただからだよ。あなただから甘えているのに・・・・・・・・・そんな事も分からないの?」
「どうだかな。信じられないよ、そんなこと。なんなんだよ。同級生の前でみっともない。今日はちっとも可愛くもないし・・・。」
僕がいけなかった。
偶然再会した同級生に彼女を自慢したいだけだったか?
それだけではないだろうが、そう云う気持ちが無かったかと云えば嘘になる。
あと、お酒に酔った時の彼女をいつも心配していた。
僕以外の男にもこんな風に甘えているんじゃないかといつも、いつも心配していた。
僕はいつまで経っても大人になれない、そもそも大人になる気が在るのかさえ解らない。
彼女はなにも悪くない。
そんな、なにも悪くない彼女を、馬鹿にするようなことを言ってしまった。
当然のように彼女は怒った。
「はぁ?そこまで言われる覚えないわよ?友達に自慢できる女性と付き合いたいなら他を当たってよ。」
「はぁじゃ、ねえよ。」
「もういいです。降ります。さようなら。」
「おい、待て、無理だろうそんなに酔った状態で・・。ドア閉めろ。」
「うぅ~。・・・・・・・あぁ・・・。」
そう云って彼女は半開きのドアに寄りかかって、苦しそうにしていた。
僕は車を降りて、助手席側にまわり、彼女を起こしてドアを閉めた。
運転席に戻るまでに笑みが洩れた。
“僕のかわいい年上の彼女はお酒が弱い、心配だけど彼女がそう言うなら信じるしかない”
彼女はそのまま眠ってしまった。
僕は、そんな彼女の寝顔を見ながらどこまでも幸せな気持ちになった。
その後も彼女は色々な自分を僕に見せてくれた。
恐らくはそう、意図的にそうしていた。
言い換えるならば、無理をしていたということだろう。
彼女は一度だけ料理を作ってくれた。
ひと月過すだけの部屋だ。
最低限の調理道具すら揃っていたか定かでは無い。
でも、何を作ってくれたのか?どんな味だったのか?何一つ記憶にない。
また、ある日などは、早めに目覚めてシャワーを浴び終わったばかりの僕の前に、彼女はニコニコして立塞がった。
その日僕は休日で、一緒に大宰府天満宮を散歩した後、天神で食事をする約束をしていた。
「じゃ~ん。」
そう言って彼女は僕に向けてお尻を突き出してきた。
「ん、どうした?」
「・・・どうしたじゃないよ。見てよ、ちゃんと」
「なに?お前のお尻がデカイことくらい知ってるよ。」
「そこじゃないわ。・・・ん、まぁ、そこか?」
「何言ってんだお前?どうした?」
「ショートパンツ、ホットパンツだよ。ほらよく見ろクソガキ。」
「ああ、なんか大きい下着穿いてるかと思ったよ・・・・。」
「ほぉ、私がこんな大きなパンツ穿いていたことあるか?ん?」
「いや、お前、年が年だから、お腹冷えるのかなぁって・・・。」
「・・・・・・・・・お前、おもしろいこと言うじゃないか・・・。」
「そうでしょう?中々的を得ているだろう。」
「そうだね。・・・私今日は一歩も外出しないから。」
そう言ってイジケテしまった。
世話の焼けるお姉さんだ・・・・。
平日の大宰府天満宮は人通りも少なく、ゆっくりと参道までの道程を二人で歩いた。
この時期の大宰府天満宮はなんといっても梅だ。
本殿横にある“御神木の飛梅”はあまりにも有名で、菅原道真公が祀られる太宰府天満宮にあって、その道真公を慕って、遠く京より飛んできたと言伝えられているのが、“御神木の飛梅”だった。
その飛梅を初めとして、6000本もの梅の木が見事にその花を咲かせていた。
その中にあって、鮮やかな濃いピンク色に囲まれた彼女の姿は僕の瞼に焼きついた。
風光明媚なその空間で、鮮やかな栗色の長い髪を風に揺らし、ロングコートの隙間からたまに覗くそのショートパンツは実にミスマッチで、その日から今日まで鮮明にその姿を僕に思い出させる。
“僕はあなたが好きです”
彼女はどんな場所でも手を繋ごうとしてくれた。
人ごみの中だろうと、二人だけの散歩道であろうと・・・。
人前では決して手を繋ぐことのできない僕も、この日は彼女の差し出した柔らかなその手を、優しく握り返した。
彼女は僕の顔を見つめて、僕を馬鹿にするような、そして凄くうれしい気持ちを隠すようなそんなやわらかい笑顔で僕を包んでくれた。
“僕はあなたが大好きです”
その後、天神の人込みを歩いていた時、彼女が呟いた。
「やっぱり、ちょっと恥ずかしい・・・・・・。」
「そんなもん穿いてくるからだよ。」
「だってあなたが喜ぶと思ったし、あなたと同世代の子達はこれくらいの格好当たり前じゃない。」
そう言って、勝手に申し訳なさそうな顔をしていた。
こんな事は沢山あったのだ。
彼女は頑張っていたんだ。
僕はどうであったか?
彼女と釣り合うように背伸びをして、努力したり、その度に悩んだりしていたのかと云えばそうでは無かった。
余計な気回しと言ってしまえばそれまでだろうが、僕なんかよりもずっと、彼女は僕を気に掛けてくれていた。
離れ離れになる日が、もうそこまで迫っていたこの時ですら、まだまだ大人になれない僕は、彼女を気遣うという当たり前の事すら出来ずにいたということだ。
二人きりで毎日一緒にいる時にはその優しさや、心配りには気が付かない。
逆に、お互いの距離が離れたり、気持に隙間が生じた時などは、その気配りの無さや、自らの努力が空回りしているように感じ、その行為自体に蓋をすることになる。
そしてそれは二人の未来を見えなくする。
今だから分かることであって、当時の僕に分かるはずも無い。
3月10日。
彼女と共に過ごせるのもあと一週間となっていた。
3月に入ってからの「ニューヨーク80‘S」は目が回るほどの忙しさだった。
ようやく新たなスタートを切ったばかりの城南店は新人アルバイトが多く、お店のオペレーションは混乱に混乱を来していた。
必然的に僕は、夜は当然ながら、昼も朝も関係なくお店に掛かりっきりとなった。
僅か30分も車を走らせれば彼女の待つ幸せな時間があると云うのに、それは叶わなかった。
そんな事が二日続いた三日目の昼。
彼女が着替えのシャツを持って城南店に来てくれた。
その時僕は、2F厨房で油換えと云われる最もアルバイトが嫌う作業をしていた。
何日も揚げ物を揚げ続けた油は、フライヤーと呼ばれる調理器具の中でおぞましい匂いと熱気を発していた。
電源を切って油を冷まし、空いた缶に油を捨てる。
フライヤーが完全に冷え切ってしまうと、こびり付いた油カスが取れないため、まだ火傷しそうな熱さの中、金たわしで擦り取って綺麗にする。
そして新たな油を流しこむと云う、暇な時間帯にしか出来ない、泣けてくる作業だった。
「“べー”大丈夫?」
「うん。ごめんね。どうしても店抜けられなくてさぁ。」
「気にしなくていいよ。」
「それ着替え?」
「うん。そうだよ。」
「めちゃくちゃうれしい。助かったぁ。」
「みたいだね?それ油換え?懐かしいなぁ。」
「“ぷり”はやったことないでしょう?油換え。」
「うん。無い。無理。絶対無理。」
「だろうね。もうすぐ終わるから、そうしたらなんか食べ行こうよ?」
「うん。あっそうだ。“べー”何か作ってよ?」
「えっ、良いよ。そんなんでいいの?黒田屋行かないの?」
「うん。あなたが作ったもの食べたい。」
「よし、わかった。」
それから僕は簡単にできる“チャーハン”を作った。
当然ながら美味しい冷凍食品は沢山揃っていたけど、冷飯と卵、それから焼き豚やネギなどを使って一から作った。
彼女は美味しそうにと云うよりも、嬉しそうに食べてくれた。
“チャーハン”を食べ終わると彼女は直ぐに帰ると言った。
「少し時間無いの?」
僕の問いかけに彼女は、
「仕事中でしょう?」
と答えた。
「大丈夫だよ。一時間くらい・・。」
「駄目だよ。案外どこで見られているかわからないものよ?いいの?店長がさぼったりして。」
「平気だよ。俺20時間以上労働だよ?誰も文句言わないよ。」
「それもそうだね。良かった、このまま帰るのは、寂しかったから。」
そう言って彼女は舌を出した。
“ほんとうに、ほんとうにあなたが好きです。”
空室の中でも3Fフロントから一番遠い8F 805号室に彼女と入った。
電源を入れていない客室はひんやりとして薄暗い。
僕は電源を入れようとしたのだが、彼女に制止されて止めた。
並んでソファーに腰掛けると直ぐに、彼女が抱きついてきた。
「寂しかったよ。“べー”」
「ごめんな。」
「許さない。私のこと放ったらかしにして、もう4日しかないんだよ・・・。」
「そうだよな。本当にごめん。」
「そうだよ。後悔するよ。」
「・・・・・うん。」
「・・・・・・・・・・。」
「“ぷり”?どうした?大丈夫?」
「私・・・・・後悔してる、今。」
「どうした?俺と付き合ったこと?俺が放ったらかしにしたから?」
「・・・・・・・・・。」
「言ってくれよ。なんでだよ。」
「・・・・・・・・あなたに抱きついたこと。・・・・油臭い・・・。」
「・・・・・・・・・・離れたら?」
彼女はキスをしてくれた。
僕等は、幸せだった。
そしてそこで僕らに残された時間は実質2日しか無いことを知った。
3月17日前日、彼女の母親が福岡に来ると云う。
天神のホテルを予約しているらしく、彼女もそこに宿泊するとのことだった。
そしてそのホテルから着付け予約してあるところへ向かうらしい。
そのことを聞かされた時、彼女と一緒に卒業式で着る袴を見に行ったことを思い出した。
淡いさくら色と濃紫の袴を着た彼女は凛として美しく、それと同時に訪れるさよならを感じることは無かった。
だが、今は違う。
彼女が袴に袖を通す時、それは彼女が僕の前から居なくなると云う事実が、僕を追い詰める。
いくら考えても動かしようのない、その現実に僕は震えていた。
残りの一日はなんてことはない、僕の力でも揉み消すことは出来た。
が、揉み消しはしなかった。
彼女が故郷に帰る前に、一度だけ天神の街を一緒に歩いてみたいと言う新人君と、最後に二人きりで“おねえちゃん”と呑みたいと言う“えっちゃん”の為の一日だった。
二人には僕らもお世話に成りっ放しだ。
ここは大人になることにした。
そうなると彼女とゆっくり居られるのは今日と、明後日しかない。
僕は、彼女が持って来てくれたシャツを隠して、今着ているシャツに油をビッシリと付けた。
「ちょっと着替えに帰る。」
そう言い残して僕は彼女と城南店を後にした。
その日はもう何があってもお店に戻るつもりは無かった。
会社から支給されている携帯電話は何度も鳴り続けたが、僕は無視を決め込んだ。
その日着替えを終えた僕等は、博多区にあるホテルに宿泊することにした。
20才そこそこの僕には、その時に出来る最高の贅沢をしたつもりだ。
恐らくはこれが二人の福岡での最後のイベントとしての思い出になる。
二人ともにそう理解していた。
ドレスアップした彼女はとても綺麗で、そして誰よりも綺麗で、同施設内のレストランで向き合った時になって、自然と涙が溢れてきた。
それはすぐに止まる涙で、それ以上彼女に心配を掛けることは無かった。
高級そうなシャンデリアと、繊細な彫刻の施された店内、そしてそこで食事をする人たちの空気は、普段の僕を圧倒したことだろう。
でも、不思議とその日は、そのような周囲を意識することは無かった。
目の前にいる誰よりも素敵なその人との大切な時間。
僕は、己の場違いなど気にしている暇はなかった。
その時の味も、メニュ-も憶えてはいないが、コース料理の終盤になって彼女は大きな瞳をこちらに向けたまま、右の瞼を指差した。
そして片方の目をゆっくりと閉じたんだ。
僕は小さく二回頷いた。
彼女のその青いアイシャドーは、いつまでも僕の心を掴んで離れることは無い。
その夜の甘い記憶は、現在までも色褪せることなく僕を当時に引き戻す。
翌日チェックアウトを澄ました僕等は天神へと向かった。
指定されていた西通りの“ドーナツ屋”の前には、緊張からか、寒さからか、引き攣った面持で震える新人君が居た。
「うちの“ぷり”を宜しく。」
そう言い残して僕は、バックミラーに二人を見ながら仕事へと向かった。
その夜、新人君の興奮は治まることを知らなかった。
「店長、楽しかったです~。」
「なんだそのテンションは?まぁ楽しかったなら良かったよ。」
「いや、みんな振り返るんですよ、すれ違う人が。」
「それは無い。大袈裟だな。俺は一度も経験無いよ。」
「ほんとですって。半日天神を歩いて“辻山さん”より綺麗な人いなかったですよ。」
「そうか、そうか、で、何処行ったの?」
「CDと洋服選んでもらって、お茶して帰ってきました。」
「ん?で、あいつ今どうしてんの?」
「途中で、“えっちゃん”と合流してそのままです。」
僕は新人君のうれしそうな顔を見て、今日と云う日を我慢したことが正しい事だったと思うと同時に妙に誇らしい気持ちになった。
新人君には贔屓点がかなり加点されているだろうけれど、天神を歩いて彼女より綺麗な人は居なかったなどと言われるとうれしくない訳がなかった。
ただ、そのうれしさとは裏腹に、迫りくるその時に向けて、依然として気持の整理はつかないままだった。
その夜、彼女は城南店に顔を出した。
夜中2時は回っていただろうか、“えっちゃん”に引きずられる様にして彼女は現れた。
「店長、待合室借ります。」
そう言って“えっちゃん”は彼女を待合室に連れて行ってくれた。
少し時間を空けて彼女たちの様子を見に行った。
“ぷり”はもう完全にグロッキーだった。
「またか?悪いな。」
「いえいえ、少し呑ませ過ぎました。すいません。」
「けど、お前は未成年のくせに酒が強いな?」
「鍛え方が違いますから、店長とは。」
「・・・・・・俺は一滴も飲めないよ、俺と比べるなよ。」
「ダサいっすねぇ。相変わらず。」
「・・・・・・・・・お前、今から働いて行かせるぞ・・・・・・」
「いや、マジで無理です。帰ります。」
「なんだよ。置いて行くのか?」
「店長がいるからいいでしょう?お店が忙しいなら私働きますから、“おねえちゃん”の横に居て挙げてくださいよ。」
「いや、もうお店も落ち着いているし大丈夫だよ。俺が看ているよ。」
「じゃぁ、帰ります。」
そう言って立ち上がった“えっちゃん”に僕は思いがけず声を掛けた。
「いろいろ・・・話出来たか?」
「そう・・・・で・・・・・すね。」
彼女は泣いていた。
「どうしたお前。寂しいのか?」
「そりゃぁ、寂しいですよ。だってもう会えないですよ。また会おうね、なんて言ったところで、中々逢えないことくらい私でもわかりますから・・・・。店長もそうですよ?何時でも逢えると思っていたら後悔するかも知れませんよ・・・・。」
「そうだよなぁ・・・。」
そう呟いて、“えっちゃん”の頭に“ポンポン”とやさしく触れた。
彼女はそのまま僕の腕を掴んで泣いていた。
暫く泣いて、そして僕のスーツの肩付近に鼻水を塗りつけ、「あーッ、スッキリした。」
「店長―。お願いしますよー。」と大きな声で意味不明な言葉を残して帰って行った。
残された僕は“ぷり”の寝顔を確認した後、厨房におしぼりを取りに行った。
“えっちゃん”最後の言葉の意味が、何となく分かりそうになったが、結局分からなかった。
それとは別に、年下相手だと俺も立派な大人だという結論に至っていた。
“えっちゃん”や新人君とは二つ違うだけだ。
“4才年上のお姉さんからは、僕のことはどう見えているのだろう?”結局それも、僕に残された宿題となった。
思い出の待合室。
もしも二人が別れて、どこか思い出の場所で再会を果たすなら・・・・・そんなドラマのワンシーンのようなことが僕らにも訪れるのだとしたら、それはきっと、この待合室だろう。
彼女の寝顔を見ながら、今までこの待合室で交わした、今隣でいびきをかいている女性との数々の言葉が溢れるだけ溢れて消えることは無い。
この、僕の大好きな人と、あと一日しか一緒に入れないことを考えると、どうしても涙が止まらなかった。
「どうしたの?何泣いてるの?」とやさしく抱きしめてくれる筈の彼女は、けたたましいいびきの中にあって僕の感傷を破壊する。
それでも尚止まらない涙はどうしたものか、この時ばかりは彼女が寝ていてくれて助かった。
そしてそのまま朝を迎え、最後の日となる大宰府の部屋へ二人で帰った。
道中、彼女のいびきは依然として激しかった・・・。
その日僕は仕事を休んだ。
彼女の提案で、その日はどこにも出掛けず、ゆっくりと部屋で過ごすことになった。
そしてたった一つのルールを言い渡された。
“絶対に暗い話はしない”それだけだった。
その夜は電気も点けず、一組の薄い布団に二人で包まって、昇る朝日を見たんだ。
翌日の昼、彼女は天神へ向かった。
「明日、来てくれるでしょう?」
「勿論行くよ。」
「お母さんにも紹介するからね?大丈夫?」
「ああ。大丈夫だよ。」
「それじゃ、行くね。明日ね。」
「おう、明日な。」
その日僕は仕事に出た。
そして翌日の朝、彼女が卒業する福岡大学へと車を走らせた。
その日は何故かこころは穏やかだった。
途中、予想を超える車と人の多さに多少苛立ちもあったが、彼女が旅立つこととは関係ないであろう。
3月であることを忘れさせてくれるような陽気と、青い海が似合う彼女を祝福するかのような青天に恵まれたこの日、それでも僅かに感じる寒風を受けて門へと向かう。
昨日の内に予約しておいた、大きすぎるかも知れない花束を持って。
不思議なもので彼女とのお別れよりも、彼女のお母さんと対面する緊張の方に意識が向く。
僕はやっぱり子供だ。
約束の場所へ近づくと同時に、心臓が飛び出すのではと思えるほどの動悸と緊張が襲ってきた。
暫く辺りを見渡す。
彼女は見つからない。
もう一度彼女を探す。
いない。
不意に気になり、校内のガラス戸に映る自分の身なりを整えて、また辺りを見渡したその時、彼女を見つけた。
燦々と舞い落ちるさくらの中に、淡いさくら色と濃紫の袴姿の彼女を見た。
彼女に会うまでは気が付かなかった。
辺りは、綺麗に咲き乱れるさくらに囲まれていた。
1歩彼女に近づく度に、その光景が現実のものとは思えないような錯覚に、僕は倒れそうになる。
そこに佇む僕の彼女は、驚くほど綺麗で、泣けるほど素敵で、20才の僕の感情は一気に壊れそうになった。
そんな僕を悟ってか、僕の代わりに彼女が泣いてくれた。
彼女は僕の両手をしっかりと握って言ったんだ。
「大丈夫だよね、私達は。あなた別れようなんて思ってないわよね?あなたの事、信じていいのよね?私あなたを信じたい・・・。」
涙でボロボロになりながら、いつもの大きくて、綺麗な、力強い眼差しを僕にくれた。
「当たり前だ。お前、がんばれよ。」
僕はそれしか言えなかった。
“卒業おめでとう。”その言葉すら言えなかった。
その後、彼女と彼女のお母さんを博多駅まで送った。
移動の車中では、彼女とも、彼女のお母さんとも殆ど言葉を交わすことは無かった。
そして、いよいよお別れのときがやって来た。
彼女は僕をやさしく抱き寄せてくれた。
久しぶりに感じるあの香り。
彼女と出会った、そして彼女を好きになったあの時の香りに、僕はもう壊れるしか無かった。
車に戻って、彼女の後姿を見送った。
ハンドルが壊れるのではないかと云うくらい“ガン、ガン、ガン、ガコンッ”いつまでも殴り続けた。
とまらぬ涙は、どこに向けてのものだったのだろう。
大好きな“ぷり”との福岡での生活が終わった。
3
彼女の居ない日々が始まった。
僕は今までの日常に戻った。
暫くは寂しさもあったが、不思議なもので彼女が傍に居ないことが当たり前となるまでに一週間と掛からなかった。
地元に帰った彼女とは毎日電話で話をした。
実家に戻った彼女は、当面の間、一人暮らしは考えていないと言っていた。
そんな彼女は自身の部屋に専用の電話を引いてくれた。
「あなただけにしか番号教えてないから。電話が鳴ったら全てあなた。これで毎日気兼ねなく話せるね。」
そう言って笑っていた。
「はやくあなたに会いたいよ。“べー”。」
「地元に帰った早々、何言ってんだよ。」
「何って、当たり前のことじゃない?あなたは会いたくないの?」
「そりゃぁ、会いたいさ。」
「いつ逢いに来てくれる?」
「近いうちに行くよ。今忙しいんだ、ちょっとまた掛けるよ。」
「なんでよ。もう少し話しようよ。」
「わるい。またな。」
夜電話することが多かった僕は、フロント前の公衆電話を使用していた。
会社の電話を使う訳にはいかなかったし、当時、携帯電話からの通話料金は驚くほど高かった。
その内、アルバイト達の間で僕の行動は密かに噂となっていたようだ。
ある時、2F厨房でアルバイト達がなにやら盛り上がっていた。
「お前たち暇そうだなぁ、気も滅入るような仕事でも与えてやろうか?」
そう言いながら僕は彼等の輪に入った。
そこで、一人のアルバイトが僕にこう言ってきた。
「店長の彼女さん、どんな人なんですか?」
「なんでお前に言わなきゃいけないんだよ?」
「いや、店長の彼女だったら、きっとすごい人なんだろうなって話してたんです。」
「なんで俺の彼女だったらすごい人なんだよ?」
「・・・・・・・・・・・・・いや、違うんですよ。俺店長尊敬してますから。」
「言葉に詰まり過ぎだよ。・・・・・・お前に尊敬される覚えは無いよ。」
「・・・・・・いや、みんな言ってますよ。」
「みんなって誰だよ。お前含めて二、三人ってとこか?」
「もう、苛めないでくださいよ~。本当にみんな尊敬出来る店長だって言ってますよ。」
「・・・・・・・・・で?」
「いや、店長本当に若いのにすごいですよ。だって店長俺より二つ下ですよ?見えませんもん、とても。落ち着いているし、・・・。」
「お前、完全に俺のこと馬鹿にしてるだろう?」
「してませんよ~。俺本当に店長について行きますから。」
「着いてこなくていいよ。迷惑だよ。」
「お願いしますよ~店長。」
僕は、知らず、知らずデビルから多くを学んでいた。
彼ほどの恐怖政権は布けなかったが、当たり前の秩序のある、とても調和のとれた僕のお城だった。
その後、尚も食い下がるアルバイト達に根負けして、元アルバイトが彼女だと告げた。
“ぷり”を知らないアルバイト達は僕をおおいにからかった。
「うえーっ。何かがっかりやん。店長のことやけん、もっとすごい人と付き合いようかと思いよったぁ。元アルバイトとか身近過ぎやん、うえっー。」
そんな時厨房は、以前のような「辻山さん」談義が開かれるようなことはもう、無い。
それでも今では頼りになるリーダーとなった“えっちゃん”が彼女の素晴らしさを得々と彼等に説いてくれた。
そんな彼等を見ながら、自分自身の仕事にようやく、喜びと充実感を得るようになっていた。
そんなある時、フロントのスタッフからアナウンスが入った。
「店長、お知り合いの方がみえています。」
フロントに向かうと、高校時代の女友達が二人遊びに来ていた。
彼女達を自ら客室に案内して、そのまま彼女たちと一緒にカラオケに興じる事になった。
一通り歌い終えたところで、思い出話やこれからのことについて語り合った。
「すごいね。本当に店長してるんだ?」
「うん。見ての通り。」
「いや、なんかさぁ、店長してるって云うのは聞いていたんだけどね、まさか“ニューヨーク”とはね。もっと小さな5部屋位のカラオケボックスかと思っていたよ。」
「5部屋でも、ここでも一緒だろう?する事は変わらないよ。」
「いやいや、全然違うでしょう?だってここスタッフ何人いるのよ?」
「30人位じゃない?」
「でしょう。・・・すごいじゃない。いきなり30人のトップでしょう?」
「凄くないって・・・。アルバイトばっかりだもん。」
「いや、すごいよ。私考えられない。無理だよ。そんな人数操縦するのは・・・」
「操縦ってなんだよ・・・。」
「私、高校卒業してほら、小倉の“ベスタ電気”に就職したでしょう?二年働いて後輩二人、役職なんて当然無いし、部下なんて一人もいないよ。しかもうちのお店全体で35人くらいだし、その中にもパートアルバイトさんも結構居るのよ。そう考えたら本当にすごいと思うよ。大出世だね。」
「そんなこと無いって・・・。」
そう返答しながらも僕は、悦に入って居たのかも知れない。
でも、そんな考えは一瞬で砕かれた。
それはもう一人の女友達の言葉から始まった。
「で、将来どうするの?」
実にシンプルながら、その言葉は僕を動揺させた。
「どうってなにが?」
「なにがってことは無いけど大事なことじゃない?将来の目標とか、人生設計とか?」
福岡女学院短大を卒業して福岡市の信用金庫に就職した彼女の言う事は一々正しい。
「今すぐにはどうとか考えてないよ。現状でも精一杯だし・・・。」
半年前まで学生で、何も考えず中退した。
そしてなんとかこの店に拾われ、漸く仕事を覚えて、やっとのことで店長として認められるようになったばかりだ。
ついこの間までは深い闇に沈んでいた僕の心から出た本心だった。
「でも、一生続けられる仕事では無い気がする。結婚して子供が出来て、それで夜働くと云うのはどうかなぁ?」
「そんな先のことまで考えて働いている人ってどれくらい居るの?私たちの勤務では無いけど、JRにしても夜間勤務はあるし、CAさんだってそれこそ日付跨いじゃったら昼も夜も無いよ。それだけじゃないよ、うちの店長なんて、もう7年も単身赴任らしいよ。それが本当なら家族ってなに?って感じだよね。」
「それもそうね。」
「そうだよ、しかも“ニューヨーク”ってどんどん事業拡大してるじゃん。店舗も増えてるし、飲食も展開してる、今後が楽しみなんじゃない?」
“ベスタ電気”の女友達の発言でほんの少し落ち着くことが出来た。
「相変わらず、お前は堅いね。」
そう言ったものの、僕は社会の恐ろしさを感じていた。
どれほどの苦難を乗り越えて上った山も、それは自身の勝手な評価で在って必ずしも他人の目線が同じでは無いという現実。
「私そう云う所あるからね。でもそうだよね、店長って云っても大きな会社組織な訳だし、その上の役職もあるよね?更にはノウハウを吸収して独立って考えもあるもんね。その時は是非当行をご利用ください。」
そう言って彼女は笑っていた。
「お前、すごいな。お前の彼氏になる奴は大変だな。」
「そうね。まぁ、ずっと居ないけどね。」
みんなで笑い合った。
でも、僕は笑っていられる心境では無かった。
彼女の指摘がどれほど正しいのかは分からない。
ただ、店長なんていつまでもやっていられる仕事では無い気がした。
そして、世間の評価は僕の思っているものとはズレがあるのだとなんとなく理解した。
今僕が、彼女の言う様に志高く、独立をするつもりだと胸を張れるならまだしも、現状の小さな世界で満足している馬鹿な自分が情けなくて成らなかった。
しかもそれは“ぷり”の一件で既に気が付いていた筈なのに。
自分が居る世界は小さな、小さな世界であることに苦しんだあの時を、もう僕は忘れてしまっていた。
彼女達に出会わなければ、僕は今まで通りの僕のままで、大切な“ぷり”をがっかりさせてしまうことになっていただろうから。
僕がひと月前と変わらぬ日常に戻ったのとは対照的に、新たな春は彼女の想像を遙かに超えていた。
4月に入り、本当の意味での彼女の新生活はスタートした。
入社間もなく始まった研修は、想像を超えるハードなものだったようだ。
疲れているであろう彼女を気遣って、一日でも電話を掛けない日があると彼女は怒った。
「昨日はどうして連絡くれなかったの?」
「ごめん。バタバタしていて気が付くと23時回っていたから。」
「回っていたから?なに?」
「いや、寝てるかなと思ったから。」
「どんなに遅くても電話鳴らしてよ。」
「わかったよ。」
「・・・ねぇ、なんだか面倒だと思ってない?」
「全然そんなこと無いよ。どうした?」
「そんな気がしたから・・・。私、今あなたと話すことだけが楽しみなんだからね。」
「今はそんな事言ってないでしっかりと研修頑張れよ。」
「言われなくても遣ってるわよ。」
「どうした?そんなに怒る事無いだろう?」
「だって、随分上から言ってくるから・・・。」
「そりゃぁ、社会人としては先輩だからな。」
「なに?馬鹿にしてる?そんなことあなたに言われたくない。もういい。」
そう言って電話は切れた。
以前ならば、相変わらずの憎まれ口にお姉さんのゆとりを見せていた彼女、慌てて電話を切る僕の心裏を理解出来ていた彼女。
その姿はそこには無かった。
それでも、3月17日彼女が言った言葉が僕に自信を与えてくれている。
“俺達は深い絆で結ばれている”その思いは揺らぐことは無かった。
“トゥルルルルル・・・・・・・・”
21時過ぎ。
“トゥルルルルルトゥルル・・・・・・・・”
明くる日22時過ぎ。
“トゥルルルルルトゥルルトゥルルルル・・ガチャッ・・・・・・”
そのまた明くる日22時過ぎ。
「はい、もしもし・・・・。」
「もしもし、俺。今大丈夫?」
「うん。」
「昨日も、その前も連絡したよ?」
「ああ、ごめんね。疲れて寝ていたのと、歓迎会・・・・・。」
「歓迎会お前大丈夫だったか?悪酔いして醜態曝さらすことはなかったか?」
「そんなわけないでしょう。」
「・・・・・・・・・・・・・どうした?大丈夫か?」
「何が?・・・・・・・・・。」
「いや、何がって・・・・・別人みたいだから・・・・・・・。」
「ごめん。疲れてるの、切るね。」
そう言い終わらぬくらいで電話は切れた。
僕は少しだけ不安になった。
この頃は会話が続かない。
そして、僕は、彼女の研修が終わる日まで、電話することを辞めた。
“トゥルルルルル・ガチャッ・・・・・・・”
22時過ぎ。
「はい・・・・。」
「俺。研修昨日で終わりだろう?お疲れ様。」
「ああ、最初の研修が終わっただけ。明後日から次の研修だよ。」
「そうか・・・。大変だな。大丈夫か?」
「・・・・・・わかんない。」
「・・・・・・・・・・・・うん。」
「私、だいぶ舐めてた。社会人になるってこと。」
彼女は泣いているようだった。
「そうか、でもみんな大変だと思うよ。俺だって辛かったし、」
僕はまだ話の途中であったが、彼女はそれを許さなかった。
「ふっ、一緒にしないでくれる?あなたと。何万、いや何十万人の前に出るってことがどんなことか想像できる?」
「出来ないな。・・・まぁ、俺に八つ当たりしてどうにかなるならお好きにどうぞ・・。」
「なんなのそれ?あなたは立派な社会人?受け止める事も出来ないの?」
「今はなにを話しても一緒だな。また掛けるよ。」
そう言って今度は僕から電話を切った。
彼女から先に切られると腹が立つ、理由はそれだけだった。
彼女を支えられないばかりか、この日はこれでも我慢したほうだと僕は、思っていた。
社会に出る厳しさは想像しているよりもずっときつい。
それぞれに圧し掛かる責任はそれまでに感じた事の無い重圧に違いない。
こんな小さな世界でも心が壊れそうになったくらいだ。
彼女の重圧は僕のそれとは比べものにならないであろう。
若いうちは、失敗が許されない事だと勘違いしてしまう。
しかし、誰でも必ず失敗する。
失敗してもいいのだと云う事を知る術は、失敗するしかない。
僕は、一人の女性を犠牲にした?
それが取り返しの利く失敗だったかどうか・・・。
そして今は、彼女の心の支えには成れなかったというだけの事だと思っていた。
春が終わろうとしていた。
春か夏かわからない頃、彼女に電話をした。
話をするのはいつぶりだろうか。
集中的な研修に区切りが付き、一定の安堵感と、希望ある未来と自信を、会社から植え付けられたのであろう彼女は、とても元気だった。
「もしもし、“べー”どう調子は?」
「ああ、俺は至って普通だよ。なんだか元気そうで安心したよ。」
「やっと解放されたのよ。秋くらいには私アナウンサーデビューよ。」
「おおー。すごいなぁ。さすが“ぷり”だね。」
「私、頑張るよ~。あっ、そうだあなたBMWどう思う?」
「BM?車か?かっこいいよな。」
「だよね。」
「なんで?どうしたの?」
「いや、社割で安く買えるのよ。どうかな?」
「いや、わかんない。新入社員が生意気なんじゃぁないの?」
「それがそうでもないのよ。周りの社員たちもお金持ちの選ばれた人たちが多くて外車なんてザラなのよ。」
「へー、そうなんだ・・・。」
「あっ、後、街中とかは堂々と歩けなくなるかもだけど、ごめんね。」
「・・・・・・・・まぁ、それはその時考えようか?」
「その時じゃあ、遅いのよ。あとあなたにもキチンとした格好をして欲しいわ。」
「キチンとしてないかなぁ?俺・・・。」
「う~ん。どうかしら?今まで通りでは駄目かもね。」
「・・・・・・・・誰かの目を気にして、自分を変えるってこと?」
「ふっ、先が見えてないのね。まあいいわ。またね。」
電話を切った僕は、複雑な感情を抱いた。
今までの彼女には無い不思議な感覚を覚えていた。
少女のように温もりを求めていたひとは、徐々にやり場のない怒りを露にした。
そうかと思えば、無気力にその体を宙に放る・・・。
抑え込めない感情は涙となってそのひとを潤し、その後には大いなる希望が訪れた。
そんな不安定に思えるそのひとの事が気になっていた。
ただ、たくさんの違和感ある彼女の言葉を、正す気には成れなかった。
人生は選択だ。
大人になるに従って自分の可能性を否定することから始まる道は、その時々の要因で勘違いさせ、見失い、最後には自分が特別な存在では無いと気付かされる。
そのことを僕が本当に理解出来るようになったのは、これよりずっと先のことだ。
僕の小さな世界だけで考えてみても、その繰り返しだった。
女友達から気付かされたあの日から、同級生と自分の給与を比べた時の優越感、夜働く事への偏見をダイレクトに伝えられた時の劣等感、同世代の人との仕事に於ける自由度と裁量権の違いを感じた時の高揚感。
まだある。
尊敬していますと言った大学生達が就職してから再会したときの態度の変化に感じた違和感や、それまで以上の尊敬の念を頂いた時の幸福感、小さな箱の中に閉じ込められているような閉塞感や、自らの店舗から店長を輩出して複数の店舗のエリア責任者となった時の充実感。
様々な場面においてそれらは繰り返し僕に問い掛けてきた。
きっと彼女も同じ筈だ。
元々彼女から連絡が来る事は少なかった。
近頃では僕から彼女へ連絡することも減ってきている。
上昇教育を叩き込まれた、今の彼女をどこか敬遠するようになっていた。
但しそれは、僕が何度も繰り返していたように、彼女の中でも起きている変化だと思っていた。
彼女への愛が移ろいでいたわけではない。
不毛な衝突を避けようとする考えから来た、大人としての僕の判断だった。
「もしもし、久し振り。どお?最近は?」
「うん。相変わらず。ただ会社の戦力になれていない自分が歯痒いよ。」
「“ぷり”っぽいな。」
「あなたはどうなの?」
「別に普通かな。そう云えば、うちに新しいアルバイトが入ってさぁ、その子が食えないプロボウラーなんだよ。だから昨日は仕事さぼって何人か連れてボウリング行ったよ。
久しぶりだったから全然スコア出なかったよ。」
彼女は何の興味も示さないばかりか、僕の他愛も無い世間話に嫌悪感を滲ませた。
「ねぇ、そんなことでいいの?」
「なにが?サボった事言ってるの?それも大事なコミュニケーションなんだけどな。」
「あなたが良いならいいけど・・・・。」
「なに苛々してるんだよ?“ぷり”」
「・・・・ごめん、その“ぷり”って辞めない?」
「・・・・・・・・・・なんで?」
「私たち、もう子供じゃないんだから。」
「出会った時から俺達は子供じゃないよ。それが就職した途端にそれかよ?」
「ああ、もういい。あなたには伝わらないみたい。」
彼女はいきなり受話器を置いた。
この時ばかりは僕も動揺した。
彼女への怒りは勿論のこと、“ぷり”“べー”と呼び合う事を辞めようと言ってきた彼女に驚いた。
別にその愛称に浮かれるほど子供では無い。
そうでは無いが、そう呼び合えること、それが二人の関係性の指標になって来た事は疑いようのない事実だった。
それから暫くの間、僕しか知らない筈の二人だけの電話に、彼女が出ることは無かった。
僕は、彼女の異変に気付いていた。
僕は、自分が取り残されることに怯えていただけなのかも知れない。
ある日の土曜日。
午前11:00頃。
僕は車の中、携帯電話を手に取り、彼女へと電話をした。
「ゆっくり話がしたいんだ。今大丈夫かな?」
「ごめんなさい。あまり時間が無いの。」
「大事な話だよ。少しくらいいいだろう?」
「約束があるから・・・・。」
「俺のこと避けているのかお前?この電話がどれほど大事なものかわかるだろう?」
「・・・・・・・・・。」
「・・・・・・・・・・・・・。」
「はぁ・・・・。」
彼女の大きな、わざとらしい溜息が聞こえてきた。
「はっきり言っていいのね。」
「・・・・・・・・・。」
「あなた、わからない?私と話をしていて・・・・。」
「わかるよ。わかっているから電話したんだよ。ただ、お互い忙しくて、お前が長崎に戻ってから一度も会えてないし、俺も自分の時間を優先していたところがあったから、・・・・その部分は悪いと思っているから。」
「いいのよ。反省なんてしなくて・・・・・・・もう。」
僕は怖くてどうしようも無くなった。
このまま二人は終わってしまうとわかったから。
「良くないだろ。今から行くから・・・・。」
「・・・・・・・。来なくていいわ。」
「いや、行くよ。」
「来ても会わないわよ?迷惑なの。あのね、あなたを苦しめたくないから今まで言わなかったの。あなたまだ若いし、早々にそっちで新しい人と上手くやっているんじゃないかと思って、」
「そんな訳ないだろう。」
僕は大声を出していた。
「そんなに興奮しないで。大人でしょう?落ち着いてよ。」
「・・・・・・・。」
「私、自分が子供だったんだって、気が付いたの。正直言うと、会社に入社して直ぐにあなたに対する感情は変化していた。私の世界で働く男の人はほんとに素敵で、輝いていて、驚くほどスマートな大人で・・・・。じゃないと私あなたと付き合ってないと思うの。」
「どうしたんだよ、お前?言いたい放題じゃないか。どうせ今だけだろう?」
「私ね、あなたに全く興味が無いの。わかって貰えない?」
「俺が夜働いているから?カラオケ屋の店長とか云う小さな世界で満足している男だから?」
「わからない・・・。考えた事も無い。唯、興味が無いの。」
「待ってくれよ。突然そんな事言われても・・・。」
「突然じゃないって何度言わせるの?それに別れ際にそんな感情乱して・・・・本当に子供ね。」
「もっと俺が大人になればいいのか?俺が立派な社長にでもなればお前は考え直してくれるのか?」
「・・・・・・・・・。」
「成るよ。俺、大人に、立派な社長になるよ。だから・・・お願いだから・・・。」
「そういう自分本位の考え方も受け入れられない。」
「・・・・・・・・・・。」
「・・・・・・・・・・・・もう、いいかしら?」
「これで、この電話で終わりってことか?」
「・・・・・・どんな終わり方でも同じよ。もう終わっているんだから、私の中では。」
「お前の気持ちが落ち着いた頃、必ず行く。高速降りたら電話するから必ず出てくれ。」
「・・・ガシャン・・ッッ-ッ-」
あまりに突然の別れに頭がおかしくなりそうだった。
3月17日の彼女の言葉は・・・・僕だけの記憶になった。
今まで二人が話した、過ごした思い出も僕だけのものだろう。
二人で描いた未来は存在しない。
彼女の為に犠牲にしてきた人たちへの想いは僕が大人になる為に必要な傷か。
もう、どうやって車を運転したのかさえ思い出せない。
「社長、博多地所の近藤さんからお電話です。」
「お電話変わりました、ああその件ですね。はい、承知しております。明日の夜でもゆっくりお話ししましょう。西中洲の“ひいらぎ”押さえておきます。ええ、ええ、わかりました。では明日19:00に・・・。」
「藤波さん、明日19:00“ひいらぎ”個室4名で予約入れといて。」
「わかりました。予約名はどうされますか?」
「原田でいいよ。」
あれからどれ程の月日が流れただろう。
例え話にあった“社長”に僕は成った。
自らが想像も付かなかった高級外車に幾つも乗った。
ただ、いつかの時に彼女が言っていた“ぼくちゃん”と呼んでくれる人は傍にはいない。
ある日のこと、いつもと同じく部屋に入ると倒れ込むように眠りについた。
途中酷く喉の渇きを覚えて目を開いた。
真っ白な天井を見ていた。
実際には、背の高いマンションに挟まれたこの部屋にあって、今が何時位かという外の情報は少なく、カーテンを閉め切った部屋の天井は黒色に近い灰色に見えるに違いなかった。
“この部屋の天井は白い”ということを知っている脳が、僕の眼に、僕の心に、その情報を伝えているのだろう。
その時見ていた天井は確かに白だった。
過去の自分が知っている情報を基にして、現実と異なる姿を僕に見せてくれる便利な脳があるというなら、お願いしたい事はひとつだけだ。
酷く乾いた喉を潤すことも忘れて、天井を見ていた。
思考停止した無の世界で、その白は遠く離れ、ある時は、目前に迫りくる。
どれくらい時間が経っただろう。
思考を開始した僕はゆっくりと目を閉じた。
真っ暗な世界は逆に騒がしく、思い描きたい未来も、塗り替えたい過去も浮かんでは来てくれない。
なにも見えないその白のキャンバスを前に、僕は何色の絵具を手に取ればいいのだろう。
陽気な目覚まし時計の音に殺意を覚える。
先程目を閉じたまま、眠りに落ちていた。
この頃では、泣きながら眠る事は珍しいことではなくなった。
僕は今日、泣きながら目覚めていた。
今が何時で、此処が何処なのかはわかった、つもりだった。
水色の空に逞しく伸びる入道雲、空との境目を判断するには困難なほど同じ水色をした海。
どこまでも、どこまでも続くその遠浅の浜辺。
真っ白な砂浜に目を向けるとそこにはポツンと置き去りにされた一人の赤子がいた。
「おかしいなぁ、こんな所に赤ちゃんを置き去りにするなんて・・・・。」
周りを見渡しても、それらしい人影は見当たらない。
どうしようもない不安に駆られ、その赤ちゃんに近づいたその時、彼女が現れた。
その瞬間僕は全身が震えた。
音の無い号泣を続けた。
そして、唯唯うれしかった。
彼女はその赤子を拾い上げ、こう囁いた。
「すぐに見つけることが出来たよ。不思議ね、この世界はどこまでも広いって云うのに。」
そのまま彼女と赤子は僕の前から姿を消した。
二度と逢えない筈だったその人を前に、涙するばかりの僕はその人を追いかけることはしなかった。
なぜ?
心地良かったから。
ずっと、ずっと、ずっと僕は心から幸せだったから。
彼女の温もりを感じていたから。
晴れ渡った空に激しい雷が舞う。
そして、突然の暗闇が僕を包む。
慌てて駆け込んだ先の窓越しに見えたその光景に、僕は言葉を失った。
彼女が泣いていた。
現実には未だ見ぬ彼女だろうが僕にはわかった。
あんな彼女を見たのは初めてだった・・・・・・・。
白のキャンバスに描けなかった未来は、不思議な夢を僕に見せた。
夢の中でも僕達は、同じ未来を共有することは出来なかった。
現実の世界と違っていたのは、その原因が僕らに起因することでは無いと云う事だった。
なにかどうしようもない運命に引き裂かれる二人という設定は、何色にも塗れなかった僕が選んだ最高の絵具だろう。
未来に絶望した僕等は、ある決断をする。
それは来世にその望みを託すという選択。
そしてそれは、僕だけが生まれ変わるという奇妙な物語。
僕は誰かの子となり、ある世界に産まれた。
彼女は僕を探し出し、彼女が僕を育てた。
お互いに愛し合ったいつかの記憶を胸に抱き、その為に生まれ変わったことすら理解していた。
そして、20年の月日が流れ、立派に成人した僕と、白髪交じりの彼女が向き合っている。
大人になった僕は、彼女を選ばなかった。
明日、いや、100年後、たとえ生まれ変わることが出来ても、僕は僕として生まれてくるのだろうか?
そして、愛するあの人を見つけ出せるだろうか?
いつの時もそうだった。
僕の手を掴むのは彼女だった。
僕が彼女の手を掴んだことは無い。
それは言い換えるならば、自分が傷つくのを恐れていたと言う事に他ならない。
恐らく僕は、彼女を探すことはないだろう。
自分の中だけで見える景色はいつも僕の思い通りだ。
そうして僕は大人になっていくのだろう。
ちゃんと終りをくれたあなたに、お礼を言わないといけないね。
あなたから始まったこの恋は、あなたが終わらせてくれた。
僕は、ありがとう以上の言葉を探した。
今はまだ見つからないその言葉を彼女に伝えることでこの恋は終わると思っていた。
彼女との思い出だけは忘れまいとする想いは、同時に未来が無いことを悟らせる。
彼女と二人で見た夢は叶わない。
記憶の絵具は、また同じことを繰り返すだけかも知れない。
それでも、その度にあの喜びに包まれるのであれば決して悪くない。
それは同時に耐えがたい痛みと苦しみを伴うだろう。
でも、あなたが居なくなることがわかっていても、またあなたと出会いたい。
僕はさみしいよ。
あの日からどれだけ時が過ぎても、あの日の記憶が消えてくれない。
あの頃の僕が語りかけてくる。
高速道路を降りて直ぐに電話を鳴らした。
何度コールをしても、彼女は出ない。
家の近くまで車を走らせ、電話をした。
辺りは暗くなり、そして、深夜となった。
雨が降って来た。
その頃、携帯の薄暗い緑の液晶が消えた・・。
公衆電話を探す。
また、電話をした。
何度も、何度も。
ずぶ濡れになった。
車を出て、公衆電話と向き合う。
隣の自動販売機で甘い缶コーヒーを買った。
“温かいな”、ホットが売っていて安心した。
ゆっくりと、冷たいコーヒーになるまでゆっくりと飲んだ。
そうして、朝が来た。
彼女は出なかった。
僕は尚も電話を鳴らす。
“トゥルルルルル・ガチャッ・・・・・・・”
「もしもし、もしもし、」
「はい。」
「えっ、あの、原田です。裕子さん御在宅でしょうか?」
「いえ、おりません。」
「・・・・・・裕子さんの卒業式の日にお会いしました原田です。申し訳ございません。裕子さんともう一度きちんとお話がしたいのですが・・・。」
「・・・・・もう話をすることは出来ません。」
「そこをなんとかお願いできませんか?」
「・・・・・・・・・。」
「しつこいことは承知しています。でももう一度だけお願いします。」
「うぅぅぅ・・・・・・・・・・・・くっ。無理です。」
「・・・・・・・そうですか・・・。」
「あなただけじゃありません。私たちももう、あの子と話すことは出来ないんです。」
「・・・・・・あの・・・・・・裕子さんに何かあったのでしょうか?」
「・・・裕子はもう・・・・うううっ、おりません。」
「あの・・・・・・」
「ガシャン・・ッ-ッ-。」
僕と彼女だけの電話はもう、その意味を持たない。
僕は、僕だけが彼女に差し述べることが出来る魔法の杖を放棄したのだ。
彼女もまた、同じだったに違いない。
消せない記憶に隠された懺悔の想いは、未熟な二人を透かして見せた。
ここへ来た時と同じく、急発進で車を出した。
高速道路の入り口までは、心臓が張り裂けるほど乱れていた感情は、真っすぐ続く障害の無い道を走らせていると、ようやく一つに集約された。
悲しいよ。
涙が止まらなかった。
ただただ悲しかった。
どこまで走っても涙が止まることはなった。
この時流した悲しみの涙は、その後すぐに後悔の涙に変わった。
いつの時も僕は、無くすことへの恐怖、言わば自分自身への憐憫ばかりで、本当の意味での愛憐など無かったのだと理解出来るのはまだずっと先の事だ。
気にして無くても入ってくる情報はあっても、気にしているものほど得られないものだった。
彼女の活躍の場は、彼女の思い描いたものでは無かったのだろう。
挫折か適正か、それとも彼女の決断なのか、自らを子供では無いと言った彼女は、何色に自分を塗りたかったのだろう。
今となっては知る由も無い。
あの日、自分可愛さに小さな勇気一つを持てなかった僕。
ずっと以前から、自分自身と戦っていた彼女をその苦痛から救いだせたはずの僕。
無くして感受しようとするその行いは、子供だった僕が経験した小さな世界。
本当に無くしてはいけないものは、後悔の想いにかたちを変えて片時も僕の隣を離れることは無い。
“最後に彼女は大人に戻れたかな”
肌寒い海風が心地よく感じる。
もう少しすれば、空の色と重なって、目の前の景色ももっと青に染まるだろう。
今、僕が見ている景色は僕だけのものでは無いとわかったあの日から、どれくらいの出会いがあっただろう。
とても簡単なことなのに、うまく伝えることが出来なかったあの日はいつのことだろう。
記憶は上塗りされるものだけど、最後のページが最後の記憶とは限らないと知ったあの日。
どこか途中の1ページを大切に閉まって生きて行くことが大人になる事だとわかった。
だれかの震える心を救えなかった事など、あれから幾度経験したことだろう。
それら全てが、僕の生きて行く意味となっている。
“僕は頑張ったよ。”
“僕は大人になったよ。”
誰よりもあなたに見ていて欲しかった。
大人になっていく姿を、大人になった僕を、あの頃に戻ったあなたと一緒に。
僕の声はもう、届かない。
届ける必要もない。
大人になる過程で無くした涙は、年を重ねて僕の所に帰ってきた。
止めどなく流していた、どこに向けたものかもわからぬあの時の涙は、あなたの代わりに流した涙。
ふっとやわらかな海風に包まれた。
昼下がりの海岸線は僕を過去へと、そして未来へと走らせる。
言うなればそれは、僕が今を生きていると云う事。
そしてそこは、あなたがいない世界。
“僕が此処にいると言う事は、あなたが居たという証しになるのかな”
眼下に広がる、“どこまでも惹き込まれるその青色”はどこかで彼女と繋がっている気がしていた。
あの甘い海の香りはあれ以来僕の元に訪れることはない。
もう二度と会う事の叶わないあなたへ。
そっちはどう?
先ずは僕の話から始めようか。
何から話せばいいだろう、なにしろ僕は失敗の連続だったからね。
そうだなぁ、まずは、あなたと過した半年間は一言で言えば遠い昔話だ。
あの頃僕は20才だった。
あなたと出会うまでの、それまでの月日を合わせてもまだ足りない、40才を過ぎてようやく、あなたと向き合えているよ。
あなたが僕のあなたで無くなった日から、そしてあなたの大切な人達のあなたでさえも無くなった時から、僕のところに現れるあなたは、いつも悲しみと苦しみ、そしてさみしさと一緒に遣って来ていた。
手の届かない筈のあなたに辿り着いてしまったことは、僕の最初の失敗だ。
そして、自らの尺度で小さな世界を飛び出してしまったことは次の失敗。
もがき苦しむ中で僕の所へ会いに来てくれなかったのはあなたの意地悪と言うべきか。
現実の自分を理解しつつも、理想の大人を演じ続けてきたこの20年は失敗と云う名の僕の人生そのものだ。
文字通り、何かに敗れて失うことは、僕が人として生きてきた時間であり、結果だ。
失う事を繰り返す。言い換えるならば、それだけ多くの何かを得るからこそ失ってきたと云えると思わない?
僕がこれまでの人生で失ったものは100や200じゃ足りない。
あなたと出会った頃の僕は、いくつの何かを持っていたのかな?
人は生まれて来るときに持っているものは両親や兄弟、あとは自らの命くらいのものだ。
それから人は、何かを得る為に歩き出す。
容あるもの、それは友や、恋人や子供だろうか。
見えそうで見えないもの、友情や愛情、他にはなにがある?
ありそうでないもの、見栄や恥、意地や勇気かな。
必要であり不必要なものもあるよ、金や名誉や情報や、挙げればキリがない。
そして僕が、どうしても失いたくなかったあなた。
僕のあなたでなくとも良かった。
あなたを失いたくは無かった。
あなたを無くした僕が、それと引き換えに手にした何かに気が付くまでに失った時間は、20年だった。
20年と云う歳月とあなたを無くした僕が手にしたものは、たった一つの言葉だとしたらあなたはどう思うかな?
あの時のあなたと、最後の時のあなたに、どうしても伝えたい。
いや伝えなければならなかった大切なことば。
「○○○、○○○○○○○よ。」
今、やっと君に届けることが出来る。
大人になれないと言った青年がいた。
随分時間が掛かってしまったけれど、僕は成りたい自分になったよ。
そう、僕は大人になったんだ。
投稿者のプロフィール
最新の投稿
-
-
2022.05.11.
福岡小説 どこまでも惹き込まれるその青色 -
-
2017.03.07.
福岡小説 第十話 あなたの為なら(小説:モテすぎた男) -
-
2017.02.21.
福岡小説 第九話 迷い(小説:モテすぎた男) -
-
2017.02.07.
福岡小説 第八話 深夜の多忙(小説:モテすぎた男)