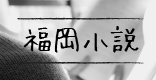第二話 工作(小説:モテすぎた男)
記事内にプロモーションを含む場合があります
木曜日の19:00だというのに、毛利則之の経営する炉端焼きのお店は、既に満員御礼の繁盛ぶりだ。彼は炉端焼きのお店を3店舗と和食の定食屋とイタリアンのお店を経営している。
どの店も皆が知っている程の繁盛店で、同級生の中でも一番の稼ぎ頭かも知れない。
「お前、またやるのか?」
カウンター越しに毛利が話しかけてきた。
「ああやるよ、前回もまあまあだったからな。こんないい仕事ないよ。利益率ほぼ100%だ。今にお前の稼ぎ追い抜いてやるからな。後、ビールお代わり。」
そう言って空になったジョッキをカウンターに上げた。
「でもな、今回はちょっと集まりが悪いんだよ。」続けざまに田村秀明は言った。
セミナー主催会社を経営する田村秀明と毛利則之は、小学校の時からの幼馴染だ。
「いい年して、そんなことで金稼いで、そんなの仕事って言えるのか?」
「うるさいよ。金は金だ。金が無くて、ただ飯食わせろって毎日来られるよりマシだろ。」
「それもそうだな。で、なんだそれは?邪魔臭い紙広げて。」
そう言ってお代わりの生ビールを田村に手渡した。
「これか?今回の応募者のリストだ。」
「なんだ、随分来てるじゃないか?それでも少ないのか?」
不思議そうに尋ねた毛利に、田村はにやけ顔で返した。
「あのなぁ、誰でもいいってわけじゃないんだよ。ある程度の商品じゃないと売れないだろう?見るからにかつらですって50歳の貧乏じじいが来ても俺もお手上げだよ。ちょっと指導すればものになるって奴を選別する。そうすればうちのセミナーの評判も上がるってもんだろう。」
「何言っているんだお前、そういう人達の為の講習会じゃないのか?ちょっと見せてみろ。」
そう言って半ば強引に田村の手から応募者リストを取り上げた。
「おい、一応、個人情報ってもんがあるんだよ。返せ。あと、うちのからくり外でべらべらしゃべるんじゃないぞ。」
「なかなかいいメンツじゃないか。」
「いいから返せよ。」強引に取り返そうとした田村に対して、「ちょっと待て。」
と、毛利の手が停まった。
「どうした?」怪訝そうな顔で見つめる田村に向かって毛利が続けた。
「こいつなんて、えらくモテそうじゃないか?」
「ああ、谷川旬さんなぁ。モテそうだよな。でもな、モテるというのと、彼女が出来るというのは違うんだよ。そこがうちのセミナーの売りでもあるんだ。」
自信気に語る田村の言葉に、適当な相槌を打ちながら答えた。
「そうか。それなら一度、俺も参加してみるか。」酷く険しい表情の毛利に対して、
「お前、なんて顔しているんだ。そんなマジになることじゃないよ。お前、かみさんに逃げられて寂しくなったか?気ままな一人暮らしを謳歌しているとこだろう?」
茶化した田村に、毛利が言った。
「子供が2人一緒だよ。なあ、田村、参加者少ないなら俺の方で何人か声かけようか?」
「本当か?助かるよ。期待しているよ。」
田村の陽気な返答は、毛利の耳には届かなかった。
“谷川旬かぁ、なんであいつがこんなセミナーに参加するんだ?あいつふざけやがって。”
翌日、毛利は常連客の瀬尾博之に電話を入れた。
「瀬尾ちゃんか?俺だ。ちょっと頼み事あるんだけどな、今日城南の店に来てくれるか?」
「わかりました。20:00でもいいですか?大事な会議があるんで、少し遅くなりそうです。」
瀬尾博之は今年35歳の外資系エリート金融マンだ。過去に一度田村のセミナーを受講していた。
「全然構わないよ。待っている。」
20:00ピッタリに瀬尾は毛利の店にやってきた。
毛利の城南のお店はイタリアンレストランだ。全面ガラス張りで、テラス席もあるお洒落な店内には、4組程の客が楽しそうに食事を楽しんでいる。
毛利は瀬尾に気が付くと、奥の個室に案内した。
「悪いな急に、赤でいいか?」
「はい、で、どうしたんですか?」
店員を呼び、赤ワインを2杯オーダーしたところで、
「たいしたことじゃないんだよ、田村のとこのセミナー前に行ったことあっただろう?あれどうだった?」
「ああ、あれですね。なかなか的を射ていて参考になりましたよ。まあそれで彼女が出来るわけでは無いでしょうけど、目から鱗な話もいくつかありましたよ。」
「で、瀬尾ちゃんは良い人出来たの?」
「残念ながら、まだ。でもそれがどうしたんですか?」
「いや、俺も行ってみようかと思ってね。事前に情報を仕入れとこうかとね。」
「毛利さん行くんですか?いったいどうしたんですか?それに田村さんに直接聞けばいいのに。」
「案外そういうところは線引きがきちんとあるものなんだよ、同級生とは言えね。」
店員が赤ワインをテーブルへ運んできた。
それじゃあ乾杯とは言わずに、「もう一回参加しないか?」と瀬尾に切り出した。
「いや、30万円はきついです。」という瀬尾に「当然参加費は俺が出す。一緒に来てくれよ。」
とお願いした。
「だったら全然行きます。アシスタントの女性が綺麗なんですよ。あの子が居たらいいな。」
陽気に言った瀬尾に毛利は顔を近づけた。
そして、もう一つお願いがあると告げたあとにこう続けた。
「もう一人参加者を見つけてくれないか?それも瀬尾ちゃんに頭があがらない人間で、尚且つパソコンの操作に詳しい奴だ。そうだな、システムエンジニアなんかが最適なんだが。」
瀬尾は困惑した。
矢継ぎ早にお願いされたが、そんな条件に見合う人間など、おいそれと見つかる筈もない。
「毛利さん、どうしたんですかいったい?それいつですか?ちょっと自信ないなぁ。」
「来週の土曜日だ。なんとかなるだろう。」
「来週ってもう一週間しかないじゃないですか。いくらなんでも無理です。」
瀬尾はきっぱりと断りを入れた。
その時だ。毛利は途端に厳しい表情になった。
「おい、あんまり焦らすなよ。本気で引き受けないつもりか?」
一瞬、沈黙した瀬尾だったが、その場でスマートフォンを取り出して何人かに連絡を始めた。
そして、暫くして、
「毛利さん、何とか一人見つかりました。」
瀬尾は嬉しそうに言った。
「そうか。ありがとうな瀬尾ちゃん。今日はなんでも好きなもの食べて行けよ。」
「あの、毛利さん、そいつの参加費はどうしたら・・」不安そうな瀬尾が聞いた。
「俺が出すに決まっているじゃないか。後な、いくつかお願いが残っているんだ。」
「まだあるんですか。なんでしょう?」瀬尾は今にも泣き出しそうだ。
「そんな顔するな。なんてことは無い。そいつとセミナー前に会いたい。段取り付けてくれ。あっ、瀬尾ちゃんも同席な。」
「はい。わかりました。予定確認しときます。それだけでいいんですか?」
後は三人の時に話をしようと言って、毛利は笑顔を見せた。
その笑顔とは対照的に、瀬尾の中には言い知れぬ恐怖が広がっていた。
その日飲んだワインの味はよく覚えていない程だった。
それから二日後、瀬尾は毛利の店の前回と同じ個室にいた。
そこに同席していたのが、明石慎也32歳、容姿体格共に標準で、独身彼女無のシステムエンジニアだった。
二人はここで、毛利の到着を待っている。
毛利からは何でも好きなものをオーダーして先にやっていてくれと言われていたが、そうはしなかった。
これから、毛利に何をお願いされるのか?
やや緊張の面持ちで、只々椅子にもたれ掛かっていた。
「ここ、こんな個室在ったんですね。知りませんでした。」
明石慎也は何度かここを訪れたことがある。
お洒落で、高級な雰囲気ながら、サンダルでも気軽にはいれるこの店が気に入っていた。
将来は“自分もこんな店を持ちたい”と考えていたほどだ。
「瀬尾さんが、ここのオーナーさんと親しくしているなんて知りませんでしたよ。」
毛利に会えることが自身のプラスになると思っているのだろう。嬉しそうに明石は言った。
「ああ、すごく優しくていい人だ。元々は只の常連客だったんだけどな。
ここじゃなくて、炉端の店な。それからちょっとした縁で親しくなったんだけど、なんか違うんだよ。」
「何がですか?」
「普段の毛利さんとだよ。なんとなく、いや全く違うよ。」
瀬尾がそう言った直後に、毛利が個室に入ってきた。
「やあ、あなたが明石さんですか?態々ありがとうね。」
「初めまして、明石慎也です。毛利さんの事は、瀬尾さんからいろいろとお聞きしていました。お会いできてうれしいです。」明石の言葉は、お世辞ではないようだ。
「瀬尾ちゃん、俺の悪口ばかり言ってんじゃないの?」
「そんなわけないじゃないですか。そもそも毛利さん有名人でしょう?こんな立派なお店何件も経営されていて。」瀬尾の言葉には多少お世辞が入っている。
仮に瀬尾の言葉にお世辞が含まれていたとしても、その実、毛利は飲食業界の成功者としてこの街では認知されているに違いなかった。
まあ当然、彼のことに興味など無く、彼を知らないものもごまんといるが。
「そんなことより、先ずは乾杯と行こうか。」
毛利の合図で、三人の晩餐が始まった。
一頻食事を楽しんだ後で、毛利が初めた。
「今日集まってもらったのには、当然理由がある。今から話をすることはすべて内緒にしてくれ。当然田村にもだ。」
瀬尾も明石もワイングラスから手を放し、背筋を伸ばした。
「来週の田村のセミナーに、ある男が参加することを偶然に知った。その男を嵌めたい。多分、いや確実に相手は俺のことを知らない、筈だ。仮に知っていても顔まではわかっていない。先に言っておくが理由は聞かないでほしい。その男とはちょっと在るんだ。
そこで、俺は直接接触しないから、君たち二人で近づいて欲しいんだ。」
「どうやって近づくんですか?」不安そうに尋ねる瀬尾を制して、毛利が続けた。
「それを今から言う。原則的に君たち二人も俺も、みんな赤の他人という設定で会場では振る舞う。それと無く田村には言っておくが、あいつもその方が都合が良い筈だ。参加者数人が知り合いというのはあいつも他の参加者に知られたくはないだろう。ここまではいいか?
これからが大事だ。
ターゲットの名前は谷川旬、29歳の小僧だ。
こいつは小さなIT関係の会社を経営しているのだが、現在開発中のコンテンツに少なからず注目が集まっているらしい。
だが、同時にそれなりの問題も抱えているようだ。資金の手当てから、人材の確保その他にもいろいろだ。」
毛利は、頭は切れる方だが専門は飲食だ。ITのことなどわからない。
「そこでだ。フリートークの時間や、休憩時間それらを使って、まず瀬尾ちゃんが接触する。
瀬尾ちゃんの会社から資金提供の可能性があることを匂わせる。どういう展開になるかはわからんが如何とでも話はできるだろ?」
「実際に資金提供はする必要はないんですよね?そうなると私の一存では決められることでもないし、その谷川旬って人の会社状況も大きく関係してきます。」
瀬尾は至って冷静だ。
「瀬尾ちゃんに聞きたいんだが、仮に、一度出資なり、何なりで出した金をこちら都合で引く上げることは可能なのかい?」
「可能とも不可能とも言えます。契約次第なので。そういう話ですと増々うちの会社を使ってというのは厳しいと思います。」
「わかっている。だけどアドバイザー的な立ち位置で何らかの資金調達手段は助言できるだろう?個人投資家から集めるだとか、とにかくなんとでもなるだろう。実際のところ、金が欲しければ飛びつくはずだ。」
「それはそうかも知れませんが、本当にお金が集まるかどうかは疑問です。多分集まらない可能性の方が高いと思います。」
「大丈夫だ。金は俺が出す。」
それならば、問題ないだろうと言わんばかりの毛利だった。
実に乱暴な計画と思っていたが、毛利が金を出すというならそれほど無理難題ではないと瀬尾は思った。しかし、それ以上にこの話そのものが全く意味不明であった。
そして、その続きがどう考えても難しかった。
「それでだ、明石君に谷川の会社に潜り込んでほしい。」
「それは無理ですよ。いくらなんでも。」明石の代わりに瀬尾が答えた。
「相手の都合もあるだろうし、100歩譲って谷川って人はウエルカムでも、明石君はどうするんです?今の勤め先を退社しなければいけないし、その後その谷川って人の会社を駄目にする計画でしょ?明石君仕事を失ってしまうじゃないですか。」
瀬尾の正論を横目に、明石は事の成り行きを無言で見ていた。
そして、すぐに毛利が答えた。
「もちろん、明石君の考えを聞いてからのことだが、俺も、ただでお願いしようってわけじゃあない。」
「お金ってことですか?」明石が口を開いた。
「君がお金で動く男だとは思っていないよ。だが金で話が付くならわかりやすい。」
毛利のシンプルな提案に明石は乗った。
「毛利さんは僕の思っていたのとは、違う人みたいです。生意気に聞こえるかもしれませんが、ただ目の前のことを粛々と熟した結果が今なんだと思っていました。だけど、実際は非常に策士だ。それでいて、大事な部分は回りくどくなくてわかりやすい。好きですよ、そういう人。」
明石の言葉に毛利は思った。
明石さん、本当はあなたの想像は間違ってなどいないよ。と。
本来は工作など企んだことも無ければ、人様を巻き込んだりもしない。
今回だけ、今回だけは特別なんだ。
二人のやり取りに瀬尾は完全に置いてきぼりだ。
二人が合意したと言うなら、自分がとやかくいうことではない。
ここ最近の毛利さんは人が変わったように強引だと感じていると共に、明石の奴も案外やるもんだと感心していた。
「明石君、退職金替わりのつもりで、2,000万円でどうだ?」
「十分です。ただ毛利さん、その谷川さんの会社に潜り込めなかった時はどうなるんです?」
「それは考えていない。なんとしてでもそうして貰わないと困る。」
二人は、只々毛利の絵も知れぬ雰囲気に押されるばかりだった。
同じころ、近藤は真っ暗な部屋でパソコンと向き合っていた。
勤務先の役場から、不正なアクセスにより抜き出した個人情報を確認していた。
近藤将彦27歳 町役場勤務で高身長の痩せ男。
彼もまた、来週開催の田村のセミナー参加予定者だ。
そして、彼が手に入れた個人情報の名前は、藤原明日香。
彼女が転居届を提出した窓口で、応対したのが近藤だった。
これまで真面目に、生きてきた。
一流ではなかったが大学を卒業して、親の勧める通りに、公務員になった。
彼女が居たことはない。居たことは無いがそれは、そう思える女性と出会っていなかった為だと自分では思っていた。
そう思っていたところに現れたのだ、理想の女性が。
一目見た瞬間から恋に落ちた。
彼女のこと以外は考えることも出来ず、運命の人と出会ったと確信した。
彼女にとっても自分は運命の人だという結論に達した時には、もう、不正に手を染めていた。
こうなるともう彼を止めるものなどない。
判明した住所地を訪れ、不法に部屋に侵入した。
彼女の部屋の合鍵を作る以外は実に簡単だった。
役場の市民課に勤務する近藤将彦にとってなんとも楽な仕事だった。
藤原明日香の不在を確認して、部屋に忍び込んだ。忍び込むというには不釣り合いなほど、堂々と入って行った。
まるで、恋人の部屋を訪れるかのように。
近藤は藤原明日香と出会うきっかけを探した。
カルチャー教室、スポーツクラブ、何でもよかった。
同じ空間で話をする時間さえあれば、“僕たちの運命が二人を紡ぐ。”という確かな思いが存在していた。
そのため彼は、藤原明日香のクローゼットを開けるまではするが、盗聴器を仕掛けたり、下着を探すような卑劣な行為はしなかった。
そこには彼の強い想いが存在していた。
“一緒になってからでいい、そんなことは。どうせすぐにそうなるんだ。”
そして、テレビボードの上に無造作に置かれた封書を見つけた。
中に一枚だけの簡易的な誓約書が入っていた。
来週の土曜日に、サン・ライフホテル会議室で行われるセミナーに関する守秘義務契約書と、勤務内容、報酬に関する覚書であった。
“これだ”それをメモして部屋を後にした。
マンションの敷地を抜けたところで、セミナー主催会社へ参加の申込電話をした。
電話口の女性からは
「定員が迫っており、参加頂けるかは折り返しの連絡とさせて頂いております。後、大変お手数ではありますが、所定のシートを送らせて頂きますのでご記入、写真添付の上、返送頂きますよう皆様にお願い致しております。予めお伝えしておきますが、今回お送り頂きますエントリーシートはお返しいたしておりませんので、よろしくお願いいたします。」
実に丁寧に受け答え頂いた。
要するに沢山の希望者を集めて、炙れたものは次回のターゲットにでもするんだろう。
今時、個人情報を吸い上げ、そのうえ返却もしないなど聞いたことも無い。
なんともいい加減な会社だ。
だが、このセミナーに参加出来なくては何も始まらない。
”運命“が二人を結びつけるであろうが、時に運命は悪戯好きだ。
エントリーシートには地域活性化の施策として御社との連携を考えているとでも書いておけば間違いなく選ばれる。
ただ心配なのは、この会社がいい加減だという事だ。
「エントリーシートくらいちゃんと目を通せよ。」呟きながらポケットから何かを取り出した。
藤原明日香の部屋のカギだ。
近藤はそれをおもむろに放った。
鍵は植木の茂みに消えて行った。
もう必要のないものだ。こんな行為を働いて藤原明日香には悪いことをした。でも、二人の未来には必要だった。きっと気付くさ。
今はまだ運命に気付いていない君だけどね。
近藤の想いは適正か、正善か。
かくして来るセミナーに向け、それぞれの思惑を抱えた参加者6名が決まった。
藤原明日香、近藤将彦、毛利則之と瀬尾博之、明石慎也、それと谷川旬だ。
他にはどのような参加者が訪れるのか。
田村の殖利のセミナーは、その姿を変えようとしていた。
投稿者のプロフィール
最新の投稿
-
-
2022.05.11.
福岡小説 どこまでも惹き込まれるその青色 -
-
2017.03.07.
福岡小説 第十話 あなたの為なら(小説:モテすぎた男) -
-
2017.02.21.
福岡小説 第九話 迷い(小説:モテすぎた男) -
-
2017.02.07.
福岡小説 第八話 深夜の多忙(小説:モテすぎた男)