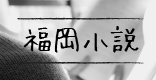第五話 再会(小説:モテすぎた男)
記事内にプロモーションを含む場合があります
博多駅から中洲まではタクシーで10分程度だ。
外は土砂降りの雨が路面を打ち付けていた。
其々お酒の入った参加者達をスマートに誘導出来そうもないことを感じた田村は、自身の周りにいるものからタクシーに押し込んでいった。
「中洲の第三ビルまでお願いします。」
タクシーの運転手に告げ、次の者達をまた乗せる。
最初のタクシーには、毛利、瀬尾、明石が乗った。
次のタクシーには、佐藤と、三上、そして和田が続いた。
最後のタクシーには谷川旬と田村、それから藤原明日香が乗り込んだ。
乗り込んだというのは正に相応しい表現であった。
当初の予定通りならば、藤原明日香は先程の会食で本日の業務終了の筈であった。
それなのに、谷川旬を後部座席奥に誘導した後、自らもまさに乗り込んで来たのだ。
田村はなにも問い掛けること無く助手席に座った。
「中洲の第三ビルまで。」
そう言った後は貝にでもなったように口を噤んだ。
そして、タクシーの助手席で、後部座席の会話に聞耳を立てていた。
「やっとゆっくり二人に成れました。すごく嬉しくてすごくざわついて、でも、すごく落ち着きます。」
俺の存在など空気なんだろうと思いながらも、谷川の返答に傾聴した。
「そうですか。僕はドキドキしているだけですよ。ずっと。ただ、さっきは急すぎて出てこなかった答えが見つかりました。藤原、いや佐竹のあすかちゃん。」
「しゅんちゃん、、、ううっ、、、、思い出してくれたんですね。」
藤原明日香は中洲第三ビルに到着するまで泣き続けていた。
田村は振り向くことは勿論、出来なかった。
フロントガラスを打ち付ける激しい雨が、しっとりと泣き続ける藤原明日香とは対照的で、
目の前の雨が悲しみならば、彼女のそれは喜びのまたその上にあるものなのだということは、二人の表情を見ていない田村にも理解出来た。
田村はセミナーでよく使う表現のひとつを思い起こしていた。
“ドラマはひとり一人にある。”
月曜日の21時が定番の「恋愛ドラマ」はテレビの中だけの話ではない。
今はもう皺くちゃになったお爺さん、お婆さんにも、そして、ようやく自我に目覚める3歳程の子供にもドラマはある。
そしてそれは、日々のことで有ったり、人生を通して忘れる事の出来ないもので有ったりするのだ。
藤原明日香のドラマはまさに、今日であり、この再会であろう。
そしてそのドラマは、彼女だけのモノではなく、谷川旬も、ともに背負っているもので有ったか、彼にとっては今日がそのドラマのスタートになるのか迄は、わからなかった。
唯一つわかったことそれは、自分が佐藤に出来ることは何も無い。ということだった。
一方で、毛利が乗ったタクシーの中では念密な報告が行われていた。
「どんな感じだ?瀬尾ちゃん。時間が無い、簡単に、だけど、正確に教えてくれ。」
「行けそうです。彼はこっちの話に乗って来そうです。何故かというと、」
「詳細はいい。夜中に聞く。初めての接触から、明石君の合流のタイミング、そして今現在どこまでの話になっているのかだけを教えてくれ。」
「わかりました。始めましてはのタイミングは至って普通です。こんにちはから始まってどのようなお仕事されているんですか?私はこんな仕事をしています。何かお力になれることがあるかも知れませんね。という感じです。その後は彼のビジネスの話を細部に渡って聞きました。」
「それで?」毛利が聞いたタイミングで、明石が代わって話し始めた。
「谷川さんと瀬尾さんの話をずっと聞いていました。それからそろそろだなというタイミングで、“何をそんなに盛り上がっているんですか?僕も仲間に入れてくださいよ”と言って接近しました。」
「もう直ぐ店に着く。それで、今は何処までの話になっている?」
毛利の質問は、瀬尾が締めくくった。
「ほぼ、全て話し終えています。明石君の転職までOKと言っていたくらいですから。勿論、入社条件や待遇、出資金額やその仕様までの話は出来ていませんが。」
「そうか、わかった。上出来だな。クラブではあまり接近するな。あまりにも目立つし、周りも何かを勘ぐり出すかも知れない。
次の店ではなにも意識ぜずに普通に楽しんでくれ。 ただし、あまり飲みすぎるなよ、瀬尾ちゃん。」
「わかっていますよ。大丈夫です。」
「ようこそクラブアマルフィへ」店長の柴田の出迎えで店に入った。
広い店内は豪華な装飾が成されていて、4人掛けのボックスが4つ、6人以上が座れるボックスが4つ、それとVIPルームと呼ばれる個室が1つあった。
その日は23:00まで貸切でお願いしていた。
通常このようなクラブが定休日以外の日に時間貸切など滅多にさせるものではない。
だが、田村の恋愛セミナーの模擬恋愛場としてクラブ「アマルフィ」が使われるのは今回が三回目である。
店内に入るなり、三上が一番奥にある四人掛けのテーブルに毛利を誘導した。
基本的に模擬恋愛の場として貸し切って居るわけであり、参加者一人にホステス一人付くのがお決まりだ。
参加者が皆で楽しむ目的ではないのだ。
しかしながら田村は、それを横目に見ながら、気付かないふりをすることにした。
“三上にどんな魂胆があろうと、自分自身が毛利を憎んでいようと、そして和田が言っていたおかしな空気があろうとも、恋愛セミナーを定番セミナーとして成功させることが一番の目的なのだ。先ほどは自身の至らなさから近藤という脱落者を出してしまった。
さらにその原因とも言える藤原明日香が、谷川旬を追いかけてこの店に来ている。
彼女が言っていたように近藤の動きは多少なりとも気にかかるところだ。
何らかのクレームを言ってくることは勿論、藤原明日香への個人攻撃の可能性だってあるのだ。
更に気掛かりなのは藤原明日香へ想いを寄せる佐藤に如何に報告するかだ。
それだけでは無い。
和田に対するフォローも必要であろう。
忙しくなりそうだ。
田村は店長の柴田を呼んで采配をお願いした。
「店長、奥の二人には大人しい聞き上手な控えめな子をお願いします。
それ以外は一人ずつ掛けさせますので、其々にホステスさんを付けてください。あと、あちらの男性には何方も付けて頂かなくて結構です。」
「承知いたしました。」柴田はそう返答すると、すぐに待機していたホステスたちに指示を出した。
田村の云うあちらの男性とは勿論、谷川旬のことだ。
三上達とは真逆の店内奥のテーブルには谷川旬と藤原明日香が並んで腰掛けていた。
向かい合わせのように仕切られた二つのテーブルには瀬尾と明石が其々腰を下した。
広い通路を隔てた反対のテーブルには佐藤が、その隣には和田が陣取った。
田村はと云えば、谷川旬達のテーブルとガラス板一枚挟んだテーブルに着座した。
谷川旬のテーブルの話は耳を澄ませば聞こえる距離にあり、それ以外の参加者達も一目で見渡せる位置だった。
ただ一席、三上と毛利のテーブルだけは立ち上がっても見えない、当然、話し声など聞こえるはずもなかった。
其々のテーブルに女性が付いた。
その直後、瀬尾の大きなそして驚きの声が聞こえてきた。
「なに、どうして?なんでここにいるの?」
「どうしてでしょう。元々わたしはここで働いているんですよ。以前のセミナーへは田村さんにお願いされて参加したんです。」
「そうだったんだね。嬉しいよ。また会えるなんて。」
「そう言って頂けてうれしいです。」
今回の藤原明日香同様に、以前のセミナーにアシスタントとして参加した女性がクラブ「アマルフィ」に在籍していたのだ。
この再会は瀬尾には予想外にして最高の収穫であった。
以前一度出会っただけのこの女性に心奪われ、もう一度逢えないものかと悶々とした日々を送っていた。
安田優里奈というこの店一番人気の女性だった。
投稿者のプロフィール
最新の投稿
-
-
2022.05.11.
福岡小説 どこまでも惹き込まれるその青色 -
-
2017.03.07.
福岡小説 第十話 あなたの為なら(小説:モテすぎた男) -
-
2017.02.21.
福岡小説 第九話 迷い(小説:モテすぎた男) -
-
2017.02.07.
福岡小説 第八話 深夜の多忙(小説:モテすぎた男)