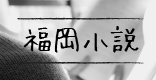第十話 あなたの為なら(小説:モテすぎた男)
記事内にプロモーションを含む場合があります
セミナー2日目は講師である藤原明日香を中心に、『女心』をテーマとした全員参加型のトークセッションからスタートした。
予定時間は9:30~12:00。
ランチ休憩までの2時間以上を割いていた。
朝の挨拶を簡単に済ませ、参加者全員の後ろ姿が見える位置に腰を下ろした田村は、つい先程までのことを整理すべく、深く椅子に座り直し、腕組みをして静かに目を閉じた。
20分程前に不意に毛利から連絡が入った。
「昨日は連絡返せなくて悪かったな。」
「ああ気にすることは無い。それよりも大丈夫か?昨夜はなんだかお前らしく無かったぞ。」
心配していた素振りを見せた田村に対して毛利は早口で語った。
「大丈夫。少し悪酔いしただけだ。と云う訳で今日はすこぶる体調が悪い。申し訳ないんだが今日のセミナーは欠席にしてくれないか?」
毛利の発言は、昨夜和田と話し込んだ田村には予測出来たものだった。
というのも毛利から連絡が入る1時間ほど前、田村は自室で谷川旬の訪問を受けていた。
“どうしても今日のセミナーには参加できない”
そのことを彼はお詫びに来たのだ。
理由は聞かなかった。
聞くまでの無くそれが、谷川旬本人の意思では無いことくらいはその表情から察するに余りあった。
田村は、心の内ではこのような事態を招いたことをお詫びするばかりであったが、今後起こるかも知れないなんらかの事態については語る事は無かった。
トークセッションは滞りなく進んでいた。
藤原明日香の講師ぶりは見事と表現するしかない程だった。
しかし、如何に彼女が上手にその場を回したところで、参加者達に“熱”が無ければそもそも成立しない。
それには近藤の協力が大きかった。
彼は積極的に発言した。
そしてそれは前日までの自身の彎曲した想いを発表する場では無く、今となっては恋愛成就に関心などないであろう参加者達を巧みに巻き込んで見せた。
しかしながら、唯一一言も発することの無い参加者も居た。
瀬尾だ。
いつの時も瀬尾の頭を支配するのは数年前のあの事だった。
日々忙しい時間を過ごしていた。
お金を扱う仕事だ、それなりに心労も多い。
顧客からの無理な注文や、会社からの強烈なノルマ。
それでも、完璧とは言わないまでも順調な人生。
の筈であった。
しかし、事態は突然急変した。
得意先の学校法人清和学園にリスクを説明せずに仕組債と呼ばれるリスクの高い債券を販売していた。
それが突然のリーマンショックで大きな損失が発生したのだ。
わずか一日にして、瀬尾は地獄にたたき落とされた。
学校法人清和学園からは、説明義務違反で訴訟されそうになった。
昇進を控えていた瀬尾は問題を穏便に解決するために、当時同じく顧客として面識のあった毛利から、その損失分を工面してもらい学校法人清和学園に返済したのだった。
“今自分がこうして平穏な日々を過ごせているのもすべて毛利さんのお陰だ。”
穴埋資金を捻出してくれた時も、その後もただの一度もそのことを引き合いに横柄な態度を取られたことなど無い。
しかも、月々僅か5万円という返済金額を申し出た瀬尾に、文句の一つも言わずに笑顔で
「無理しなくていいよ。」と言ってくれた。
今回だけなのだ。
毛利さんが毛利さんでは無いような、鬼気迫る、そして自分に高圧的な態度を露にしたのは。
きっと何かあるのだ。
今、あの人の役に立たなくてどうする。
その後も彼は、一言も発言することなく、その日を終えた。
可も無く不可もなく、午前の行程は終了した。
そもそも恋愛セミナーなど興味の無い三上にとっては、ようやく訪れた昼食の時間だった。
昼食として準備された仕出し弁当が参加者に配られる。
田村は和田の想いを汲み取って、その魂胆の真相こそ不明ながら、なんらかの思惑を持って自身に近付いていることを察している事実を、この時間を利用して三上に伝えようと決めていた。
勿論それは、三上に擦り寄る為の行動などでは無い。
これ以上、和田を傷つけることのないよう三上に忠告することが目的だった。
「三上さん、隣宜しいですか?」
「ええ、構いませんよ。」
田村は三上にすべてを伝えた。
三上は表情を変えること無く静かに聞いていた。
途中、一言も口をはさむこと無く田村の話を聞き終えた三上は、田村の肩にそっと手を置いた。
「ありがとうございました。あなたが居てくれて本当に良かった。」
そう言い残して立ち上がると、真っすぐに和田の元へと向かった。
意外な言葉を頂戴した田村は、和田の元へ向かう三上の背中を見ながらあの日の彼を思い返していた。
出会った当初の三上。
最近では感じる事の無かった、あの時と変わらぬ、力強く、誠実な眼差し。
“この人と仕事してみたいと強く思ったあの日が蘇っていた。”
三上は一人で昼食を取っていた和田の隣に腰を下ろした。
そして延々と昼食時間終了間際まで語りかけていた。
一方、田村は、三上の背中と、和田の横顔を余すことなく観察した。
三上の背中は凛として伸び、その後ろ姿からは疚しさや、卑劣さは微塵も感じ取れなかった。
和田はどうであろうか。
初めこそ、警戒心から来る緊張、そして疑心暗鬼や疑念、複雑に絡まった迷路に迷い込んだ青年は分かりやすく戸惑いの表情を見せた。
此処にきて田村は気付いた。
青年特有の真っすぐな感情に不埒な自分は怯えていたのだと。
なにも和田が特別な訳では無い。
人の裏を出し抜く事しか考えない男が、真正面から本心で向き合ってくる青年に恐れを抱く事は当然だと。
そして最後に和田は笑顔で三上に頭を下げた。
三上もまた、立ち上がり深々と深々とその頭を下げた。
他の参加者達には異常に見えるその光景も田村には理解出来た。
恐らく、いや、間違いなく三上は真正面からあの青年にぶつかったのだ。
そしてその思いは無垢な青年の心を突き動かしたに違いなかった。
二人の間で交わされた何かについて今、自分が知る必要も無ければ、知りたいとも思わない。
いつか二人が、いや二人のうち一方でも自分に助けを求めて来ることがあるなら、その時は全力で力になろう。
それが、三上にせよ、和田であっても、どちらかの営利の為でないことは確信が持てる。
田村は、もし、自分の判断が間違っていたとするならばその時は、自分なりの責任の取り方を既に心に決めていた。
一方、昼食の時間が終わる時間になって、瀬尾の携帯にメールが届いた。
見慣れないその番号は安田優里菜からであった。
“昨日は再会出来てうれしかったです。今日はお休みですか?ゆっくり体を休めてくださいね。”との昨夜のお礼の挨拶であった。
普段であるなら、気取った返信の一つも入れて、空回りするのが関の山であろう彼は、この日、咄嗟に電話を掛けてこう言った。
「今日、逢えないかな?どうしても逢いたいんだ。」
安田優里菜からの返答は意外なものだった。
「いいですよ。私も少し相談したいことがあるから・・・・」
「なにか遭ったのかい?」
「・・・自分ではどうしようも出来ない問題を抱えていて辛いです。」
彼女の真っすぐな言葉は瀬尾を奮い立たせる。
「ありがとう。僕に言ってくれて。それがどんな問題でも必ず僕が力になるよ。必ず。」
「すいません。心強いです。凄く・・・。」
「あなたの為ならきっと僕は何でもするだろう・・・。ありがとう。そう思える勇気をくれて。」
その後待ち合わせの時間を決めて電話を切った。
しかし、瀬尾は浮かれるでもなく、自身の言葉に酔い痴れるでも無く、そして先程の発言を後悔することも無かった。
ただ唯一の自分として、その存在のあり方を繰り返し自問自答するばかりだった。
事の首謀者である毛利は、自宅に帰る気にはなれなかった。
結果、いつものスポーツジムに立ち寄ることにした。
延々と泳いだ。どこまでも泳ぎ続けた。
何度ターンを繰り返したことだろう。
いつまでも、いつまでも、そしてまた、いつまでも・・。
どれ程の時間が経過した?
その頃にはもう重大な決断を下していた。
自分の中での迷いが消えたことを確信して、プールを出た。
シャワーで汗と共に自身の間違った感情を綺麗に洗い流して、スポーツジムを出た頃には辺りはすでに真っ暗になっていた。
そして徐に携帯電話を取り出した。
「瀬尾ちゃん、今大丈夫か?今日は勝手に欠席して申し訳なかったね。大事な話があるんだが、」
「お疲れ様です。全然構いませんよ。セミナーも無事終了しました。それと、明石君も欠席でしたよ、毛利さんの指示ですか?」
「いや、明石君の件は知らなかった。初耳だよ。どうしたのかな?まだお会いして間もないが、繊細そうな子だ。きっといろいろと悩んでいたのかも知れないね。」
「毛利さんも知らなかったんですね。どうしたんだろ?明石の奴。そんな勝手な真似して。今から連絡してきつく言い聞かせておきますよ。」
「いや、瀬尾ちゃん。それには及ばないよ。それよりも大事な話があるんだが、今から時間取って貰えないかな?」
「すいません。今からはちょっと。明日仕事終りで伺います。どちらに行けばいいですか?」
「そうか。それじゃぁ申し訳ないが、「瀬川」まで来てくれるかい?」
「はい。伺います。」
毛利は何としてでも今日、瀬尾と会うべきだった。
事態はもう、引き返すことの出来ないところまで進んでいた。
投稿者のプロフィール
最新の投稿
-
-
2022.05.11.
福岡小説 どこまでも惹き込まれるその青色 -
-
2017.03.07.
福岡小説 第十話 あなたの為なら(小説:モテすぎた男) -
-
2017.02.21.
福岡小説 第九話 迷い(小説:モテすぎた男) -
-
2017.02.07.
福岡小説 第八話 深夜の多忙(小説:モテすぎた男)